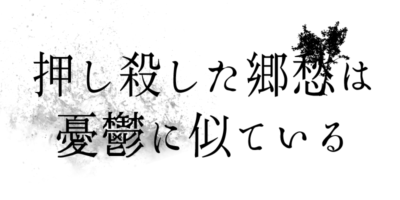過去話いつつめ ずかんを読んでほしい話
アンチ・アンチ・ヒーロー(ノット・ヒーロー)5
「そういうわけで、同じ部屋になった――あー、仮面だ。名前はないから、仮面でいいぞ」
そうして男に『九番』の部屋へ放り込まれた仮面が、最初に困ったのは、自己紹介だった。何しろ名前がないのだ。だから結局、自分から『仮面』を称することとなってしまった。それもそれで違うような気はしたのだが、妙な名前をつけられるよりはマシだったので、仮面は投げやりにそう名乗った。
「なんか、あれだ、仲良くやろうぜ」
九番と呼ばれる青年――いや、少年か――は、そんな仮面に、首を傾げて、その赤茶色の目を瞬かせると、部屋を出て行こうとしていた男に声をかけた。
「しょちょう。これ、もらっていいの?」
これ。また物扱いされている。別にいいけどよ。流石にこいつは初手からこっちを真っ二つにするようなことはしないだろうし。問われた男が、貼りついた笑顔で、返事をする。
「いいよ。好きにしなさい」
少年はその答えに破顔すると、えへへぇ、と幼い子供特有の間抜けな笑い声をこぼした。本当に頭の中がガキになってるんだな。可哀想だなー、と、仮面は、適当なことを思う。何があったか知らないが、こうなってしまっては人生おしまいだろう。元に戻せるのなら、男もとっくに戻しているのだろうし。いや、あの男と出会った時点で、人生は詰んでたのかもしれないが。でもそうなると、俺も人生詰んでるってことになるな。それはあまり考えたくない――それに実際のところ、仮面は自分の人生が詰んでいるとは、あまり思っていないのだった。死んだ方がマシだと思えるようなひどい目に遭わされたし、というか今も遭わされ続けているし、毎日謎の脅威に晒されたりもしているけれど、冷暖房完備の部屋で眠れるのは、やはり快適だった。それに、男の書棚から本を借りて読むのは、存外楽しかった。どういうつもりなのか、許可さえ取れば、どんな本でも貸してくれるのだ。まあ、それならと無断で借りた時は、重石付きで浴槽へ放り投げられそうになったが。流石にあれだけは、自分が悪かったと反省している。人のものを勝手に持ち出した上に枕にして眠ってはいけない。
「仲良くするんだよ」
男の、恐ろしいほど柔らかな声。ぞわっとするからやめろ、と言いそうになって、仮面は堪える。また壁に叩きつけられたくはなかった――はっきり言って、普通に痛いのだ。それに、この同居人が、下手にそんな手段を覚えたら困る。
「これが何かしたら、俺を呼んでいいからね」
「うん!」
少年が、ベッドに腰掛けたまま、足を揺らしてにこにこと頷いた。なんでだ。なんで俺が何かやらかす前提なんだ。どう考えても、こっちの方が子供な分危ないだろうが。俺がこいつの面倒をちゃんと見るだなんて期待してるんじゃねえだろうな?
「……別に、君にそういう期待はしてないよ」
「心を読むな」
読んでない、と言いながら、男はため息を吐く。
「君より、彼の方が付き合いも長いんだから、信頼するのは当たり前だろう」
それに、彼が何をするのかは大体予測がつくから対策も対処もできる。そこで男は、珍しく冷淡とも思える目で仮面を見た。
「頼むから妙なことを吹き込まないでくれよ? 彼は、何でも覚えてしまうから」
「信用ゼロ過ぎないか?」
「信用というか……単に予測が立たなくなると困るんだ。管理できなくなる」
「管理、ねえ」他人を管理しようというのがまずおかしいような気もするが。普通、そんなもの、管理できなくて当たり前ではないだろうか。
「保証はしかねる」
「まあ、できるだけでいい」
というか、本人の前でこんな話をしていていいのだろうか。そう思って少年の方を見てみるが、当の『九番』は、何もわかっていないと言った顔で男と仮面を見ているだけである。そわそわと落ち着きなく視線を彷徨わせながら手にした本を弄る少年、その表情にあるのは、『早く終わってどっちかが遊んでくれないかなあ』と言ったようなものだ――ある意味大変わかりやすい。
「とにかく、仲良くしてくれよ」
どっちがなくなっても、俺は悲しいからね。男はそう言って、部屋を出て行った。そうして、少年と二人きりになって、仮面は身を震わせる。
――やばい。
(か、解放感……!! 同じ部屋にあいつがいないだけで、こんなにも空気が軽い!!)
感動。今すぐ叫んで、飛び回りたい気分であった。まだ男が近くにいるだろうから、やらないけれど。苦節二週間、ついにあの男から解放された。記憶を失って道端に転がっていたことを生まれ変わったと称すなら、仮面は確かに、生まれてから背負っていた重荷を、ようやく下ろすことができたのだった。
「……で」
「なに?」
「その手に持ってる本はなんだ?」
「ずかん。オレ、これ、読めないから」
「じゃあ読まなきゃいいじゃねえか」
「読みたいの。読んで……えっと、読んで、ください?」
「なんで疑問形なんだ……」
つうか、頭の中はともかく、図体はきっちり成長してデカくなった男が首を傾げたって別に可愛かねえんだよな。身長何フィートあんだ、こいつ。六くらいあるだろ。ああでも、友達にならねえといけねえんだっけ。仮面は、早々に面倒くさくなっていた。けれど、一度そういう約束をしたのならば、守らねばなるまい。相手があの男以外なら無視するという選択肢もあったが、ここでそんなことをやったら今度こそ確実に殺される。その自信がある。火炙りは嫌だ。
しかし、友達――友達か。
不思議な響きだ、と仮面は思った。
「……仕方ねえな。読んでやるから、ページ開けよ」
そんなものが――かつての俺にもいたのだろうか。
満面の笑みを浮かべて図鑑を開いた少年の、腹のあたりに収まりながら、仮面はなんとなくそんなことを思ったのだった。
(→続く)