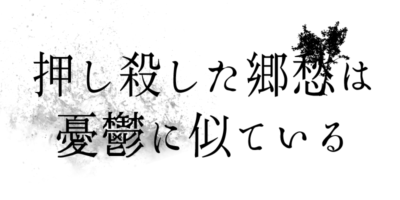小説リハビリの多分三月上旬くらいの話4。青薔薇の話が少し出て来ます。
※何に注意してもらえばいいのか最早ほんとにわからないので何か問題があれば教えてください……。
『――美潮』
漫画で読んだコックピットみたいに作り上げた自分の『お城』――その椅子で膝を抱えたまま、その『何か』は通信に返事をした。
「……はぁい」
『お前、木戸のところで何かしでかしただろう』
「……うん……」
『返事は“はい”だろうが。いつまで小学生気分なんだ? お前は本当に、いつまでも安定しないな』
知らないよ。知らない。わたしは何にも知らないもん。違う、『知っているから』、今こうしてわたしがんばってるんだよ? 口に出して叫んで喚き散らしてやろうかと思ったけれど、我慢をする。
いけなかったんだよ。
奇跡なんか起こしちゃいけなかったんだよ。
世界なんて救っちゃいけなかったんだ。
かわいそうなひとを救っちゃいけなかったんだよ。
『美潮』
薄青く光る画面に――かっこよさ重視で視認性を度外視したから、ビデオに映るその人の顔は、ぼやけてよく見えない。向こうには見えてるんだろうけど。この薄暗い『砦』の中で睨む、このわたしの姿が。
『お前が救われたのは、あのゲームの応用実験の結果に過ぎないことを忘れるな』
「はい」
この人はわたしを救ったつもりなんだって知ってる。わたしだって、最初はそう思った。この人たちはわたしを救ってくれたんだって。
でもそうじゃなかった。
ただ、奇跡を模倣してみたかっただけなんだ。
だって、だって、だってさぁ――
『“執念”』
画面に合わせて、スピーカーから声がする。
『たかがそんなもので一般人が“邪神を利用して”自分の目的を達成できるはずがない』
ならばどこかに理論があり、それさえわかれば、我々が邪神を完全に支配して利用することも可能なはずだ。画面の中の人――わたしを今の『何か』にした、柳亘弘支部長が、怨嗟のこもった声で、唸るように言う。
『そのために、お前を生かしているんだ』
「……わかってますよぅ」
――だって、どんなひとだって、奇跡が欲しいんだもん。
青い薔薇が欲しいんだ。
それがもう、咲いていなかったとしたって、本物が現れたら、我慢できなくなるよ。
ただ一輪の青い薔薇を咲かせるために……人間ってずっと研究を続けられるんだよ。続けてきたんだよ。そういう生き物なんだよ。
『わかっているだと? いいや、わかってなどいない。“世界を救う”ために、一体どれだけの犠牲を払わなければならないか、あの邪神どもを利用できれば、それがどれほど世界のためになるか!』
うるさいなあ、と『何か』は思った。昔私に『神託』を求めて来た信者さんも時々こんな風に興奮していたけど、この世界にそこまで興奮する必然性なんてあるかなあ。そんなんだから、なぎちゃんもあなたを捨てて教団と心中したんだよ。『何か』は段々面倒くさくなってきて、それでも通信を勝手に切ることなんてできなくて、ただぼーっとぼやけた画面を見ていた。そう言えばこの人、猟兵にはいい顔するんだよね。あと適当な理屈こねるし。らお君、騙されてないといいけど。でもよく考えたら、らお君他人の顔覚えられないから、二度目に出会っても得意のご機嫌取りはできないだろうな。ざまみろ。誰?って顔されてしまえ。
『しかもお前は、あの村で“本体”を奪っていったな? そんなことをしてどうする? 折角私たちがあそこで“守ってやって”いたというのに』
「ごめんなさい」
『違う、謝罪じゃない。私は、理由を訊いているんだ』
「……」
言ってどうする。言ったら、言ったら――『もうわたしは救われない』。それがわかる、わかりきってる。この人たちの思考回路を、わたしがどれだけシミュレートしてきたと思ってるんだ。この場所で、あるいは自分の電脳の中で、何千パターンも試してみた、誰にも迷惑をかけず、誰も死なせず、わたしひとりが、ただささやかに、『救われる』方法。
でもそんなもの、どこにもなかった。
「……傍に」
『傍?』
「あれを……傍に置いておきたくて……」
嘘。壊してしまいたくて。
『そんな感情で行動したのか?』
「ええ。いけませんか」
『……』
柳はしばらく黙っていた。こいつは役に立たないと思ったら娘だろうと使い潰す男ではあるけれど、馬鹿ではないし、『感情で動く』というのを嫌うから、納得ができないのだろう。
だが、この男は今、あの事件に囚われている。
あのゲームに。
真夏の、あの蠅のたかった部屋に。
人の執念が、何かを成し遂げたという事実に――囚われている。
魂という、目には見えない不確かな臓腑の、『確からしさ』に、こいつこそが今、まさに、『執着』しているのだ。
何かを強く『否定』したいと願うことは、それに強く『執着』することに他ならないのだとこいつは理解していない――だから。だからこの男は、この、『UDCオブジェクトに紐づいた美潮香純という女の魂を利用して、邪神と接続としている』男は――この時点では絶対に、『美潮香純の感情』を、無下に出来ない。
そのはずだと、『わたし』は踏んでいた。
三分と二十三秒悩んで、柳は、刺々しく、『お前が』と口を開いた。
『お前がUDC怪物を殺すために行動しているのであれば何をしても許す。庇ってもやる。だが、“そうでない”のなら――』
木戸の件も。
お前の本体の件も。
例のゲームと勝手に接触していた件も。
『みちるの件も――許しはしない』
……驚きを隠すのに、些か苦労した。
通信はそれで終わった。女の容をした『何か』は、アハハ、と笑った。なんだ――なんだ、なんだなんだ、アハハハハハ、娘が死んだの、ちょっと後悔してるじゃないですか。柳支部長も人間なんですねぇ、一人娘が死んだの、ちょっとだけ悲しいんじゃないですか。
「アハハ、アハハハ、ああ、ばーかばかしーい!」
アーハハハハハ、と『何か』は笑った。それなら大事にしてあげたらよかったのに。それなら教団なんかに潜入任務させなきゃよかったのに。それなら洗脳プロセスに対する訓練をもっともっと積ませておいてあげたらよかったのに。まあ、なぎちゃんは洗脳されてたわけじゃないですけど。というかぁ、わたしが『黙って見てた』だけなの知ってたんだ、知っててらお君に『彼女を助けてくれてありがとう』なんて言ったんだ、アハハハハハハハ! 足をじたばたさせて、『何か』は笑った。それからぴたりと止まって、椅子の上で体を弛緩させて天を仰いだ。
「……ほんと、馬鹿馬鹿しい」
奇跡なんて、意図して起こせないから奇跡なんですよ。
「大体ですよ、他人を馬鹿にしてますよ、ね、そうですよね」
『何か』は後ろを振り向いて、ピンクを基調にデコレーションしたケースを手に取った。中に入っているのは、オフラインのスマホである。
「ねー、『主人公』ちゃん」
『……彼女から複製された私は、その本質を既に持っていないわ』
画面には、黒髪に黒い服の、可愛い女の子の絵と――それから、縦向きに調整されたメッセージウインドウがあった。
『だってここには“物語”がないもの。それに、“物語”はもう終わったのよ』
「わかってますよ。でも、だからって、デフォルトネーム?っていうので呼ぶのも違うじゃないですか? だってちゃんと名前があるんでしょ」
『それはどれも“私”の名前じゃないわ。“私”はもう役目のないモノよ。彼女でさえね。それに“私”はあなたによって複製され、端末に合わせた最適化という改造を加えられた“何か”でしかないもの。それとも“私”を作り出したあなたが“私”に本質を与えてくれるのかしら?』
「んー……」
『何か』は、スマホ画面の『何か』を前にして首を捻った。
「そういうの、好きじゃないんですよね」
『そうなの?』
「中身が空っぽでも、器は器じゃないですか」
『器は器であることが本質だもの。器であることで器は器たるのよ』
「あ~……ちょっと上手く言えませんでしたね。すみません。そうじゃなくてですねぇ、ええと……どう言ったらいいのかなぁ……わたし、『何かのために存在するもの』って好きじゃないんですよねえ」
『自分がそうだったから?』
「……痛いところを突きますねぇ、本体の方はちゃんと躊躇ってくれたのに」
『ねえ、“私”に魂があると思う?』
「いきなりですねぇ!」
『どうでもいいから答えてみて?』
「……ないんでしょうねぇ?」
『複製されたから?』
「……むしろ、あなたはあると思ってるんですか? 自分に?」
『さあ?』
「煙に巻こうとしますねえ……性格悪くないですか? わたし複製しただけですよ?」
『“主人公”でない私なんてこんなものよ。元々性格が悪い人間の魂を分割してるんだもの』
「性格悪かったんですか?」
『悪くなかったら、あんな質問をして手当たり次第に石膏像にするなんてことしないと思うわよ』
「そうですかねぇ……」
殺していないだけ優しいと思うけれど。甘いとも言う。世界を憎み切れなかったんだろうと思う――一番憎んでいたのは自分自身だったのだろうし。
「世界は優しいんでしょうか?」
『世界は世界よ。そこにあるだけ。優しくも厳しくもないわ』
「世界に希望はありますか?」
『それも同じ答えね。結局受け取る側の問題なのよ』
「……わたしは、わたしでしょうか」
『さあ。眠って起きた自分の連続性を信じている限り、あるいは目を閉じて開いた世界の連続性を信じていられる限り、あなたはあなたなのかも。そもそも“あなた”って何かしら?』
「……なんでしょうね。菌類……ですかね」
『菌類?』
「本体の方は菌類なんですよ。というか茸ですね。わたしに寄生したあの虫たちはですね、自分の餌になるよう、私の体を菌類に作り替え続けていたんですよね」
だから途中で、体がボロボロ崩れて掃除が面倒というので、分割されてあのガラスケースに収められたのだ。
「でも意識はあったんですよね……それともあれはわたしの意識じゃなくて虫の意識だったのかなぁ? 今のこのわたしでさえも? どう思います?」
『わからないわ。私はあなたじゃないもの』
「とりあえず粉砕してはみましたが、あれがあの土の下から茸としてにょきにょき生えてきたら困りますねえ……」
まあ虫も八つ裂きにしたので大丈夫だとは思いますがぁ、と『何か』は言った。
「何にせよ、起きた奇跡を模倣しようなんて、烏滸がましくないですかぁ? あれは、あの場にいた人たちがぁ、本気で立ち向かった結果じゃないですか。大体、あれって『邪神を利用』してたわけじゃないでしょう? それを結果だけ見て、過程を見ずに横取りしてみようなんて、研究者の風上にも置けなくないですか? 同じ研究者として恥ずかしいですよ!」
『あなた研究者なの?』
「違いますね。何も研究はしてません。楽しいことしてるだけです」
『そう……あなた、結構適当なのね……』
「んん……というかですね……」
わたしもうだめなんですよね、と『何か』は言った。スマホの女の子は、いつの間にやら呆れ顔を見せている。
「『わたし』は、世界を憎んでます」
『そう』
「すごくすごーく、憎んでるんです」
『それで?』
「だから……世界を滅ぼしてしまいたくて仕方ないんです」
『……そう』
「今どんな神様と繋げられようとしているのかもわからないんですけど、世界を滅ぼして、更地にして、全部全部ぶち壊してしまいたくって――ずっと堪らないんです」
大嫌いだった。
大嫌いだった。
嫌いで嫌いで嫌いで嫌いで、痛くて痛くて痛くて痛くて。
お父さんもお母さんも役に立たなくて、先生はわたしを庇ってもくれなくて、同級生はわたしに石を投げた。給食だって配膳してもらえなかった。ランドセルに落書きされた。何回も背負えなかったけど、それでも嬉しかった、わたしの赤いランドセルに。それでお母さんに言ったけど、『でも香純は、もうすぐ神様と一緒に働く偉い人になるんだから。ランドセルくらい、いいじゃない』って言われて。頑張って拭いたけど消えなくて、服もぼろぼろで、汚いやつって言われてた。
「バリア!とか、ふふ、小学生ですから、言われちゃったりして。今なら本当にバリア出せちゃうんですけどね、わたし。すごいって言われちゃうかも。でも昔はね、美潮に触ったら最悪だって言われてね……上履き池に捨てられたりして……」
『よくある話だわ』
「そう、よくある話なんですよ。だから、こんなのが『よくある話』になっちゃう世界、要らないんじゃないかなって、ずっと、誰かが、わたしを誘導しようとするんですよ」
『そうなのね』
「でもね」
スマホを握り締める。女の子は、真剣な顔をしてくれている。これは一人芝居に過ぎないんだろうか? それでもいいよ。
「そんなわたしに光を見せてくれたのは、あなたを救ってくれた人たちなんですよ」
だから世界を滅ぼしたくない。
滅ぼしたくなんかない。
せめてあのひとたちが存在している間は。
「確かに、わたしを『こう』したのは、あのバカ支部長ですよ、でも、その切欠になってくれたのは、わたしを『こう』してくれたのは、あなたを救ってくれたひとたちだった」
あのひとたちがいる限り、わたしは、世界を、守っていたい。
「それを知った日から、あのひとたちのファンなんです。らお君が案内した、あのひとたちの事件は全部調べました、報告だけじゃなくて、当時の監視カメラの映像とか、できるだけかき集めて、それで、ほんとに、好きで……あのひとたちが好きなんです、あのひとたちが……あのひとたちだけが、今、この世界で唯一、大切なんですよ……」
どうしてうまくいかないんだろう。
どうしてわたしには、こんな手段しかないんだろう。
奇跡なんて起こして欲しくなかった。奇跡なんて要らなかった。それがなかったら、わたしは今ここにいなくて、もしいたとしても、こんな苦しまずに、世界を滅ぼそうって簡単に決められた。
でも奇跡は起きてしまった。
そしてわたしが今実行しつつあるこれは、決して奇跡じゃない。
奇跡なんかじゃない。ただの手段だ、私が『救われる』ための。
あるいは『世界を滅ぼす』ための。
「だからわたしはまず、あなたが救われる事件を予知してくれた人……じゃないか、うん、そう、あの仮面さんと、肉体さんとね……接触してみたんです。そしたら、思ったより『ひとつ』として機能してて、面白くって……すごくないですか、ぎーさんの事件とか、すごいなって思って、あんな状態でも、あの肉体さんは、あの仮面さんが好きなんですよ、すごい、ひとって、すごいですよね、わたしほんとに、面白くて。ああ、わたしも友達にして欲しいなぁって思っちゃったんですよね。だから、今、友達になってもらおうとしてるところなんですよ」
『ふうん……ところで、あなたの言う友達って、一体何なのかしら?』
女の子の質問に、美潮香純と呼ばれる『何か』は、へらりと笑った。
「わたしの生きた二十数年間で、友達と呼べたのは、ただ一つですよ、『主人公』ちゃん」
わたしは世界を憎んでいる。
それはきっと永遠に変わらない。
だから目の前で何が起こっていたって無視できる。何もせずにいられる。だって嫌いなものが勝手にドミノ倒しで壊れてくだけなんだもん。知らないよ、わたし嫌いなもののために頑張れるほど大人じゃないもん。
アハハ、と、『何か』は、スマホを握り締めたまま、また笑った。
「あのひとたちがいなかったら、わたしは世界を滅ぼせるのに」
救ってください。
お願いします。
「そんなわたしでも――救われたいって渇望は、一人前なんだから反吐が出ますよね」
ねえ、らお君。
世界のためになんて言いません。
ただわたしのために。
わたしのためだけに。
わたしの
(→続く)