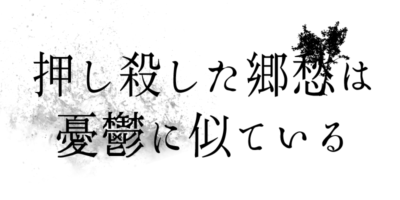小説リハビリに書いていた過去話1。肉体の方は何を思ってそれを選んだかの話。
※最早何に気を付けていただくべきかわからないので色々気を付けてください。
『オレ』の『もの』なんて、何一つなかった。
「本当に……すまない。俺には、君を……元に戻すことが、できないんだ」
オレが『生まれた』のが、いつだったのか。オレには日付の感覚がほとんどなくなってしまっているから、わからないけれど。
「だから、君は、もう、君のままでいい。ずっと……そのままで……」
知らない誰かが、すべてを手放して、目を閉じて――目を開いた時、オレはもう、『オレ』になっていた。『しょちょう』が、泣きそうな顔で「大丈夫だよ」と言って頬を撫でたのは、きっとじぶんに言い聞かせていたのだと思う。何度も何度も「大丈夫だよ、元に戻せるはずなんだ」とオレの頭を撫でた男は、結局、貼り付けた笑顔で、泣きそうな瞳で、それだけ、オレに告げた。
「その代わり、いつか、近いうちに俺は君を殺すだろう。それを許して欲しい」
「……うん」
うん、うん、と、オレはただ、男の言うことに頷いた。
目の前の男を――オレは多分、知っていた。そういう男だということも。オレが『こう』なった以上、その選択をするだろうとわかっていた。だって、この人は、オレの知ってる、『しょちょう』なんだから。難しいことを全然考えられなくなってしまったオレの頭の中で、そんな言葉が泳ぐように浮かんでいた。だから、男の判断を、拒否することはなかった。
ただ、頷くオレの胸で、じわりと滲んだ『いとしさ』と『さびしさ』は、『おとうさん』を前にした時に似ていたんじゃないかと、何となく思った。でも、多分、違うのだ。この男は『おとうさん』ではないのだろう。何もわからないけれど、それは確かだった。男はきっと、オレのおとうさんじゃなかった。でも、もしかしたら、それ以上に大切だったかもしれないひとだった。何も思い出せなくても、それでも。
だから、オレの『それ』は……ぜんぜん、消えてはくれなかった。
そして同時に、オレにはわかってしまっていた。
『これ』は、『今のオレ』の、きもちじゃない。
オレじゃないオレのきもちだけが――ずっとのこってる。それがわかっていた。知らない人だって言うのに、今のオレを見る、男の泣きそうな瞳が苦しくて息が詰まった。どうしてあんたがそんな顔をしてしまうんだ、オレは、あんたと一緒にやれて、この七年間ずっと、楽しかったよ、だからどうか、かなしまないで……オレとあんたで過ごした日々の、この結末を、笑って受け容れてくれよ……オレも、地獄の底で、笑って待ってるからさ……。
オレのきもちじゃないきもちが、オレを、苦しめた。
男のことも。
それが……たまらなく、嫌だった。癇癪を起こして泣いてしまえば、男は益々悲しげな眼をしてオレから遠ざかった。苦しそうにオレに背を向けた。それが嫌で嫌で、オレは泣くのをやめた。笑うことにした。えへへ、と、出来る限り、楽しそうに、笑っていようとした。男も笑っていたし、オレも笑っていたけれど、何も楽しくなんてなかった。ただ、かなしいきもちだけが、オレの中に広がるだけだった。
オレのかなしみ。オレのくるしみ。
知らない文字で書かれたノートやレポート。知らない文字で書かれた本。
白いシーツ。白い天井。白い服。
浅黒くて長い手足。赤茶色の瞳。オレンジ色の短い髪。
あい。
こころ。
からっぽになった……あたまのなか。
それから――いなくなってしまった『オレ』を、まだ、愛しているらしい『しょちょう』。
オレのものなんて一つもないのに、それは全部、確かにオレのものだった。
かなしいかおを、してほしくないのに。
かなしいかおなんて、したくないのに。
夜は嫌いだった。誰もいない部屋は、不安をかきたてた。シーツにくるまって、一人で声を潜めて泣いた。
部屋にあった本は、一冊も読めなかった。だから、男は、オレのために、色んな絵本や図鑑をくれた。それでも読めなかったけど、絵や写真が綺麗で楽しかった。沢山の棘がついたトカゲや、鋭い歯のワニ、それからサメも好きだけど、シャチの方がもっと好きだ。白と黒でかっこいいから。ユーベルコードを使えば恐竜を生み出せるひともいるのかな、とオレは少しだけ、わくわくした。オレは恐竜なんて出せないけど。
でもやっぱり――これも、オレのものじゃなかった。
こどもみたいなことしか言えないオレを見て、しょちょうが用意してくれたものだけど。これは、なんだか……『オレのためのもの』じゃなかった。オレのために用意されたはずなのに。どうしてだろう? 絵本の文字さえ、オレには難しかったからだろうか。
あのひとは――オレがどれくらい読めるかも確認せずに、これを用意したのだと。
わかってしまったからだろうか。
オレが喋ることのできる単語や使える文法から、このくらいなら読めると思ったのだろうことは推測出来た。でも、オレは、喋ったり聞いたりする能力よりも、読み書きの能力の方がずっとずっと落ちていたから……この程度でも、本当に難しかったのだ。絵本だって図鑑だって、名前くらいしかわからなかった。どんな言語でも、まともに読めなくなっていた。
――死ねたらよかったのにな。
絵本や図鑑を開いたまま、ベッドに横たわって、そんなことを考えることもあった。あの日、ちゃんと死ねていたら、オレじゃないオレが、ちゃんと死んでいたら――誰もかなしいおもいをせずにすんだはずだったのにな。
オレもしょちょうも、わるいやつだったから、だれもしあわせになれないのかな。
ぼんやりそんなことも考えた。男がわるいやつなのはわかっていた。いいやつは、オレに「いつか殺してしまうことを許して欲しい」なんて言わない。そう判断する程度の頭は流石に残っていた。
でもそんなしょちょうが、多分オレはすきだった。
元のオレも。
少しずつ、オレのものじゃないものが、オレになっていった。
元のオレの字を真似して書いてみたこともある。でも書けなかった。無理だった。鉛筆を握ってお手本通りに書いているはずなのに、上手く文字を認識することすらできなかった。それが文字だとわかっているのに。図形を描くつもりでやってみたらどうかと試してもみたけれど、どうしても、どう頑張っても、『オレ』には戻れなかった。
なんでもないみたいな笑い方ばかりが、上手くなっていった。
それからどれだけ経ったのか、やっぱりオレにはわからない。相変わらず貼り付けた笑顔のしょちょうが、黒くて白い――オレはなんとなく、シャチを思い出した――仮面を持ってきた。なんだろ、と思った。でもしょちょうが変なものを持っているのはいつものことだと知っていたから、オレはいつもみたいに、絵本がどれだけ読めたかとか、図鑑がいつもよりちょっとだけ読めたこととかを報告した。そしたらしょちょうの顔が、珍しく強張って――いきなりどこかから、「おいおいおい所長さん、表情筋が死んでんじゃねえか。いつもの調子はどこ行ったんだ? 子供は苦手ですかぁ?」と揶揄うような声がしたので、ぎょっとすると同時に、しょちょうの手が、一瞬の間に仮面を壁へと叩きつけた。それに合わせて「ぎゃう!」と鳴き声がしたので、喋っていたのは仮面なのだと知った。カァン!とやたらにいい音が響いていた。目を丸く見開いて、その光景を――『仮面が喋っている事実を違和感なく受け容れている自分』を――不思議に思いながら、何度も瞬きをする。そんなオレに、しょちょうは、仮面をおそらく凄まじい力で壁に押さえつけながら、きっと、オレが今のオレになってから初めて見せる、優しい笑顔で、オレに言った。
「すまない、今すぐこの仮面を薪にしてくるからちょっとだけ待っていてくれないか」
「ぐおおおあああああ悪かった悪かった悪かった、茶化したのは謝るから縦に割るのは勘弁してくれマジで頼む鋸の音がまだ聞こえるんだよほんといや冗談じゃねえんだあっでも横もやめて欲しいがっていうか痛い痛いいてえんだよ押さえつけるなああああああ」
「痛いようにしているから君が痛がっているなら問題ないな。そうだ、縦に割るのが嫌なんだろう? じゃあこのまま握り潰せるか試しても構わないか? 木っ端微塵になっても薪にはできるしな」
「ぎゃああああああ!!」
こんな――しょちょうは、見たことがなかった。
「……えへへ」
自然に笑みがこぼれて、オレは声を上げた。オレの前なのに少しも我慢をしていないこの男を見るのが、楽しかった。
「おもしろいね」
このひとがこんな風に遊んでいるところを、オレは知らなかった。元のオレだって、知らないはずの姿だった。知っていたら、少しくらいは、オレもそんな部分を知っていただろうから。
そう――このひとは、今、遊んでいる。
たぶん、それはこの仮面以外の誰も、できなかったことだったのではないか。
オレはそう思ったし、それが、オレには、とても面白かった。
「……そう?」
ほっとしたような、でもどこか心配そうな顔で、しょちょうは仮面から手を離した。仮面は「い、いつか、やりか……や、やりかえ……できるわけねえんだよなクソ……」と細い声で毒づきながら、ふらふらと壁から逃れた。
「そう、そうか……」
しょちょうは何か考え込んだような仕草で数度瞬きをした。それから、
「少しお昼ご飯を食べてくるからね、そうしたら、これについてのお話をしよう」
と飛ぶ仮面をまた掴んで去って行った。廊下からまた、あー!だの、掴まれなくても自分で移動出来るんですよ俺が飛べるのご存知でない!?だのといった言葉の直後に再度、仮面の悲鳴が響いて消えた。あの仮面も、わざとやってるんじゃないかな。あんなふうに言えば、しょちょうが遊んでくれる――しょちょうが遊ぶことができるって知ってるんじゃないか。
楽しそうだし、お昼ご飯、一緒に食べたいな。そう思ったけれど、オレは食堂ではご飯を食べないように言われていたし、だいいち、さっき部屋で既に食べた後だった。デザートのオレンジゼリーがもう一つ欲しいなと思いながらも言えず、しょちょうにトレイを返したところである。
そうして一人残されたオレは、何もやることがないまま、手持ち無沙汰に、ベッドの絵本を開いた。絵しかわからない紙の束は、あまり深い感慨をオレに齎してはくれなかった。絵だけでも話はなんとなくわかる、それは確かだ。けど、オレは『ちゃんと』知りたかった。自分の見ているものがどんなものか、世界の何を記しているのか、世界がどんな風に作られているのか。
それを教えてくれたのは、しょちょうだった。
いっそ、誰かに読んでもらえばいいのかもしれない。でも、しょちょうは忙しい。他の人はよく知らない。元のオレは、というかここの人は殆ど、お互いにあまり興味がなかったしともだちになろうともしていなかったから。オレたちはみんな、ただ仕事をするためにここにいただけで、お互い助け合ってとか、そういう関係はだれも求めてなかった。だからオレは他にどんなやつがいるかも知らない。それに、しょちょうが思っている以上にオレの状態がひどいなんて、教えたくなかった。
……あの仮面が、しょちょうのともだちになってくれたらいいのにな。
そしたら、オレを殺した後も、今ほど悲しまずに済むかもしれない。
しょちょうは、まわりが思うほど、『常軌を逸していない』。それはなんとなく、今のオレだってわかっていた。じゃなかったら、オレが『元のオレ』になれないことを、悲しんだりしないはずだ。オレを死なせてしまうことを、苦しいと思ったりしないはずだ。『元のオレ』が――もう記憶もない、おとうさんとかの家族より大事だと感じることもなかっただろう。
だけど、しょちょうのまわりは、しょちょうを『ふつう』として扱わない。そりゃあ、もちろん、オレだって、あのひとがふつうだと思っているわけじゃないけど。
でも、あのひとは、心がないわけじゃない。
今も、大事なものをなくして悲しんでる。
その席に、オレが座ってるのを、苦しいと思ってる。
あのひとのさびしさを……あの仮面は埋められるだろうか?
きっとオレが空けてしまったのだろう、あのひとの胸の穴を。
(がんばりもせず、だれかにたよるのはよくないことだ)
そう思っても――願わずにはいられない。
オレのものじゃなかったはずのきもちはもう殆どが全部オレのもので、からっぽになっていたオレの中を勝手に満たしていた。オレのすべては今やオレのものではなかったけれど、オレのものでもあり、だからオレは、しょちょうのしあわせを祈っていた。
だから――目を閉じて、開く扉と同時に目を開いて、迎えたしょちょうが、オレに仮面をあげると言って、オレはひどく驚いた。てっきり、これは、しょちょうのおもちゃなのだと思っていたから。
「そういうわけで、同じ部屋になった――あー、仮面だ。名前はないから、仮面でいいぞ」
シャチみたいだと思った白黒の仮面は、よく見たら別にシャチとは似ていなかった。木目が見えているので、どちらかというとちょっと茶色い。それに、名前がないなんて。番号でもなんでも、しょちょうならつけそうなものだけど。ただよく考えたら、空飛ぶ仮面なんてこの仮面しかないから、仮面というだけでも一意の記号になり得るのかもしれない。
「なんか、あれだ、仲良くやろうぜ」
じっと仮面を見て、首を傾げ、瞬きをする。それから、出て行こうとしていたしょちょうに向かって、「しょちょう」と声をかけた。振り向いた男は、いつもの貼り付けた笑顔のままだった。それが少し嫌だったので、仮面がいつでも、あの時みたいにしょちょうと遊んでくれたらいいのにな、なんてオレは思った。
「これ、もらっていいの?」
「いいよ。好きにしなさい」
まあ――それはそれとして、おもちゃがもらえるのはやっぱりうれしい。それにこの仮面なら、文字が読めるかも。そしたら絵本や図鑑を読んでもらえる。それを考えると、勝手に口が、えへへぇ、なんて笑みを浮かべてしまった。
(続く)