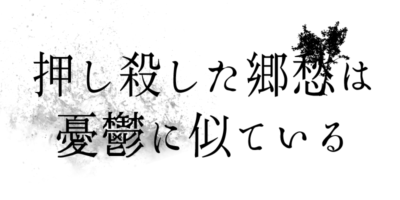過去話よっつめ 犬が死んだ時の話、あるいはご飯を食べる話
アンチ・アンチ・ヒーロー(ノット・ヒーロー)4
その青年を見て最初に思ったことはと言えば、「なんか、事前に聞いてたのと随分違うな」であった。男が説明するに、その青年は十九歳で、十二歳から傭兵稼業をやっていて、ユーベルコードをいくつも使えて、銃火器の扱いもそれなりで、まあそうして七年間誰かと殺し合ってきたのに四肢の一つも欠けることなく生きてこられた――『運のいい』奴だということだったのだが、実際に仮面が目にした青年はと言えば、なんというかこう――本当に『子供』と称するのが似つかわしいようなものであった。青年は男を「しょちょう」と呼んで、子犬のように絵本がどうの、図鑑がどうのと纏わりついた。十九歳がこんな言動をするか?と仮面は思ったものだった。そして何故か、その時ばかりは、男の笑顔がどこか張り付いたようなものに変わったので、思わず茶化して真正面から壁に叩きつけられた。白くて綺麗な壁とキスして「ぎゃう!」とあんまりにも情けない悲鳴を上げた仮面を、青年が「面白い」と言っていたく気に入ってくれたのは、不幸中の幸いと呼ぶべきだろう。ここで気に入られていなければ最終的に暖炉の薪へとジョブチェンジしそうだったから。
男は彼を、ただ『九番』とだけ言った。
「幼児退行?」
「そう」
青年の部屋を後にして、食堂で遅めのランチを取る男の横で、仮面は「ふーん」と返事をする。正直に言えばよくわかっていなかった。言葉としては理解できるが、それがどういう影響をあの青年に与えているのかよくわからないのだ。男は柔らかそうなパンを千切りながら、「君を拾った日にね。丁度壊れてしまって」とその睫毛を伏せた。
「長く一緒にいたし、気に入っていたから……処分するのも忍びなくて。収容するだけして、ずっと判断を保留にしていたんだよ」
食堂には、男の他誰もいない。ランチタイムは過ぎているし、そもそもこの寮――仮面はどう見ても病棟か監獄だと思ったが、男は寮だと言い張った――に、住人は今殆どいない。皆仕事で出払っているのだという。職員たちも住んではいるらしいが、それもやはり、もう食堂に用はないらしく、一人も顔を出しては来なかった。
「お前、忍びないとかいう感情があるんだな……」
「君は俺を一体何だと思ってるんだ。さっきもそうだが、辛い時は辛いよ。ペットが死んで泣いたことだってある。俺だって、こう見えて人間なんだから」
「人間ねぇ……」
仮面がかつていたところに、『人類』はいなかったので、何とも言えない。仮面にとっての人間とは現時点ではこの男とあの青年しかおらず、比較して意見を言うことができないのである。彼らが『人間』スタンダードでないことだけはなんとなくわかる。何か、自分たちと彼らで変わることはあるのだろうか。
「……仮面に言ってもわからないか」
「この場合はそうなのかもな?」
「素直だな……まあいい、それで、友達になれそうかい」
「一目見ただけでそれがわかるなら、俺たちは言葉なんか使ってないだろうなあ」
「……それもそうか」
ため息交じりに、男がポテトサラダを口に運ぶ。そうしてあんまり『美味そうに』咀嚼するので、「もっと美味そうに食えねえのかよ」と仮面は文句を言った。
「うん? 何か、おかしなところがあったかな」
「頭の先から足の先まで変だよ。完璧過ぎるっつーのか。CMに出てくるモデルの方がまだ『抜けた』演技するぞ」
「……ははあ。君は、案外鋭いね」
自分のことには鈍いのにね、と男が笑う。どういうことなのかは、やっぱりよくわからない。とは言え、わからなくても問題はないのだろうと仮面は無視する。
「何言ってるのかさっぱりわからねえが、とりあえずやるならもっとちゃんとやれよ。俺みたいなのにこうやって言われるの、イヤだろ」
「ふむ。『演技するな』ではないんだな」
「なんで俺が他人のことそこまで口出ししないといけないんだ。めんどくさい」
大体、『必要だと思って』やっているだろうことを、なぜわざわざ『やめろ』と言わねばならないのか。必要がなければ勝手にやめるだろう、知能があるなら。必要だと本人が思っている以上、第三者 である自分が止める理由などどこにもない。
それに、と仮面は思った。
深入りするのは――面倒だ。
ただ馬鹿騒ぎをしたいだけの時に、他人の情報なんて、邪魔になるだけだ。考えるのも苦手だし、相手に配慮するのも億劫だ。だから仮面は他人に深入りをしない。男の名前も未だに知らないし、それで構わないと思っている。番号で呼ばれた青年の本名にも興味はない。もっと言えば、『自分の名前すら、ついていなくたって構わない』。
記憶を失って二週間、男から、適当に名前でもつけるかと言われなかったわけではない。ただ自分が辞退してきただけだ。挙げられた名前はどれも自分のものではない気がしたし、何より、『自分が知らない自分に為る』のはなんとなく嫌だった。自分が、知らない自分に為る。あるいは、自分が知らない、自分に為る。どちらも嫌だった。自分は自分だった。だから仮面は未だ、仮面とだけ呼ばれている。それは自分だったからだ。誰が見ても、自分が見ても、自分は仮面だった。空飛ぶ仮面。だから仮面は仮面なのだ。
「思うんだが、君は結構、思慮深いよね」
「馬鹿らしいなぁ。頭煮えてんのか」
ノータイムでアイアンクロウ、からの、叩きつけ。机に強打された己から、カァン!と良い音がして、仮面は呻いた。こいつ、叩きつければ俺が必ず黙ると学習してきやがったな。絶対あのガキに教えるなよそれ。音に何事かと顔を出したコック――正式名称を仮面は知らない――に、男が笑顔で「ちょっとぶつけてしまって。すみません」と返事をする。
「俺がこれ以上馬鹿になったらどうすんだ、畜生……」
「記憶の一切合切を失ってる時点で、もう失くすものはないだろう。安心したまえ」
常識なんてものに至っては最初からないのだからね。その言い草に余程言い返してやろうかと思ったが、ふっと諦めが勝ったのでやめた。良くない癖がついているとは気付いていたが、結局この男には勝てないのだから仕方がない。怒るのも無駄だと悟ってしまうのだ。そうなると、もう怒りなど持続しなかった。
それより、今の仮面には大事なことがある。
「あの九番とやらと友達になったら――」
「なったら?」
男は、メインのステーキを食べている。
「お前の鞄以外に部屋をくれ」
この男と四六時中一緒なのは、精神衛生上本当に良くないのだ。殆ど予備動作がないので何をするか常に気を張っていないと怖いし、気を張っていても突然痛い目に遭わされるのは回避できない。檻に入っていない猛獣と一緒にいるようなもので、逃れられるなら逃れたいと仮面は常々思っていた。
男の返答はあっさりしたものだった。
「いいよ」
「いいのか!?」
それはつまり、出来れば俺が起きるまでこいつが起きてこなければいいのになと思いながら夜を眠らなくて済むということだ。なお、仮面が目を覚ますまでに男が起きてこなかったことはこれまで一度もない。彼の目覚めはほぼ常に、男が取った何らかのアクションによって齎されてきた。ようやく解放される。涙が流せるのなら、仮面は滂沱していただろう。
「元々、彼と相部屋にする予定だったからね」
「彼、ってあの」
「そう、あの九番の彼だ。彼、世話が必要でね。あの状態では、食事も食堂ではさせられないから、部屋でさせなくてはいけなくて」
かと言って、誰かとずっと一緒にしておくわけにもいかなかったから。男がそう言って、フォークを置いた。
「友達になるついでに、彼と一緒に住んで、世話をしてくれると助かるよ」
任せろ――とは言い難かった。仮面は子供の世話などしたことがない。少なくとも記憶はない。いやまさか、自分がかつてベビーシッターをしていたとはまったく思えないだろう。性格的に。それくらいわかる。自分に向いていない職業ナンバーワンだと思う。何しろ、責任感がない。皆無である。ハッキリ言って、赤ん坊が喉に何か詰まらせて死んでも、自分は悲しくないと思うし、自分のせいじゃないと豪語してしまう自信がある。自分の過失で引き起こされたなら誠心誠意謝っては見せるが、一週間もすれば忘れるだろう。
「そ、それでも良ければ」
「いや、流石に赤ん坊ではないからね彼も……」
自分の世話自体は自分で出来るんだよ、一応。男が呆れたように言う。
「ただ、彼はね……ううん……何と言うのかな。寂しがりなんだ。いい子なんだよ、本当に。家族思いだし、一生懸命だし、明るくて素直だ。凄くいい子なんだ」
「なら問題ないんじゃ?」
「……俺は辛いよ」
辛いんだ。男が、グラスのミルクを一息に飲んだ。
「二十年くらい前にね。可愛がってた犬を亡くした時を思い出すんだよ。彼を見ていると」
二十年。ということは、男が子供の頃の話だろうか。
「よく俺に懐いてくれてね……本当に可愛かった。真っ黒なジャーマンシェパードでさ」
「なあ、その話長くなりそう?」
「……なるよ。なるから、やめておこうか」
ここでする話でもないしね、と男が笑う。口を挟んだので気分を害するかと思ったが、そうでもなかったらしい。男が、仮面を掴んで立ち上がる。別に、飛べるから掴まなくても良いのだが。仮面は何も言わなかった。
男の思い出話を止めるのを、悪いと思わなかったわけではない。けれど、止めるべきだとは思ったのだ――だって。
(……こんなところで泣くもんじゃねえよなぁ)
男が犬とどんな関係を築いていたのかは知らないが、その過去による感情の発露は、自分が見るべきものではない。仮面はそう思ったのだ。
ただ、それだけだった。
(→続く)