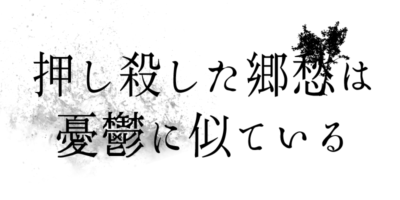いなくなる前のあの子の話
※戦場とか深く考えてないので適当です(というよりもまあ設定は多少考えていますが詳細を出したくないというのが正しい)
サブマシンガンを手に、乾いた村を駆ける。足音の消し方など、とっくの昔に覚えていた。透明になった体躯と、消えた気配で、誰も彼のことになど気付かない。
多分、もう、駄目なんだと思っていた。頭の中はめちゃくちゃで、命令を聞いて動くのが精一杯だった。それなのに体が動くのは、この七年の生活のおかげだったのだろう――あるいは、その『せい』なのか。どちらでもいい、と青年は思った。どちらにせよ、自分は、もう、駄目なのだ。
何か、彼を彼たらしめる『大切なもの』が、どんどん削れて、壊れていくのが、わかっていた。でも、仕方がないのだろうと思う。七年、七年だ。あの人の下で、七年も耐えられたのは、多分、自分だけだと思う。だからこそ、これが最後で、最期だった。この仕事が終わった時、自分は、『駄目になる』。
あの人のことを、好きだったか。
多分、そんなことはないと思う。いや、よくわからない。嫌いではなかった。所謂善人ではないと知っていたが、どうせ青年だって別に善人ではない。この七年で何人殺して、何人の人生を壊してきたか。それを『些末なこと』だと判断してしまえるくらい、多分、青年もまた、『人の容をした怪物』だった。だから、あの人のことを、その点において責めようだとか、軽蔑しようだとか、そんなことは少しも思っていない。給金の支払いはいいし、青年の家族は、彼のおかげで救われて、青年自身もまた、生まれ故郷では考えられないような食事をさせてもらえた上に、勉学まで修められた。今の青年は、アカデミーレベルではないけれど、ハイスクールを卒業できる程度には、学がある。無知と無学は罪だと青年は思っている――それで兄は足を失くした。故に、使うところがたとえ一生ないのだとしても、青年はそれを尊んでいるのだった。
よくわからないな、と青年はやはり思う。乾いた村を抜け、視力を高めて辺りを探す。標的はこの辺りだったと思うが。機械に頼らぬ目は、青年の装備を軽くし、敵からの索敵を逃れる術を与えてくれた。この目が、青年は、存外気に入っている。
そう――『気に入っている』のだ。
あの人との生活を、あるいは、この砂埃や、戦場の緊迫感を。改造され続けた己の体を。与えられた学を修めた頭を。爆発のしびれを。銃弾のうなりを。人智を超えた力を。
(オレは……思ったより、ずっと……気に入ってたんだな)
理性の一線が。知性の一片が。
人間の脳の限界を超えた力と知識と狂気の濁流に飲み込まれて、弾ける。
あなたの名前を、オレは多分、忘れるよ。
いや、覚えてるかもしれないけど、その名を呼ぶオレは、もう、オレじゃない。
別れも言わないオレを――許してくれよ、所長。
そして青年は、その日、壊れた。