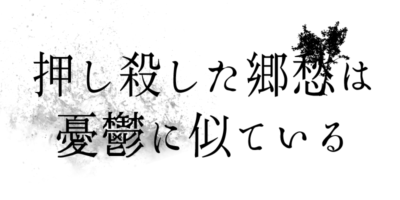小説リハビリの多分三月上旬くらいの話3。青薔薇の話が少し出て来ます。
※相変わらず九雀がひどい目にあわされています。食べ物を吐き戻す……吐き戻す?描写があります。
そういう経緯で、不本意なバスタイムが終了した九雀は、もう一度両手足に枷をつけ直された上で、明らかに香純よりもサイズの大きいバスローブにくるまれ、現在、多少広い部屋のベッドに寝かされていた。黒布は、部屋についてベッドに横たえられた時に外された。傍らには、風呂場から持ってきたと思しきドライヤーとブラシがある。
独房。
そんな言葉が頭を過ぎる部屋であった。否、独房へ実際に入ったことなどないので、九雀の認識が正しいのかはわからないのだが。確かに、独房と呼ぶには綺麗で、広すぎたかもしれない。ただ、安そうなパイプベッドが一つあるばかりで、本棚もなく、壁にある窓は遮光カーテンに覆われ外が一切見えないというこの真っ白な部屋の現状を考えると、やはりその言葉がどうもしっくりくるのである。娯楽が一切ない、寝るだけの部屋。部屋の隅に何か、二つ扉があるが、あれはそれぞれどこへ繋がっているのだろう。そんなことも思う。
「まさかとは思うのであるが、ここで香純ちゃんは生活しておるのか?」
「え? してませんよ。ここは、らお君のために作っていたお部屋です」
さらりと計画的な犯行を自供された。尤も、百八十を超えるこの肉体に合うバスローブがあった時点で、計画的なのは間違いなかったのだが。
「安心してください、トイレはありますからねぇ」
「こんな状態で、どう行けと?」
「んん? 大丈夫ですよぉ、そろそろ効果が切れると思います。強い代わりにそれほど長く効かないやつなので。まあそしたら違うの打ちますけど」
上手く歩けないとは思いますがぁ、多少は動けるようにはなりますよぉ。相変わらず間延びした口調で香純が言う。まあ――そちらの方がいくらかマシか。それに、動けるのなら、どうにか逃げる算段を立てられるやもしれぬ。
「あ、そうそう。窓は鉄柵嵌めてあるのでぇ。多分逃げるのは無理ですよ」
「左様か」
元より窓に期待などしていなかったので構わないが、そうなると、どこから逃げるべきであるかな、と九雀は思う。扉。施錠されるだろう。そもそも九雀の強さ、というか戦闘能力は、この肉体がかつて鍛えていたらしい、身体のバネや強度による速さに由来するところが非常に大きい。九雀はそれを自分で使いこなせるようにするだけで精一杯だったので、それ以上の能力というものは備わっていないのである。そのため、薬等で肉体の自由が奪われるとなると、九雀の戦闘能力は、笑ってしまうほどに低下する。大体、仮面そのものにまともな戦闘技能がないのだ。魔法やそれに類するような力が使えたらまだ役に立ったのだろうが、仮面にそのようなことはできない。つくづく無力である。
(……まあ、しばらく様子を見るか……)
それしか出来ないとも言う。「髪の毛乾かしましょう」と香純が横たわる肉体を起こして、ベッドボードに凭れさせるのを、無抵抗に受け入れる。ドライヤーのコンセントを挿そうとしているらしく、ベッドの横で屈みこんだ女に、コンセントはあるのか、と九雀は少しだけ思った。
「後でスマホも貸してあげますからね。電子書籍、沢山入れておきましたから!」
「ふむ」
正直、本は少しばかり嬉しかった。ブラシを入れられ、ドライヤーの温風が髪を乾かしていく。風の音で聞き取りづらいが、香純が続ける。
「ネットワークには繋げませんがぁ、オフラインで読めるように色々買っておきましたし。映画や音楽も入れておきましたので、しばらくは楽しめると思いますよぉ」
「わざわざ買ったのであるか?」
「え? ええ。わたしが趣味で持っていたものじゃ、らお君楽しめないでしょう?」
女の答えに、九雀は小さく、何度目かわからない唸り声を上げた。出来るだけ自分のことを楽しませようとする女の心遣いは確かに感謝に値するはずなのだが、如何せんこの状況が素直にそれを告げさせてくれない。
「……監禁されておるのでなければなあ……」
「いいじゃないですか、監禁ライフ。楽しんでくださいよぅ」
「せめて薬を打たれておらねば、まだ楽しいと感じられたのやもしれんであるがなあ」
「でも薬打たないと逃げちゃうじゃないですか? それともその肉体の足を折ってもいいんですか? 因みに、わたし的にベストなのは切り落としてしまうことです」
「もうその発言からして楽しみとは無縁だと思わんであるか?」
「思いませんねぇ」
熱い風と共に肉体の髪をブラッシングされながら、「左様か」とだけ九雀はぼやいた。この女と相互理解を深めることは既に諦めている。
「しかし映画であるか」
「お気に召しませんか?」
「気に召す以前に、実のところオレは、映画を殆ど見たことがない」
「あー。らお君のおうち、テレビもないですもんねぇ」
「加えて言うのであれば、オレは顔を覚えられぬであるからな」
顔を覚えられないということは、登場人物が覚えられないということであり、つまり九雀は映画を見ても、物によっては内容を理解すること自体が困難を極めるということになるのであった。
「多少ならどうにかなるのであるが、登場人物が多くなり過ぎると駄目なのであるよな。話をまともに追えん」
「そっか、そうですよね。そうか」
視覚に重きを置く媒体だとそういうことがあるのか、と香純が呟く。失念していましたね。その呟きに消沈の色はなかったが、多少の悔いが滲んでいた。その手は肉体の髪の毛を編み始めている。
「ごめんなさい、そういうところはあんまり考えてませんでした。それでも楽しめるものがあればいいんですけど」
「まあ、声や衣装が覚えられんわけではないであるからな。多少なら見られよう」
「登場人物が少ないものなら大丈夫ですかねぇ?」
「どちらかというと服が変わらぬものの方が有難いであるな」
「ううん……それなら、ゲームとかの方が良かったですかね」
キャラクターなら衣装殆ど変わりませんし、と香純が言って、「でもらお君ってゲームとか遊ばないですよね?」と首を傾げた。
「遊ばぬであるな」
「興味はないんですか?」
「興味がないわけではないのであるが。単に遊ぶ機会があまりないのであるよな」
九雀の一日は、本を読んだりUDCオブジェクトを弄ったりしているだけで終わってしまうことが殆どで、滅多にゲームに手を出すことがないのである。
「電気がないものであるから、デジタルゲームの類は遊べぬであるしな」
「なるほどぉ……」
香純が頷いて、それから、「やっぱり」と続けた。
「電気くらいは通した方がいいと思いますよ? ゲームもできますし。なにより、電気さえあればスマホが使えたわけでぇ、こんな状況になる前に誰かへ連絡できたわけですからぁ」
「それは痛感しておるよ……」
まあ、そんなことしようとしたら腕の一本くらい切り落としてましたけどぉ。そんな物騒なことをのんびり口にしながら、香純は、何時の間にやらリボンを取り出して九雀の髪に編み込んでいた。ポケットにでも入れていたのだろう、これもまた――香純の髪や服とはまた違う系統の――ピンク色をしていた。もしかするとこの女は、ピンク色が好きなのかもしれないと九雀は思った。
「ああ、そう言えば、ホラーなら見られるかもですねぇ。登場人物が一人だけのものとかありますし」
「それで映画として成り立つのであるか?」
「ホラーなら成り立つんですよね、これが」
そんな他愛のない会話を続けてしばらく、香純が「終わりました」と言って小さな鏡を差し出してきたので素直に覗き込めば、オレンジ色をした肉体の髪の一部が、細い三つ編みにされていた。
「どうです?」
「どうも何も」
三つ編みだなあと思うだけである。
「可愛くないですか?」
「香純ちゃんとしてはこの姿は可愛いのであるか?」
「え、はい。ピンクのリボンと髪の毛の色がいい感じだなって思ってます」
「左様か」
よくわからん。香純に合わせて己の『可愛い』の価値観をアップデートすべきなのかどうか九雀は迷い、結局アップデートしないことにしておいた。そもそも、可愛いという感情がどういったものなのか、九雀にはどうも理解できていないのだった。
「さてそれじゃ、ご飯とか買ってきますねぇ。帰って来る頃には薬が切れ始めてると思うので、新しいの使ってあげますから」
「『使ってあげる』と言うが、オレは求めておらぬのであるよなあ……」
三つ編みにされたままベッドに再び横たえられて、天井と女の顔を見ながらそう言えば、香純が柔らかく微笑んで、それから言った。
「でもこれは、わたしのやさしさなので」
その肉体をだるまにされるのは嫌でしょ? だから、薬を『使ってあげる』んですよ。
「友達は大切にするべきですからぁ」
じゃあ、大人しく待っていてくださいねぇ。女はそれだけ言って、視界から消えた。やがて部屋の扉を閉める音がして、女の気配がどこかへ消える。
「……」
はあ、とため息めいた声を漏らして、九雀は天井を見た。言いたいことは山ほどあった、友達を脅すなだとか、まだ友達になったつもりはないだとか、まずお前はどうして自分と友達になりたいと思ったのかそこを教えろだとか――だが、女は既にこの場から去っている。それに、下手なことを言ってあの女の神経を逆撫でするのも避けたかった。あの女はおそらく、九雀の発言によっては迷いなくこの肉体の手足を切断する。義手と義足でどうにかなると思っているからだ。女にとって生きた肉体というのは一切の価値がないもので、むしろ捨て去るべきものだとさえ思っているものなのに違いなかった。最悪、この肉体をバラバラにしても、代替品が用意できるなら問題がないという判断をするはずである。
しかし友達、友達――か。一人になってみて、初めてその言葉の意味を正面から考える。友達。友。友達に――なって欲しい。女は自分に、そう言った。
友達になる。
友達になる、など――
「……そんなもの……」
仮面には。
自分には。
――そんなことを考えても無意味だ。そう思った九雀は言葉を続けず、切り替える。ひとまず食事は与えられるらしいのはわかった。香純が、この状況でも『譲歩している』らしいことも理解した。となると問題は、『香純が最終的に何を求めているのか』である。自分と友達になりたいと女は言ったが、『何故そうしたいのか』が、九雀にはまるでわからない。
(……追々、聞き出してみるか)
流石に疲れた。元来、考えるのは得意ではない。既に眠たいとさえ思っている――朝の四時から穴掘りをさせられた挙句に投薬されて拉致監禁されたら誰でも疲れるはずだと九雀は疑っていない。トランクは狭くて正直居心地は最悪だったし、どうせ動けないのだ、香純が帰って来るまでしばらく休もう。そう決めて、思考を放棄する。
そうして女が再び扉を開けたのは、それから幾らか経ってからであった。
●
美潮香純は――美潮香純と呼ばれる女は、否、女でさえ、人でさえないかもしれない何かは、車を走らせながらぼんやり考えていた。ここまでは上手くいっている。ここまでは何の問題もない。だから、ここから先も、『一分の狂いもなく』目的を達成しなくてはならない。あの仮面――と、その肉体――のことは、かなり情報を収集したので、ある程度理解出来ていると思う。振る舞いから推測した『在り方』について言ってやれば息を詰めて黙っていたし――多分、自分の理解は正しい。
友達なんて。
友達――なんて。
「……なぎちゃん」
死んじゃったな。そんなことを思う。大人しい後輩だった。教団のメンバーだったなんて知らなかったけど。あの子と自分は友達だったのかな。ううん多分違う。友達。友達って、何だろう。わかってる。『わかってるよ』。
「……わたしは……」
『違う』。違う、違う違う違う。違うんです。正常な思考ができなくなって、香純は車を道路の脇に停める。駄目だ――全部捨てたはずなのに。まさかこんなわたしに魂なんてものがあると言うのか? 馬鹿らしい――くだらない。魂なんて、電気信号を詩的に表現したものに過ぎない。少なくとも、わたしのようなものには。わたしに魂なんてものは何処にもない、『そうでなくてはならない』のだ。だから香純はあのゲームの仕組みが知りたくて話をしていたし、あのゲームのことを否定したかった。いや、あるいは、あのゲームに魂があるのだということを――『絶対的に肯定したくてたまらなかった』。
あれが、ただ一人の人間の魂から作られて、今も『魂を持っている』のだということを。
「……」
助けてくださいよ。
助けてくださいよ。
助けてください。
誰でもいいんです。
誰でも。
お母さんもお父さんも役に立たないので、あいつらは要らないから、だから。
助けて。
「……あのランドセル、何回背負ったんだっけ……」
赤色のランドセル。ピンク色が欲しいって言ったけど、買ってもらえなかった。でも、小学生になれるのは嬉しくて、背負って、何回学校に行ったっけ。友達。友達なんていないよ、出来なかったよ、だってわたし、文字も読めないの。教科書読めないの。香純には要らないねって、もうすぐ神様と一緒に働くんだから文字なんて、ああ。あああ。憎い、憎いよね、全部全部憎いよ。こんな世界要らな、違う、違う違う違う――「違うんだってばッ!」
怒鳴って、ハンドルを殴ってしまってから、はっとする。今の自分の力で殴ったら、下手をすると車が壊れる。それに早くご飯を買って帰らないと。らお君とご飯を食べたいよ。薬が切れたら、らお君のことだしさっさとグリモアで帰っちゃう。それで組織に連絡されちゃう。あ、でも、わたし、ご飯、食べられないな。らお君の分だけ買って、それで。何買ってあげようかな。いい感じの写真が撮れるやつがいいなぁ、アレルギーはないはずだし、食事の好き嫌いもないはずだから、わたしの趣味で選んでいいかな。いいよね。うん。らお君は優しいから、多分許してくれる。車を車道に戻して走り出しながら、香純は一人、えへへと笑う。馬鹿みたいだと思った。
「わたし、」
わたしに、魂はあるか。
あのゲームは、あなたにだって魂はあると言った。誰かが助けてくれるかもしれないとも言った、あなたの友達になりたいとも。でも違うよ、違う、違うんだよ。
わたしは人間じゃないし。あなたたちとも『違う』。
わたしのともだちは。
わたしにとってのともだちは。
だから。
ああ、だから、ね。
「……らお君、わたしのともだちに……」
なって。なってください。
そして。
「わたしを……」
助けて。
●
帰ってきた女は、サンドイッチと、小さな――可愛らしい包みの――菓子を抱えていた。ピンク色のリボンをつけた薄い箱は、バレンタインの日にデパートなどで見た、チョコレートの箱に似ていた――というよりも、そのものであった。中に入った、これまたピンク色のチョコレートを見て、九雀は、「よくもまあここまでピンク色のものを集められるものであるなあ」などと――嫌味ではなく、心の底から、ただ――感心していた。
「わたしは食べられないんですが」と前置いて、両手足を縛られた九雀の横に、香純がサンドイッチの紙袋と、チョコレートの箱を開いた形で置く。それから色んな角度で写真を何枚も撮った。何をしているのかはよくわからない。買った食事の日記でもつけていて、写真を添付しているのだろうか。そうして満足したらしい女が顔を上げたのは、しばらくしてからであった。
「さてご飯……ですけど」
女は不意にサンドイッチを見下ろしてから、「忘れてましたね」と、言った。何を忘れたのかと――主に倫理観などは間違いなく忘れているのだがと九雀は思いながら――黙って見ていれば、ふらふらと何処かへと出ていった女は、包丁やフォークの類のカトラリーの一揃いを持って帰ってくるなり、サンドイッチを切り始めた。よく見れば、何かのケースのようなものも一緒に持ってきている。おそらくこの後打つ心算の薬だろう。
「ちゃんと食べさせてあげますからね」
「いや、薬が切れたら食べられるのであるから、もうしばらく放っておいてくれればいいのであるが」
事実、僅かに指先や顎程度なら動くようになってきている。それがわかっているからこそ香純も固形物を買ってきたのだろうし、あと十数分でどうにか自力で食事はできるようになるだろう。だが、女は、「いいえ」とサンドイッチを切り分けた包丁を置いた。
「いいえ――」
香純が、玩具を前にした子供の笑みで、焦げ目のついたパンに銀色のフォークを刺した。
「わたしがやってあげますよ」
――笑う女の意図がわかって――わかってしまって、九雀はただ、「興味本位でやっているとしか思えぬわけであるが」と前置いてから、淡々と言葉を続ける。
「貴様、この肉体の顔をそんなに見たいのであるか」
女の顔が、子供の『それ』から、得体の知れぬ怪物の『それ』に歪んだ。
「ええ。らお君が、その肉体の顔を見られてどれくらい怒るのか……見てみたいなって」
「……」
おかしい、と、流石の九雀も思った。女の行動に一貫性がない。友達は大事にすべきだと言って九雀の許可を取ろうとしながら、そのくせ九雀の踏み込まれたくない場所に無理矢理踏み込もうとする。何をしたいのかがわからない――この女は結局、何を得たいのだ?
最初から今まで、この女の行動は滅茶苦茶だった。何一つ九雀には理解ができない。拉致して脅しながら、九雀を慮って本や映画を用意する。しかも、それが楽しめなさそうだと思えば、真剣に落ち込んだり考え込んだりするような素振りも見せる。生命として丁寧に扱う時もあれば、全部忘れて乱暴に扱おうとする時もある。
「香純ちゃん」
「なんですか?」
「何か――オレへ『本当に頼みたいこと』があるのではないのであるか?」
笑顔を浮かべていた女が、す、と、表情を消した。
「香純ちゃん、」「それが」
九雀の言葉を遮って、無表情の女が言う。
「それが何か、今、関係ありますか?」
「あるであろう、『友達』になりたいなら――カッ」
銀色が閃いて、バター用らしき小さな丸いナイフが、仮面の表面を浅く斜めに、だが強く抉っていった。致命的ではないが確実な痛みに、九雀は呻きにも似た悲鳴を上げる。
「関係ないんですよ」
黒にも似た深いブラウンの目が、ぎらついた光で九雀を捉えている。――何かあるのだ、間違いなく。それだけは、いかな仮面にだってわかることだった。
だが、『何があるのか』。
それが本当に、まるでわからない。見当さえつかない、元よりこの女とは、それほど長い時間を過ごしたわけでもないのだ。
「……あ」呻く自分に、女が子供の顔に戻って、悲しげに眉根を寄せた。「すみません」
「わたし、気が長くなくて。だから、ごめんなさい、仮面を動かして、肉体に食べさせてもいいですか?」
今度断って、肉体に包丁を突き立てられたら。その想像で、仮面は女の提案を承諾した。
「……構わん。あまり動かすと咀嚼できぬから、気を付けてくれ」
「やったぁ!」
らお君のお顔、と楽しげに仮面を動かされるのは、率直に言って不愉快ではあった。自分がただ触られるだけならともかく、肉体の焦げた顔を見られるのがたまらなく嫌なのだ。九雀がこの顔を醜いと思っているから、などではない。この顔を見た他人が、肉体を傷つけるかもしれない、ということが、仮面には不安で仕方ないのだ。たとえこの肉体が『こうなることを許した』結果こうなっているのだとしても、それを見た人間が『むごい』と言えば、肉体はきっと傷つく。『許したこと』を否定されるから。『許した』自分と、この肉体の顔を『こう』した人間との関係までも否定されてしまうから。だから仮面は、この肉体の顔を、余程親しい人間の前以外では、僅かでも見せたくはなかった。加えて言えば、単純に、顔へこれほどの傷を負った人間は往々にして傷を隠したがるものだという知識が仮面にはある。だから、この状況は、九雀にとって、心底最悪と呼べるものに間違いなかったのだ。
「わあ、真っ黒ですねえ。これは綺麗に焼かれてるなあ……どんな火力で焼いたらこうなるんだろ、そもそもなんで焼いたのかな……あ、鼻は削いでから焼いたのか……うーん、鼻が要らなかった? でもなんで……んー、唇も結構焼け縮んでますねえ……口を閉じても歯が見えちゃってますね。でも歯自体は無事だなあ……そう言えば、虫歯はないんでしたっけ。偉いですねえ」
「……観察するな。さっさと口に入れるであるよ」
あまりにべたべたと顔に触るので、九雀も苛々と吐き捨てる。が、女は気分を害した様子もなく、「んんん」と唇を尖らせるばかりだった。
「仕方ないですね。もうちょっと見たいんですが」
はい口開けて、と言われて大人しく開いた口へ、フォークに刺さったままのサンドイッチをねじ込まれて――一口大と見えたが、思ったよりも大きかった――咳き込みそうになりながらも、どうにか肉体の顎でゆっくりと咀嚼する。いや、本当に大きい。この動きが鈍った顎では荷が重い、味としては、多分蟹か海老の甲殻類が入っている。確認する前に口の中へ入れられたので、どちらなのかまではわからなかった。香ばしく焼かれて水分を失い、硬くなったパンは、石のごとくである。こやつ、喉に詰まったらどうする気だ。オレは元々咀嚼がそれほど得意ではないのであるぞ。
「あれ、もしかして苦しいですか?」
「それを訊くか? 正気か?」
「とっくの昔に正気じゃないですけど?」
香純はきょとんとしている。くそったれが、と、自分にしては珍しい語彙を頭の中で吐き捨ててから、仮面はとりあえず、感じたままに伝える。
「口の中への入れ方が相変わらず生命への配慮を欠いておったな。とりあえず水分をくれ、そしてサンドイッチをもう半分のサイズに切れ、喉に詰まる」
「あ、このサイズじゃ無理でしたか……オレンジとりんご、どっちがいいですか?」
「……オレンジの方にしてくれ」
「はぁい」
そうして間延びした返事と共に――香純が肉体の顎を無理矢理こじ開けてサンドイッチを引きずり出したので、九雀は「ハ!?」と声を上げた。
「何、何を」
「え? 大きすぎるんですよね? 切ってもう一度入れてあげます」
「……、……ッッッ!!」
何を言えばいいのかわからない、が、そういうことをして欲しかったわけではなかった。それだけは確かなことだった。オレンジジュースでも飲めば多少はふやけて咀嚼しやすくなるだろうし――何故そんなことをするのか、理解ができない。
そこで、はたと九雀は気付いた。
この女――ちゃんと『食事をしたことがあるのか』?
あの虫に寄生されて――それからサイボーグとして肉体を得て。その時の肉体にどれだけ生体部分があったのかは知らないが、そこで食事をしたことがあるのだろうか。それに、『虫に寄生される前』もそうだ。香純の口振りからして、彼女の親がちゃんと食事をさせるような者だったとはあまり思えない。
だから香純には、『食事の仕方がわからない』のでは――ないか。
「香純ちゃん」
「なんですかぁ?」
「好きな食べ物は何であるか?」
「……え?」
やはり、女の手が止まった。歯形と唾液でぐちゃぐちゃになったサンドイッチをフォークで刺したまま、香純が驚いたような顔をする。
「なんでそんなこと訊くんですか?」
「いや何――友達になるならば、そう言った些細なこともちゃんと知っていた方がいいかと思ったのであるよ」
「……らお君は、その肉体の好き嫌い、知ってるんですかぁ?」
「何を食べさせると特別喜ぶかくらいは理解しておるよ。オレンジとりんごなら、オレンジの方が喜ぶ。肉と魚なら、魚の方がやや喜ぶように感じるな」
「……」
女が僅かに俯いて、サンドイッチを見た。
「……わかんないです」
フォークに刺した残骸のようなサンドイッチを、女が、また無理矢理開けさせた肉体の口の中へねじ込む。今度はそれほど無理なサイズではなかったので、咀嚼していく。
「給食は……美味しかったかな……」
「給食か」
「ええ。……食べ方が汚いって……クラスの子に、馬鹿にされましたけど」
だって、わたし、お箸使えないから。
「スプーンがついてくるメニューが……好きでしたね。フルーツのね、シロップのやつとか……カレーとか……シチューとか……」
でも、わたし、文字読めなかったから。
「わたしの好きだったメニューが、どんな料理だったのか、よく知らないんです。クラスの子が、今日はカレーだとか騒ぐから、そう認識してただけで……わたしが好きだったのは、本当にカレーだったのかなあ?」
「名前はそんなに大事なことではないと思うであるがな」
「……そうですか?」
「たとえ名前が記号でしかなかったとしても、そこに確かな『感情』があるなら、他の何がなくたっていいのだろう――と、オレは思うであるよ」
「……らお君」
香純がふにゃりと笑い――そして、フォークの先端を、仮面の額に思い切り突き立てた。衝撃で思わず、動きを取り戻し始めていた肉体を跳ねさせてしまって――それ以上に仮面は悲鳴を上げた。これは刺さっているか? いや、フォーク程度が刺さるほどに軟な素材ではないと自負している、だが、痛いものは痛い。
「わたしに優しくしようとするのは、本心ですか?」
「ク――ぉあ――」
「わたしは特別ですか?」
再びフォークが振り下ろされる。肉体に振り下ろさないのは――何故なのだろう。それを考えたいと思ったが、三度振り下ろされたフォークで仮面は悲鳴を更に上げ、フォークは先端が折れた。いつの間にか肉体の口から吐き出してしまっていたサンドイッチが、ベッドを汚しているのが見える。ひゅー、と肉体の喉が鳴った。
「……あ、」
香純が、ふらりと揺れた。
「違うんですよ。違う。わたしはらお君と友達になるんです」
明らかに常軌を逸した様子で、切り分けられていたサンドイッチを、今度は香純が、指で摘まんだ。
「はい、どうぞ……」
……もう、この女の目的には触らない方が得策か? だが知らないことには何もできん。逃げるのにも情報が要るのだ。九雀は痛みの響く自身に細く断続的に呻きを上げつつ、またサンドイッチを口に入れる。とりあえず食うべきだ。食わねば肉体がもたない。それを目的に、今度は何も言わず、咀嚼して飲み込む。それでようやく正体が知れたが、多分これは、海老だろう。
「美味しいですか?」
「まあ……そうであるな……」
それは確かだった。おそらく焼かれて温かったのであろうパンは既に冷めていたが、それでも美味いものではあった。もう一つ与えられたので大人しく咀嚼し、再び飲み込めば、更に次のサンドイッチが与えられる。香純が何も言わなかったので、ただ餌を食む雛鳥のように、九雀も無言でそれを食べた。
「それじゃあ薬を打ちましょうねぇ」
女がそう言ったのは、サンドイッチを食べ終わった頃であった。枷が外され、大分動くようになった腕を――振るって攻撃するには、女の指は、少々力が強すぎた。おそらく下手に動かそうとした瞬間へし折られるのは間違いない。最初カトラリーと一緒に持って来られたケースは果たして薬で、九雀はそのまま注射を打たれた。
「それじゃあ、しばらくわたしはお外に出ているのでぇ」
遊んでてくださいねえ、チョコも食べていいですからね、とスマートフォンを渡されて、香純はサンドイッチの紙袋やらの一切を片付けると、チョコレートの箱だけ置いて、そのまま部屋を出ていった。両手足の枷は外されたので、一先ず体を起こしてみて、九雀はベッドから下りる。どうにもひどい倦怠感であった。歩くにもやはり、支障がある。窓に近付き、僅かにカーテンを動かして外を覗く。女が言う通りの鉄柵越しに見えるのは、小さな庭と白い柵だけである。住宅街なのかどうかもわからない――いずれにせよ、鉄柵はどうにもできないのだからここは放置するしかあるまい。よろよろとまた歩き、扉を確認する。一つはトイレ、もう一つはシャワールームだった。洗面台には未開封の歯ブラシや歯磨き粉が置いてあった。その他に部屋にあるものと言えば、コンセント、それからネットに繋がっていないスマートフォンとチョコレートである。あの女の言動からして、どこかに監視カメラと盗聴器くらいはありそうなものであった。が、九雀には見つけられなかった。
今更ながら、まったく、厄介な状況になったものである。
歩くのが辛くなってきたので、探索をやめてベッドへ横たわる。せめていつも所持しているオブジェクトの類や武器があればとも思うが、ないのだから仕方がない。重たい腕を伸ばし、スマートフォンをつけてみる。アプリが幾つも入っていて、動画やら音楽やら本やら、それぞれで何らかの作品が見られるようであった。はあ、と適当に、どうやら本が読めるらしいアプリを起動する。本当に色々なジャンルがごちゃごちゃと入っていたので、九雀はとりあえず、一番上の左端から読んでいくことに決めたのであった。
(→続く)