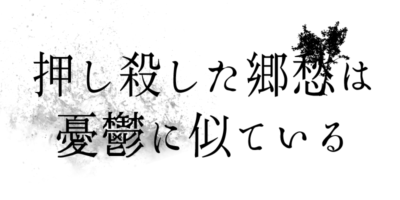小説リハビリの多分三月上旬くらいの話2。青薔薇の話が少し出て来ます。
※ひどい目に遭わされ過ぎて流石に九雀がキレています。グロはないですが男の裸があります。また、「ぼくのかんがえたさいきょうのUDCそしき」みたいな状態なのでなんだか色々気を付けてください。
本当に公開していいのか不安になってきました。中身は真面目な話をしているつもりです。あと公開してないモブの名前が出ています。執筆順を間違えました。
暗闇に詰め込まれて、どれほど経ったか。九雀は正確な時間感覚を持っているというわけでもなかったので、それはよくわからなかった。二十分ほどであったようにも思うし、一時間以上経っていたようにも思う。何にせよ、車の喧しいエンジン音に耐えながら、動かぬ手足を折り畳まれて、九雀はどこかに運ばれた。否――どこかというのは正しくない。
「つきましたよぉ。わたしのおうちです」
「……おうち、だと」
「はぁい」
開けられたトランクを、香純が覗き込んでいる。その背中には、打ちっ放しのコンクリートと思しき天井と、蛍光灯である。ガレージ――女の言葉が正しいのであれば、香純の自宅の、ガレージなのであろう。九雀は、女の家に連れて来られていた。
誘拐されたのは初めてであるなあ、などと、九雀はぼんやり考えていた。
「貴様は日本住まいだと思っていたであるが」
「本宅はそっちにあります。ここは、わたしが勝手に買って作った、別荘みたいな場所ですね! ラボって言った方がいいのかな? でも研究は別にしてないし……工房? うぅん、まあそんな感じの場所です」
「金持ちであるなぁ」
「節約の成果です! 機械の体は別にご飯を必要としませんしね!」
未だ動かぬ――本当に何を打ったのか、小一時間きっちり問い詰めたい――肉体を、香純がトランクから引き摺り出す。それから特に何も言わずコンクリートの床へ無頓着に放り出したので、九雀は鈍い悲鳴を上げた。こいつ、いい加減にしろ。
「泥がついてるので、洗いますねぇ」
言って、ふらりと女が背を向け、ガレージの隅へと向かっていく。その先には、巻かれたホースと蛇口がある。
痛烈に嫌な予感がした。
「待て!! 貴様、どうやって洗う気だッ!?」
「え? 普通に洗車用のホースで……」
振り向いた女はきょとんとした顔である。見ればその手には既に、やたら頑丈そうで、水圧の高い水を出せそうなノズルがあった。九雀は、心の底から、自分の危機回避能力に感謝した。この瞬間以上に己の本能とかそう言ったものに感謝したことはないかもしれないというくらいには感謝していた。自分に本能があるかは知らないが。ついでに、女の行動を把握できる状態で転がされた僥倖にも。
そして、当然キレた。
「きッさま、貴様、それ、それが拷問の自覚はあるか!? ないのであろうなあ!! それはな!! それは拷問というものなのであるよ!!」
怒鳴られた香純は、何を言われたのかよくわからない、と言ったような顔で数度瞬きをしてから、「あ」と小さく声を上げた。
「あ、ああー。そうですね。そうだ、そうです、まだ生身なんだった。ごめんなさい」
「機械になる予定もないのであるがな……」
疲れた。もう本当に疲れた。誰か助けてくれないか、と切実に願っていたが、普段屋敷へ籠ってしまって殆ど外部と連絡を取らない九雀は、他人との交流が希薄である。それはつまり、『自分が行方不明になってもすぐ探しに来てくれる者が極めて少ない』ということに相違なく、今既に九雀が捜索されている可能性は、爪の先ほどもなかった。買い物も二週間程度に一度なので、そちらから行方不明が発覚したとしても、後一週間はかかる見込みである。猟兵の中には一部定期的に出入りする者もいるにはいるが、今日、今、この瞬間に助けに来てくれる可能性は低かった。第一、ここまでのことをしでかしたこの女が対策をしていないともあまり思えない。それに、正直認めたくはないが、現状については自分の落ち度に近い以上、彼らの手を煩わせるというのはあまり好ましくないと九雀は思っていた――大体、それをしてもらうだけの理由も対価もないのだ。彼らは無関係である。
この肉体の自由が戻ればどうにか、と思うが、この女が薬の切れるタイミングを理解していないとは考えにくかった。となれば、とにかくできるだけ損耗を押さえながら時間を稼ぎたい。もしかしたら、その時間で解決の糸口が見つかったり、組織の人間がこいつをどうにかしてくれたりするかもしれないと、九雀は淡い期待を抱いているのである。そう言った期待とか希望とかいう他力本願は本来好きではないのだが、この場で誰かの助力を乞わずにどうにかする自信もなかった――というか、この女を野放しにしていた責任を取って欲しいというのが本音であった。メールと手紙については彼らも検閲していたのだろうし――そうでなければ彼らが自分宛の手紙の内容を知っているはずがない――こうなる前に止めなかったのは怠慢では、否、九雀がきちんと拒否しなかったからだろうか。早い段階できっぱりと拒絶しなかったから、大したことはないと放置されたのか。いやだが、普通に考えて、手紙をたまに返していただけでこんな事態になると思うか? 十通に一通返せばいいような頻度の返事で? いや思わん。思っていたら一通だって返していない。
いずれにせよ、万が一後遺症が残るような薬剤だったら、この状況が好転し次第、確実にこの女の息の根を止めてやろう。そんなことを考えながら、九雀はコンクリートの床から女を眺めて言う。
「せめて野良犬程度には生存の権利をくれ。そして生命として扱ってくれ、頼む」
「生命として扱ってるつもりではあるんですけど。つい忘れちゃうんですよぉ」
「忘れるな……」
馴染み深い諦念と、それに付随する無気力が頭を擡げそうになったが、ここでそれを受け容れてしまうと、肉体も道連れであることは理解していたので、どうにか踏みとどまる。諦めてはいけない、『いつものように』諦めるのは、今だけは絶対に許されない。
「洗うなら風呂とか……そう言ったものを使ってくれんか……」
「うーん……」
香純が首を傾げながら、ホースを元の位置に戻した。何故そこで思案する。あれか、泥まみれの人間を風呂で洗うのは嫌とでも言いたいのか。ふざけるなよ。
「というか、考えて欲しいのであるが、泥まみれになったのは貴様の責任なのであるよな」
「きさまって言うのやめてくださいよぅ。いつもみたいにかすみちゃんって呼んで!」
「早急に死んではくれんか、香純ちゃん……」
「やぁ! ひどくないですか? いつもは殺すのはあんまり……みたいな態度なのに」
「言っておくがオレはな、『死のうが死ぬまいがどうでもいい』から、『それならオレの勝手で終わらせるよりも終わらせない方がよい』と思っておるだけであるぞ」
「そうなんですかぁ? じゃあ、わたしはどうでもよくない?」
「今は少なくともまったくどうでもよくはない」
香純がにんまりと――大好きな本をプレゼントされた子供のように――笑って、九雀の傍にしゃがみ込む。
「わたしのこと特別ですか?」
「……ネガティブな意味であればな……」
まずその質問をする理由がわからない。この女の行動理由を理解できたことなど一度としてなかったような気はするが。香純が、いかにも不服であるといったように頬を膨らませて唇を尖らせた。
「えぇ? なんでですかぁ」
「ここまでの行いを省みて、香純ちゃんは本当に、オレから怒りを買わぬ言動をしていたと思うであるかな」
「んー? んん……まあ、ちょっと殴ったりバチッとしたり薬を打ったりホースの水で洗おうとしたりしてましたが……些細なことですよね!」
「本当か!? 本当に些細なことなのか……!?」
「まあなんでもいいじゃないですか、どうでもいいですよ。洗うことの方が先決です!」
「今から友達になろうとする相手にした仕打ちをどうでもいいとは流石のオレでも言わ――ぐぁっ」
黒い布を押し付けられて、肉体の頭部ごと巻かれた。何をする、と叫びそうになったが、それよりも先に、女が「らお君、そのままだと間取りを覚えちゃいますよねぇ」と言って、目的を理解する。事実、出来る限り間取りと調度品を覚えようと思っていたので、女の言葉は正しかった――こういうところが、心底性質が悪いと思う。幼いなら幼いで、徹頭徹尾幼く在るなら、もっと違った対応もできるというのに。
よいしょ、と香純は九雀を抱え上げ、ガレージから家の中へと入っていくようだった。決して最短距離は取らずに歩いていくのが腹立たしい。何度か角を曲がってから、女が足を止めて、九雀を再び床に降ろした。今度は乱暴でなかった、一応生命であることを尊重はしてもらえたらしい。
「おっふろー、おっふろー、らお君おっふろー」
何がそんなに楽しいのか、香純は調子はずれな歌を歌っている。見えていないと、本当に子どもがいるのではないかと思えるほどであった。風呂場の隅に転がされたまま、女が歌いながらバスタブを磨くのを聞く。しばらくして、どどど、と湯の音と共に湿気が九雀の方まで届いたので、湯を溜め始めたのだと知った。
「あ、靴と服、どうしますかね」
「好きにしろ。まあ、どうせであるし服は一緒に洗ってもらえると助かるである」
洗濯は嫌いではないが、面倒くさいので、やってもらえるならやってもらいたい。仮面は元より、怠惰な性質である。手を抜けるところや他人に任せられるところは任せておきたいのであった。香純が、んー、と思案の声を上げる。
「全部合わせてバスタブで、洗濯機みたい……にするのは、生身だとまずいですねぇ?」
「一生涯遠慮したいであるな」
実際『洗濯機のように』出来るのであろうことが恐ろしい。絶対にやめて欲しい、と仮面は思った。そもそも九雀は水に沈められるのと火に炙られるのが基本的に嫌いである。好きな者もそうそういないとは思うが。
「えー、じゃあ、脱がせていいですか?」
「……」
すぐに返事ができなくて、九雀は黙った。確かに話を統合すると、そうなるな。これほどまでに、自分の表情が変わらなかったことを悔やんだことはない。
はっきり言えば、非常に遠慮したかった。他人に肉体の裸を見せる趣味はなかったし、肉体自身も見られるのは嫌なのに違いないと思っていた。それに、この女の前でこれ以上無防備になりたくなかった。誰が好きでこのような女の前で無防備でいたいというのか。少なくとも九雀は嫌である。
だが、肉体は完全に麻痺していて相変わらず動く気配もない。それにこのままだと、本気で『人力』洗濯機に放り込まれそうである。ぬう、と九雀は黒い布の下で小さく呻いた。嫌な二者択一だった――だが背に腹は代えられぬか。
「……構わん」
苦渋の決断であった。唸るように返事をすると、「やったー!」と軽い歓声が聞こえた。何が嬉しいのか、やはり理解ができない。革の枷を外され、肉体の服を剥がされる。
女が、「子供の頃なんですけどね」と口を開いた。
「お人形をねぇ、買ってもらえなかったんです」
「ふむ」
「金色の髪のね、大きな目のお人形だったんです。なんて名前だったかな。キラキラした、ピンク色のドレスで。ドールハウスも一緒にあって、お風呂とかもあったんですよ」
仮面を覆う布を外されないまま、髪の毛だけ解かれ、抱え上げられてゆっくりとバスタブに入れられる。話から察するに、人形遊びでもしているつもりなのだろうか。九雀からすると、この現状は人形遊びというより介護の類に近いと思うのだが。第一、香純の言う人形とこの肉体の外見とは、明らかにかけ離れている。人型ならなんでもよいのか。布を多少緩められる感触があって、シャワーを肉体の頭部にかけられる。
仮面を伝う湯の温度は、ややぬるいくらいであった。
「ねぇねぇ、らお君、髪の毛乾かしたら、編み込みとかしていいですか?」
「駄目と言ったらやめるのであるか?」
「いちおう。だってともだちって、嫌なことはしないものですよね?」
「……」
それはそうなのだが。
言っていることは正しいが、前提として、香純は今、九雀の肉体に電気ショックを与えた上で薬剤によって麻痺させ、車のトランクに押し込んで拉致しているのである。そこからして既に間違っているのではないかと九雀は思い、そして言葉にはしなかった。面倒、というわけではなかった。ただ、なんとなく、言わない方がいいのだろうと思ったのであった。
「……別にそれくらいは構わん。切ったりしなければな」
「やったぁ!」
えへへ、とまた香純が笑って、仮面はどこか居心地が悪くなる。女の、この笑い方は苦手だった。
「シャンプーしますけど、いいですか?」
「シャンプーにいい悪いがあるのであるか?」
「いえ、石鹸が染み込んだらまずいのかなあって」
「む? ……いや? 気にしたことはないであるな。そもそもオレは、偶に支部の方で裏表洗われておるしなあ……自分でも出来る限り洗っておるし」
「あー、そう言えば、健康診断してましたっけ。診断結果見たことあります」
「うむ。病気は怖いであるからなあ」
仮面は未だ、人体に疎い。人体とその周囲は常に清潔にせねばならぬであるとか、運動が必要であるとか、そう言った本に載っているような『知識』は、勿論仮面も知っているし、実践するよう心掛けている。外傷もよくないと知っているから、怪我は出来るだけしないようにも気を付けている。何より怪我は痛いので、仮面も肉体も嫌だし、すぐにわかるのだ。だが、『肉体の内側からの感覚』となってくるとやはり、判断が難しかった。それでいて、些細な痛みや違和感が大病の元であったり、ものによると、痛みさえなかったりするという。仮面にそんなものの判別などつくわけがなかった。というわけで、仮面は、一度組織からの申し出で肉体の検査をしてもらってから、定期的な健康診断を受けているのであった。――と、そこで九雀は、漸く香純の言葉を完全に理解して、「うん!?」と声を上げた。
「診断結果を見た、だと? 香純ちゃんはそういうものを見られる立場におったのであるか?」
流石にそう言ったデータは、一般職員に公開していないはずだが。女は己をメカニックと称していたが、もしや医師か何かを兼任しているのだろうか。ならば薬剤もそう得体の知れないものではないのかもしれない、警戒し過ぎたやもしれぬな。悪いことをした。そうも考えた。
しかし女は、九雀の思考とは裏腹に、「え?」と驚いたような声を漏らした。それだけで、九雀は、女が医師の類でないことを悟る。
案の定、返ってきたのは、「あ、ごめんなさい」という謝罪であった。
「勝手にハッキングして覗きました」
でも証拠は残さないようにしたので、と悪びれもせず、女がシャンプーで肉体の髪の毛を洗い始めて、九雀は、やはり唸った。組織はこの女を野放しにするな。九雀の情報を覗けているということは、他の者の診断結果も覗けるということだ。個人情報も何もあったものではない。シャンプーは、作り物じみた花の匂いがした。
「ローズですよ」
訊く前から、香純が答える。
「薔薇の匂い、好きなんです」
「これは本物ではなかろう」
「いいんですよ。偽物でも」
たとえ偽物だったとしても、わたしは好きなんですから。
「それに、真贋って、そんなに大事なんでしょうか?」
「……いや。そうであるな、それに関しては、香純ちゃんが正しいとオレは思うであるよ」
すまぬ、と謝れば、女が笑った。先程のものとは違って、少し大人びた、吐息のような弱い笑い声が風呂場に落ちる。
「らお君、よくわかんないですよね。さっきまであんなに殺す殺すって言って怒ってたのに、どうして謝ってるんですか?」
「オレが悪いことをしたと思ったからであるよ」
「悪いって、どうして?」
「オレは、オレが常に正しいわけでないことを知っておる」
女の細い指が、肉体の頭皮を揉むように動いている。この女が、この指を、そっと肉体の首に持って行って縊ったら。それだけで、肉体は死ぬだろう。それを仮面は理解していて、だが、それでも、この女の好きにさせている。
それは何故だろう。
仮面には、己の『それ』がわからない。
「それなのに、オレは、『本物でない薔薇の匂いを好きなのはおかしいのではないか』と解釈できるような言葉を香純ちゃんに言った。さもオレが『正しい』ような口振りでな。人工香料の『それ』が本物と離れているからと言って、香純ちゃんの気持ちを否定した。それは、オレにとってはやるべきでないことだった」
そういう言葉で――容易に、他者は傷つく。それを仮面は知っていたはずだった。
『見たことがあった』はずだった。
相変わらず記憶にはないが、その残骸が、確かに九雀へ訴えていた、はずだったのに。
「怒っていたとは言え、あまりに無思慮に過ぎる。だから謝ったのであるよ」
「……らお君って、『わるいやつ』なのに、そういうところよくわかんないですねぇ?」
「『わるいやつ』が、皆他人を傷つけたがっているとは限らんである」
「そうですか?」
「そうであるよ。そも、『他人を傷つけたがること』は『悪』の必要条件ではないと思うであるがな」
「でも、他人を傷つけたことを謝れるのは『善』ではないでしょうか?」
「それならば、毎夜妻を殴っていることを謝る夫は『善』であるな」
「んん……」
香純が唸って、手を止める。
「まあ、それが善でも悪でもどちらでもよいのである。興味もない。ただ、善悪など、見る者の価値観に過ぎんとオレは思うであるよ」
「見る者、ですかぁ」
「うむ――だからオレは、こやつの……」
こやつの、と繰り返して、考える。この肉体の『何』になりたかったのだろうか。親。違うだろうと九雀は思った。親になりたかったわけではない。今でも、親とは思っていない。
ただ――自分は、この肉体の。
「……こやつの、仮面で在りたいのであるよ」
結局よくわからなくて、仮面はそう言った。仮面が仮面であることだけは、いつだって、どこにいたって、間違いのないことであったから。
「仮面ですかぁ」
それだけは、きっと叶ってるんでしょうねぇ。香純の言葉。
「思うんですけどぉ。この肉体の記憶、どれくらい残ってるんですかね」
「さあ。オレにもわからん」
「抽出できませんかねぇ?」
「出来たところでオレは見んであるぞ。他人の頭の中を覗くのは好かんである」
「じゃあわたしが見てもいいですかぁ?」
「どうして許可すると思ったのであるか?」
「いえ、許可がなければ勝手に見るだけなんですがぁ、可能なら取っておいた方がいいかなって」
「驚くほどに傍若無人であるな……」
「わたしの美徳だと思ってまぁす」
美徳の意味を辞書で引いて欲しいと九雀は思った。
「脳を取り出して、損傷したところを機械で補って戻したら、どうにかなりませんかね」
「出来るなら香純ちゃんの前に組織がやっておるであろう」
「えぇ? 本気でそう思ってるんですかぁ?」
「……どう言う意味であるか?」
「だって、それをやったら――らお君、UDC組織から逃げちゃうかもでしょ」
「……」
どう――だろう。
「いや……そんなことはないはずであるが。一応、今のオレの生活を保障しておるのは組織であるしな。意味がない」
「それって、らお君って言うか、『仮面』としての答えですよね。肉体がどう答えるか、わかるんですか?」
「……いや」
わからん、と正直に答える。仮面が肉体のことで理解することができるのは、ささやかな感情の振れくらいのものだ。何を考えて何をしたいのかなど、本当のところは理解できていない。
「ですよねぇ。そしたら、仮面としてはですよ? 肉体の言うことをぉ、多分、『尊重』しますよねぇ?」
「まあ……するであろうな」
「ってことはぁ、組織的に一番美味しいのは、組織にとっては無価値なUDCオブジェクト一つ二つあげておけば黙って仕事してくれる、今のらお君なんですよねぇ。じゃあ、組織がわざわざ、失敗してらお君から怨まれるリスクまで背負って、らお君の肉体を治してあげる必要はないんですよぉ。無駄ですしね。本人あんまり肉体の復元に興味ないっぽいし、出来ないって言っといても問題ないでしょー、って思うのは道理かなって」
「それは香純ちゃんの推測か?」
「まぁ、そぉですけどね。でもまず、組織って別にボランティア組織じゃないですからね。一枚岩でもないですし。最終的な目的が一緒で、同じように活動していて、相互の連携もしますがぁ。ほんとのところは、スタンスも違うし、得意分野も違う。わたしは今のところ関わったことがありませんがぁ、UDC-Pが嫌いな支部だってあるでしょうね。人でないものは全て殺してやる、と考えている人だっていますよ。実行するかどうかはともかくね。逆に全部救いたいって必死になってる人もいる。人がいっぱい集まってるので当然ですけど」
「それは知っておるが」
「んー。多分、ほんとの意味では理解してないと思いますよぉ。良くも悪くも、らお君ってワンマンですからね」
「ワンマン……か?」
「ええ。らお君、あんまり他人に頼ろうとしないって言うか……思い込んだら一直線と言いますか。とにかく、なんでも一人で全部やろうとして生活してるから、こうやってわたしに捕まってるんだと思いますけどねぇ。一人で考えて一人で動いて一人で失敗する。そういう生き方、よくないですよ?」
「まさか当の拉致誘拐犯に説教されるとは思わなんだな……」
中々できる体験ではない。ついでに言えば、このまま監禁も罪状に追加されるだろう。最初の電撃か何かは勿論、許可なく他人に薬物を投与するのも罪に問われたはずだと記憶している。何と言う罪になるのかは忘れてしまった。「とにかく」と香純が続ける。
「らお君のとこの支部はぁ、穏健派っていうか、『救いたがり』って感じなので、らお君の健康診断とかもしてくれたんだと思いますがぁ。支部長さんが足引きずってるとこからわかると思うんですけどぉ、サイボーグとか機械技術系、結構疎めなんですよね。あの、らお君と殴り合って入院したって言う、ぎーさん。あの人みたいなぁ、己の肉体一つでどうにかする!とか、あのー、えー、あ、りえさんなら、らお君わかりますかね。あの人みたいなUDC怪物利用しての情報収集とか、割とそう言うのに特化しててぇ」
「ふむ」
ぎーさんやりえさんというのは、おそらくエイミーやロランのことだろう。間違っていたとしたら、九雀にはもうわからない。そして、何故この女は、九雀が覚えている職員の名前まで把握しているのだろうか。騒ぎと共に入院したエイミーはともかく、ロランの方は何かあって知り合ったわけではないし、そう言った情報を香純に渡した記憶はないのだが。手紙やメールの内容は、常に個人的なことのみに留めていた。ストーカーの本領発揮というものなのかもしれないが、それなりに恐怖である。
「てなるとぉ。もし支部長さんが治してあげよう!って思ったとしてもですよ? 他の支部に打診しなきゃいけないわけなんですよぉ。肉体補修、補填系のUDC怪物の手持ちがあるなら、らお君に使うよりは、他の職員用に置いておきたいでしょうし。支部長さんが実際にどう考えていたかはわかんないですが、らお君へ恩を売るメリットと天秤にかけると、まあそっちかなーって。らお君がもっとガツガツ肉体治したい!って思ってたらまた違ったとは思いますがぁ」
「なるほど」
「それでぇ。他の支部に打診したとしてですね。そこで実際に治してもらえるか、って言うとですねぇ……まあ……確率はあんまり高くないかなー……って思うんですよね。大体、既に『戦えている』猟兵より、『戦えない』職員や一般人を助ける方が先ですし」
香純は淡々としている。
「困ったことに、世界中にいるんですよね、UDC怪物とかUDCオブジェクトって。人口は六十億なんてとっくに超えてるのにね。そうなると頭数が要るんですよ。少なくともうちの支部ではそう考えてます。そうなると、らお君に割いてるリソースってそんなにないっていうか」
間違いなくうちだと断るでしょうねぇ、とは香純の言であった。
「それにうちは結構、バリバリの……こう……『UDC殺すべし』みたいな派閥なので……」
「ああ……『一番美味しい状態を維持したい』か」
「まぁそぉです。わたしみたいなのが許されてる理由でもあります」
流石に外聞があるのでUDC-Pは犠牲にしませんがぁ、と言う女の存在は、恐ろしく説得力のあるものであった。
「納得であるなぁ……」
「でしょう?」
ということですから。香純が、張り切った声で言った。
「わたしの技術でサイボーグになってみませんか? 大丈夫、優しくします! 無料です! アフターケアも任せてください! 一生面倒見ますよ!」
「ならん。要らん」
「どうして!? どうしてですかぁ!?」
「理由は再三言っておると思うのであるがな……」
「もぉー……肉体が『何で出来ているか』なんてどうでもいいじゃないですかぁ……」
便利なのになぁ、とぼやきながら、香純が洗髪を再開する。湯が大分冷たくなってきていたからか、蛇口を捻る音がして、熱めの湯が足された。
「因みに、らお君の、あの薬の事件。あの事件の担当だった支部は、開発系に強いです。まあ、だから担当してたとも言えますが」
「開発?」
「主には薬とかですねぇ。ちょこっと、いえだいぶ、いえかなり正気を失うけど、腕が生える薬とか。まあほんとに人の腕かはよく知りませんが。あと、んー、そうですね。特殊な弾に込める中身の類とか……流石にわたしも詳しいことは見られていないんですよね。あそこはかなりしっかりしてたのでぇ」
まぁ、らお君のところも、わかってて入らせたみたいな感じはしましたがぁ。そんなことを言いながら、香純が肉体の毛先を洗う音がする。
「あとまぁ、きどさんって人からぁ、『次やったらお前の支部に何を言われたとしても絶対にお前を処分する、こっちの支部長には話をつけているから覚悟しておけ』って直々に連絡が来たので……流石に今はもう接触してません」
「まあ、当然の反応であるな……」
きどさん、というのは、木戸陽のことだろう。おそらく。木戸は『きどさん』なのか、と九雀はどうでもよいことを思った。名字の読みが二文字しかないからか。
「ほんと、メールですっごく丁寧に殺害予告されたのでわたしびっくりしちゃいましたよ。署名入りでぇ。時節の挨拶まで入ってましたよ? 内容はどう読んでも『次は殺す』なのに」
「もしオレの知っておる『きどさん』がそこまでしたのであれば、次は本当に殺されるであろうなあ……」
多少話をしただけだが、あの男がそれほど怒る姿は想像しにくい。事実、夏のあの時も、そう言った暴言などはなく、淡々と志弦に怒っていた。そんな男に『殺す』とまで言わしめたのだから、もう少し大人しくなっていて欲しかったと九雀は思った。無理であろうことは重々承知である。
「まあとにかくですね、らお君」
湿った布に閉ざされた暗闇で、女が言う。
「わたしたちって、多分、結局のところ――別にヒーロー御一行様じゃないんですよ」
「……」
「たとえ、わたしたちが、世界を救ったとしてもね」
だからわたしたちは、きっとあなたの肉体を救わないでしょう。
子供のような女は、大人の声音で、そう言った。
「勿論、そう呼ばれるに値する人も、沢山いるんでしょう。そうしたら、その人たちは、全部終わった後で、ヒーローと呼ばれるのかもしれない。世界を影で救った英雄って。でも、今はまだヒーローじゃない。それにわたしたちの幾らかは……きっと地獄に落ちますよ。そんなものがあるなら、ですけど」
「……だが」
「ん?」
「だが――それでも」
女の手が離れ、シャワーを頭にかけられる。
「それでも……香純ちゃんたちに救われた者はいるとオレは思うであるがな」
「……そうですかね」
水音の向こうで、女が喋っている。蜘蛛の糸は、わたしにも、垂れてくれますかね。その言葉に、九雀はただ、「それは流石に知らぬがなあ」と明るく笑った。
そんなことを呟くのなら、何故、『何もしなかった』のだろうと――僅かに考えながら。
(→続く)