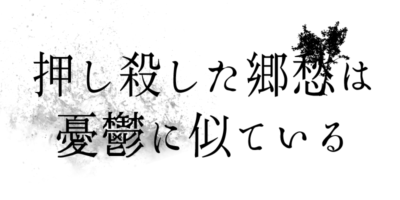コミッションで書かせていただいた259頁の理想郷オマケSS。
九雀のその後の話。
『無題』あるいは『非日常』、『いつの日にも存在しないティータイム』
「スコーンはどうであるか?」
仮面の質問に、女職員――に扮した『何か』は「美味しいです」と微笑んだ。仮面は女が何者であるか知らなかったし、『何か』に過ぎない『もの』であることには気付いていたが、特段気にはしなかった。自分に害意がないなら放置する、仮面はそういう仮面だった。
スコーンに、林檎のジャムと砂糖の入っていない生クリームをたっぷり乗せて、『何か』は紅茶を飲んでいる。スコーンは勿論、仮面が作ったものではなく、森を出てしばらくバスに乗った先の百貨店で購入したものだった。これもクッキーと同じく来客用に用意していたもので、まだ一応、湿気は吸っていない。
「紅茶も美味しいです。ありがとうございます」
「それは重畳である」
仮面は『何か』の前に座って、何にも手を付けず、ただ椅子の背凭れに体重を預けた。
「画集にはもう入りませんか?」
「気が向いたらまた入るとは思うであるよ。まあ、体力を使うであるからな。それほど頻繁に入るわけではないであるが」
「死んでしまうのは怖いですか?」
「死ぬよりも、命の責任を負うのが怖いのであるよ」
「取返しがつかないから?」
「そう。だがまあ――以前ほど恐怖はないであるな」
仮面は続ける。
「『そう生まれついて』、『そう生きて』、『そう死ぬ』。誰がどのように『生きた』としても、そして『死んだ』としても、その責任を取るのは……その『己』自身であると――気付いたであるからな」
「誰のせいでもない?」
「だが誰かのせいでもある」
オレが思っているより『生きる』というのは複雑であるからな。
「オレはオレ単体で存在していないということであるよ。オレはオレと関わった様々なものとの関係で構築されていて、常に変化し続ける。演じた『役割』がそのままオレになることもある。だがその前提の上で、誰が何と言ったとしても、確かに『オレのせい』だったことは在り、その責任は、『オレが取る』と『オレが決めた』のである。だから、『どんな生き方をしたとしても、責任を取るのは己自身』なのであるよ」
ふうん、と言って、『何か』がスコーンを食べきった。
「へんなひとたち。お互いにお互いの命を背負っている。お互いの命を占有している」
「ハハハ。だから結局、それだけが『よすが』なのであるよな」
「そうですか。ではそろそろ――ご自身を愛せそうですか?」
紅茶を飲みながら問う『何か』に、仮面は椅子の背に凭れたまま答える。
「どうであるかな。わからぬよ。しかしいつかはそうできるかもしれぬと……思い始めてはおるな」
「素敵ですね。その日を楽しみにしています」
そうしたら、いつの日にかあの画集の一頁になれるかもしれませんからね、と、女の姿をした『何か』は仮面の言葉に再び微笑んだ。ウェーブがかった金色の髪を長く垂らした、少女のような『何か』だった。
「そう言えば、入るのはいいんですけれども、もう私を囲むのはやめてくださいね。大きな人間に立ち塞がられるのって、普通に圧力を感じて怖いので」
私小さいので、と、事実として小柄な『何か』は二つ目のスコーンに手を伸ばすと、再びジャムとクリームを山ほど塗って食べ始めた。美味しいですねこれ、と言いながら咀嚼するその姿には、人として必要なすべてが揃っている。だがどこか非現実めいた姿であった。否――事実として非現実だ。夢なのかもしれない、と仮面は思っていた。春の日差しに見る、精細な白昼夢。自分が何を言っているのかも、本当はわかっていないのだ。
「『理想郷があるのだとしたら、それはどんな景色をしているんだろうか?』」
指に垂れたクリームを舐めながら、『何か』が言う。
「何度入れば、あなたの理想郷に辿り着けそうですか?」
「オレにはそんなものを欲しがるほどの情動はないであるよ」
「記憶の残滓程度で揺さぶられてしまうくせに?」
「揺れても元に戻るなら、意味などあるまい」
紅茶に、女がスライスレモンを入れて飲んだ。
「それもそうですね――『起き上がりこぼし』は子供をあやすだけの玩具ですから」
「ハハハ、上手いことを言う」
「でも子供にとっては『それ』が一番大切なものなんですよ」
その子が行き先を失った愛を預けたのは、あなたという玩具なんですからね。
「その愛を裏切らないであげてください」
「UDCオブジェクトの言葉とは思えぬなあ? 面白い」
「私は存外、子供が好きなんです。たとえページを破られたことがあろうと、落書きをされたことがあろうとね」
「ワハハ! 酷なことをされておるな!」
「まあ仕方ないじゃないですか。子供なんだし。死ぬことの意味さえ分からない子供は餌になりませんし。分別がないんですから、許してあげるしかないですよ」
そう言えば――あの画集で、子供の犠牲者とは相対しなかった。仮面はそんなことに何となく気付いた。
「それじゃあ。スコーンと紅茶、美味しかったですよ」
「おお、もうゆくのであるか。それではな」
女が立ち上がった。紅茶やスコーンは既にすべて食べられている。
「お待ちしておりますよ――モノクロームの理想郷、それをあなたが見つけるその日まで」
ところで私は、『UDCオブジェクト』ではないですよ。
それだけ女が最後に告げて――
カーテンが、風もないのにふと揺れた。
「……はて」
仮面は『何もない』テーブルに座っている己に気付いて、首を傾げた。応接間には、自分一人である。誰かをもてなしていたような気もするが――そんな痕跡はどこにもない。
――やれ、UDCオブジェクトのどれかに何かをされたであるかな。
それならば近日中に再点検をしなければ、と仮面は思った。
スコーンが二つと、ジャムにクリーム、それから紅茶が少しだけ減っているのに仮面が気付くのは――しばらく後の話である。
(了)