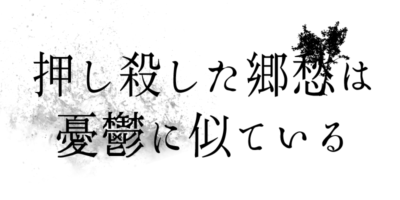去年二月バレンタインの話。去年もらった贈り物への所感を含む。
※「含む」と書きながらまだそこまで到達していません。一年経っても書ききれない(お前……)ので一旦前半部分として公開します……。多分前後編で終わる……終わるはずです……。
バレンタイン・デーという日における手作りのチョコレートと一仮面の考察について
その男がやってきたのは、『バレンタイン・デー』へ至る、二週間前のことであった。
「――ミスタ・ピーコック! バレンタインまで残り僅かですが、ちゃんと花は用意していますか?」
「……バレンタイン?」
雪の中、真っ赤な薔薇の花束を抱えたまま、スキップでもしそうな調子で九雀の住む屋敷の玄関ポーチまでやってきた男は、ここを管理している支部の職員であった。名をロラン・バリエという。中肉中背で、比較的彫りが深くはっきりとした顔立ちをしていること以外は、やはり特にこれと言って特徴のない、黒髪と黒目の男であった。強いて言うなら、他の職員より、多少肌の色が濃いか。九雀と共に居る肉体よりは薄い。ヒーローズアースもそうだが、UDCアースの人類にも、かなり色々な種類があるようだ。尤も、正直なところを言えば、単なる仮面であるところの九雀には、その違いによって人間の何が変わって来るのか、よくわかっていなかった。仮面にとって、人類とは一括りに人類である。
それはさておき、バレンタイン、とは。
「その、バレンタイン、とは一体何なのであるかロランちゃん?」
単語に馴染みがなかったので首を傾げると、男が、ばっさあ、と大仰に花束を揺すって、「そんな、ご存知ない?」と言った。
「うむ、知らぬ。であるから、教えてくれると助かるであるな」
「わかりました」
そうして笑顔のロランが滔々と説明してくれたところによると――二週間後に訪れる、バレンタイン・デーというのは、親しい相手や世話になった相手に感謝の気持ちを込めて花を贈る行事だという。日本の方ではチョコレートを渡すこともあり、『トモチョコ』とか言った名前で呼ばれることもあるらしいとのことであった。成程、と九雀は男の話を聞いていた。
ところで、殆どの職員の顔と名前が一致せず、誰のことも碌に認識していない九雀が何故ロランの名前は即座に思い出せる程度に覚えているのかと言えば、実に簡単な理由であった。このロランなる男、初対面で九雀と言う名前を告げた途端「なるほどピーコックですね!」と叫んで以来、自分を『ミスタ・ピーコック』と呼ぶのである。どう説明しても話を聞かないので、九雀は既にこの男から名を呼ばれることを諦めていた。まあどうせ偽名なので、呼ばれなくとも構わないと言えば構わないのだが。そのおかげでこの男を判別出来ている現状が良いのか悪いのか、九雀には判断がつきかねた。
あるいは――それが目的なのかもしれないとも思う。外見を変えるのは難しい。だが、『振る舞い』を変えるのは、外見を変えるよりは、と但し書きはつくものの、それなりに容易である。少なくとも、ある種の者にとっては。どちらにせよ、九雀はこの男の名前を覚えていた。それだけは確かであった。
ロランは笑顔で説明を終えた。
「――と。これでどのような行事か、お分かりいただけましたか?」
「大体は把握したである」
「それは重畳」
「だが、そのバレンタインは、二週間後なのであるよな? ではロランちゃんは、何故この屋敷にそんな花束を持って来ておるのであるか」
疑問に思って薔薇を示すと、ロランは「これですか?」と花束を抱えて、悲しげな表情を浮かべると、肩を竦めた。
「残念ですが、これはミスタ・ピーコックにお渡しするものではありません」
「左様か」
「左様です」
別に欲しくて訊いたわけではなかったのだが、面と向かって『お前のものじゃない』と言われてしまえば、少しばかりの悪戯心が芽生えて、ちょいと軽く指を伸ばしてやる。そうして、丁度指先が薔薇の花に触れるか触れないかと言ったところで、ロランが「ちょっと、駄目ですよ」と子供を咎めるような口調で九雀の手を押しのけた。
「これはこの屋敷のお墓に供えるために持ってきたんです。バレンタイン当日は仕事がありますからね、私」
「墓に? 何故であるか。バレンタインは世話になった者に花を贈るのであろう」
「だからですよ」
「ふむ?」
よくわからないまま、「お邪魔していいですか?」と男が問うので、許可を出す。いつものように、特に拒否する理由がなかったからである。
「ありがとうございます」
笑顔を崩さないままロランが歩き出すので、何となくその背に、「ついて行っても構わぬか?」と問いかけた。その言葉に、少し驚いた顔で男が振り向き、それから再び笑顔を浮かべて「いいですよ」と答えたので、九雀は男の後ろを歩き始める。
――屋敷に出入りする猟兵が作った小さな畑を通り過ぎ、ずっと進んだ先に、森と庭が融け合う境界線がある。自然と人工の境目などとっくに曖昧なくせに、それでもすぐ「ああ、ここからは森なのだ」と思うから、なんだかよくわからぬ場所であった。そんな庭の隅に、長い下草と朽ちた鉄扉に囲われた、小さな墓地がある。苔むした墓石に刻まれた名は、既に削れて久しいらしく、誰が埋まっているものか定かではないような場所だ。興味本位から、一つ二つ磨いてみたこともあるが、次の日には元に戻っていたし、九雀はどれの文字も読めなかった。単に掠れて読めなかったのだ。というわけで、九雀にとっては、その場所は何か価値がある場所というわけではなかった。ただ仮面は、『墓』というものを知ってから、それは出来るだけ尊重すべきものだろうと考えていたので、偶の草刈りだけはしていた。
日々こなすルーチンワークの中に、時折入って来る、ただの作業場所。
仮面にとって、その墓地は、そんな場所であった。
道すがら、二人の間に会話はなかった。ロランの方は知らないが、九雀は単純に、喋ることがなかったからだ。下手をすれば庭や屋敷についてはロランの方が詳しかったし、私的な会話をするほど男と仲がよいわけでもなかった。また、九雀には――仮面には、私的なことと呼べるほどの何かがあるわけでもなかった。
だから、九雀より先に、ロランが口を開いたのは、当たり前のことだったのだろう。
「……ミスタ・ピーコック」
「む?」
「このお墓に刻まれた人たちがどう言う人たちなのか、知っていますか?」
朽ちて役に立たなくなった鉄扉を踏み越え、中へと入っていった男に続き、己も墓地へと足を踏み入れた九雀は、こちらを見ずにそう言う男の、自分より――正確にはこの肉体より――頭一つ分ほど小さい男の後頭部を見た。勿論、死人の名さえ知らぬ九雀は首を横に振るしかない。「いや、知らぬ」と答えれば、ロランが続ける。
「この屋敷に住む人間は、殆どの場合死ぬんです」
「そうなのであるか?」
「ええ。実はそうなんですよ。実際、あなたも、ミス・ギーズに襲われたでしょう?」
ギーズ、という名は、当然覚えていた。九月の頭に、屋敷に惑わされてこの肉体を殺そうした女である。あの時書かされた反省文は中々厳しく、九雀は流石にもう少しキーボードに慣れておこうと思ったものであった。と言ってもタブレットやラップトップなどの電気製品を置いたとて、電気が無いこの屋敷で動かせないのはわかっていたので、タイプライターを検討していた。サクラミラージュあたりであれば良いものがあるのではないかと九雀は期待している。そして、そのような考えを九雀に抱かせた事件こそが、エイミーの事件だったのであった。
「うむ、エイミーちゃんのことは覚えておるであるぞ」
九雀は頷いて、答える。
「そう、そのエイミー・ギーズ、その事件です」
ロランが、薔薇を包んでいた紙とリボンを解く。どうやら、花束のまま供えるつもりではなかったらしい。
「ああいう風に襲われて、大体は死んでしまうんですよ」
「そうなのであるか」
「だからなのでしょうかね。この屋敷は、『最初に住人の墓を作る』んです」
「ふむふむ」
「……ミスタ・ピーコック、面白がってますね?」
振り向いたロランは、笑っていた。
「む、わかってしまうであるか?」
「わかりますよ! 私は、あなたのそういうところが、多分、好きですよ」
己の楽しみの前には死すらも厭わないところが。
「そう見えるであるか?」
「ええ、私にはね」
「ふうむ……別に死を忌避しておらぬわけではないのであるがな」
むしろ、死ぬのは御免被りたいと思っている。ふ、ふ、と、息だけでロランが笑った。
「でもあなたは――『自分』に『興味がない』でしょう」
「――、」
九雀は、仮面は、その言葉に。
「……いや? そんなことはないであるぞ」
否と口にするだけ、してみてから――わからない、と思った。
『自分自身に興味があるか?』
そんなことを――考えたことがあったろうか?
「ロランちゃんは、自分に興味があるのであるか?」
「ないですよ」
「ないのであるか」
「ええ。でもそれが肝要なんですよ、結局」
それは、『未来を掴む可能性』だ。ロランはそう言った。
「必要な時、必要な場所で。自分自身が『終わってしまう』可能性を、あなたは決して否定しない。そういうひとだと私は思っているんです。『興味がない』から」
「……」
「『世界』の勘定に、自分を入れない。いえ、『入れられない』。破滅主義というのとも違う。あなたは、元から『自分』に価値を置いていない。あなたは、『興味のないものに価値を置かない』から――だから、興味のない『自分』に、価値を見出さないんですよ」
だから興味のある『価値』のために『自分』をベットできる。
「『興味がない』……要するに『執着がない』んですよ、あなた。自分自身に」
「そう……なのであるかな」
呟いて、九雀は何となく、仮面の下の焦げ痕と、健常な皮膚の境目を指先で撫でた。自分自身が、終わってしまう可能性。本当にそれを肯定するかと言えば、九雀としてはノーである。自分の終焉はこの肉体の終焉である。九雀はそれを絶対に肯定しない。
だが――この肉体がおらず、自分が、自分自身のみであった時。
『葛籠雄九雀』でなく、ただ一つの『仮面』でしかない時。
自分の興味のために、終焉を迎えることを、『仮面』は。
(……肯定するのであるかな……)
わからない。肯定するような気もする。ただ、この肉体がいない、という前提は根本的に無意味だ。九雀はこの肉体がいるから『葛籠雄九雀』なのであり、この肉体がいなくなったのなら、それは即ち『葛籠雄九雀』の死を意味する。
『葛籠雄九雀』の死とは、仮面の生きる権利の消滅である。それが起こった時点で、仮面は生きていく必要がなくなる。それは仮面の感情に関わらず、事実である。
それが、自分の責任なのだと仮面は心底から考えていた。
『もう自分は、こいつをひとりぼっちにはしない』。
そう決めている。否、そうなった理由が不明である以上、『そう決まっている』だろうか。
第一、と、九雀は男の背を見ながら言う。
「『自身に執着がない』、というのは、よいことには聞こえぬが」
「そうですね――いいこと、ではないでしょう」
「では、何故『未来を掴む可能性』となる? 所詮、ただの自己破滅に思えるが」
ロランが、一輪の薔薇を、墓石に供えた。
「『自分を躊躇なく賭けられる』というのはね、諸刃の剣なんですよ、ミスタ・ピーコック」
一歩進んで、また別の一輪を。
「『破滅してでも何かを手に入れる』のは――誰にでもできることではありません」
知るために。
教えるために。
誰かの一頁を作るために。
「あなたがもし、『興味』のために『自身』を殺した後、それが誰かの役に立つとしたら」
それは、未来を繋ぐかもしれない。
「私は、あなたのそういうところが気に入っています」
「……」
「あなたの『終わり』が、誰かの『始まり』になるかもしれないでしょう? それは、誰にでもできることではないと私は思っていますよ」
雪の中で、薔薇が赤い。
仮面は、ぼんやりと考える。それは違う。オレは――『仮面』は、そんなことは、多分、できなかった。本当に、『好奇心のために自分を殺すことができた』のは――『始めるために終わらせる』ことを実際にやれていたのは――おそらく、自分ではなかった。それで言うのなら、自分は精々、『好奇心のために動いていたら結果的に破滅していた』程度だ。破滅したことを後悔しないだけで、目的あっての破滅ではない。
『破滅してでも何かを得たい』と動くほど……仮面は、『芯のある』性格をしていない。そう自覚していた。いい加減なのだ、きっと、生来。エイミーから紅茶の淹れ方を指摘されたのと同じく、ただ、生き方が雑なのである。勘定に入れられないというよりも、まずその勘定ができていない、間違っている。それだけだ。
だから仮面は、「ふぅむ」と首を傾げるようにしてから、ロランに答える。
「買い被り過ぎであるよなあ。オレはただ……」
ただ、何だろう、と九雀は思った。楽しく過ごしたくて。それは確かだ。だが。
(――『何故、それを楽しいと思うのか』。……)
その理由は、九雀にだって、わからない。明確にこれと言った動機はないように思うが、それすら定かではない。『それは楽しいことだ』という、原因の消え去った結果だけが、九雀の中で宙ぶらりんに存在しているだけなのだ。何があって『そう』覚えたのか、今となってはわからない。墓地の停滞した空気が、九雀の記憶の洞に淀む。少し考えて、仮面は結局、事実だけを伝えた。
「……ただ、オレにとって……それは、『楽しい』こと、なのであるよ」
「そうなんでしょうね。それは私にも少しわかりますし」
これでも、UDC怪物を身に宿したりもしているんですよ、と、ロランが白い歯でニッと笑う。そう言われても、男の姿は、他の人間と寸分違わない。
「尤も、戦うのは性分でないので、専ら情報収集や処理で『頭』を使うことが多いですが」
「ははあ、成程」
得心に頷き、一度詳細を教えて欲しいものであるなあ、などと思っていると、男が僅かに苦笑を浮かべた。
「まあ、これと言って取り柄のない人間の足掻きとしては上出来だと思っていますよ」
話を戻しましょう、とロランが言って、また薔薇を一輪置いた。
「先に言った通り、この屋敷は、最初に住人の墓を作ります。何度実験をしても、必ず住人の数だけ『墓』は増えるのです。百年は経っていそうな、古びた墓がね。それは、屋敷が、住人をいずれ殺すからだろうと我々は考えています」
「しかし」九雀は首を傾げる。「この屋敷は、そもそも、『自らを他人に見つからぬよう迷彩する』特性があったと記憶しておるのであるがな。最終的に殺すことが決まっておるというのであれば、何故、そんなことをするのであるか? 守っておるようにすら思えるが」
「実際に、守っているんですよ、おそらく」
「ふむ?」
「ここからは私個人の憶測で申し訳ないのですが――この屋敷は、住人の脆弱さを『怨んでいる』のではないでしょうか」
「怨み、であるか」
「そう。『ここまでして守ってやっているのに、どうして侵入者を許してしまうのか』。そう思っているのではないかと私などは考えますね」
「『だから』殺す?」
「はい。この屋敷の井戸は枯れません。この庭に植わった植物は、異常と呼べる速さで成長します。森では薪も拾える。それはつまり、食を与えているということではないかと思うのですね、私は。まあ動物がいないので、この屋敷のみで生きるには難しいところですが……しかしそれでも、どうもこの屋敷は、『どうやったら住人を守れるか』を考えてこんな在り様をしているように思えて仕方がない」
面白い話だった。ロランが、動物の足跡さえない真っ白な雪を靴底で踏みながら、薔薇を供えていく。
「それなのに、当の住人は、危険を招き入れる、と。ふむ、それは確かに、屋敷からすると気に入らぬことであるやもしれぬなあ」
「ま、同僚たちには却下された考えですがね」
根拠もない、とロランが肩を竦める。
「全部当て推量の妄想ですよ。実際、UDCオブジェクトに『人を守る』意思があるとは思えませんしね」
「いや、興味深いであるよ。オレは死人の願いに加担した邪神を知っておるし――この屋敷にとっては、『守った』『結果』が、ただ『滅び』になるだけなのやもしれぬなあ?」
「個人的に言うなら、その可能性は十分あるのではないかと思います。『善きことを成そうとする』ことは、『何かを救う』ことや、『味方である』ことと必ずしもイコールになるわけではないですから。時には、善意こそが他人を滅ぼすことさえある」
「ハハハ! 確かに!」
大笑し、「と、なると」と九雀は言う。
「最初から墓を作っておくのは、屋敷の『諦め』なのであるかな」
「あるいは、こうも考えられます。屋敷は『住人を殺すための理由を必要としている』。それがなくては『殺せない』。我々の中で比較的受け容れられる論はこちらですね」
「ははあ……『ここまでしても自らを危険に晒すような愚者は殺されても仕方ない』……と言ったような理屈であるか。それが屋敷には『必要』であると」
「そうです」
随分と楽しくなってきたな、と思ったところで、ロランが不意に、くしゃみをした。そう言えば、今自分たちがいるのは、雪に埋もれた墓場なのであった。
「ああ、すみません、ミスタ・ピーコック」
「とんでもないであるよ。体が冷えたのではないか? 早く用事を済ませて、帰った方がよい。それとも、暖炉で温まってゆくであるかな?」
「いえ……実はこの後も仕事があるので……」
「何、そうだったのであるか? 随分と忙しいであるなあ」
「そうなんですよねえ。困ったものです」
暇な方が好きなんですけれども、と言いながら、ロランが笑う。
「まあ、長々話をしましたが、そういうことなのですよ。ここの墓は、歴代住人の墓です。そしてここには、我々UDC組織が実験で使った『住人』たちの墓もある」
だから私はここに、バレンタイン・デーの花を贈るんですよ。ロランは一輪また手に取ると、「真っ赤な薔薇はただの趣味ですけれどね!」と軽く振った。
「赤っていい色ですよね。それにこの季節は赤が雪に映えて綺麗です」
「そうであるなあ」
日本の、雪に南天が実っているのも綺麗だと九雀は思うので、素直に肯定する。ロランはそんな九雀に、ですよね、と頷いてから背を向けると、雪を踏み分けて、ここからは言葉もなく、ただ一輪ずつ、丁寧に埋もれた墓石へと供えていく。どれを選ぶわけでもない、男は薔薇を、すべての墓に供えていた。墓石は、瓦礫のようなものまで合わせれば、軽く三十を超えていると仮面は知っていた。
やがてロランが丁度二輪の薔薇と、古びた墓を二つ残して帰ってきて、笑顔のまま、九雀を見た。あの墓には供えないのかと九雀が問うより先に、男が口を開く。
「――さて、私があなたを好む理由を、ご理解いただけましたか?」
「ぬう?」
突然の質問に少し首を捻ってみる。三秒ほどで、仮面は思考を諦めた。確かにロランは、仮面が『自身に興味がない』からこそ、そこに『未来を繋ぐ可能性』を見出しており、気に入っているのだと言ってはいた。だが、それを理解できたかと言われると、どうも理解できなかった。強いて言うなら、『ロランちゃんはオレに何がしかの幻想を抱いており、その幻想を見て好きだと言っておるのではないか?』と感じたというのが正直なところであったが、ほぼ間違いなくそんな答えは求められていないだろう。いや、それが答えなのか? わからない。あまりにも難題である。
結局九雀は、首を捻ったまま、返事をした。
「いや、わからぬであるな」
「そうですか……。ですが、いつかわかってもらえると私はとても嬉しいですよ、ミスタ・ピーコック。その日が来ることを祈っています」
「善処するであるよ」
理解力に自信がないので、出来るかどうかはわからないが。
「それでは、手始めに、これを差し上げます」
「む?」
差し出された薔薇を受け取って、九雀は疑問を言葉にする。
「先程はオレの分ではないと言ってはおらなんだか?」
「気が変わりました。ついでに言えば、余りました」
「左様であるか」
何にせよ、貰い物は嬉しいものだ――と世間一般では言われる。それに、こういう時は、ありがとうと言っておくべきであると九雀は知っていた。ただ、どうも、感情は凪いでいる――余りものを渡されたことに怒っていると言うわけですらない。凪だ。おそらく――自分は、やはり心底『どうでもよい』と思っているのだろう。そもそも、何故ロランが自分を好いているのか理解できたかという質問に答えられない時点で、この薔薇を差し出された理由など当然理解できていないのである。
流石の仮面も、余ったという言葉を真に受けるほどには愚かでないつもりだ。墓の数くらいこの男ならば、というよりもUDC職員であるのなら把握しているはずだから、丁度二輪残るように持ってきたのは間違いがない。つまりこの男は、最初から九雀に花を渡すつもりだったのだ、バレンタインの感謝の花を。だが、ここへ至るまでの行動の理由は、まるで推測もできなかった。そして、興味がないことは理解どころか推測もできない性質だと九雀は己を把握していたから、自分が男の行動に対してどう感じているかなど、考えるまでもなく自明なのだった。
それよりも九雀は、先程の屋敷の話の続きをもっとしたかった。
とは言え、仕事があるという男を引き留めて話をさせるのはよくない。それくらいは理解できる、九雀にも、その分別はあるのだ。
それにこれは、『形』だった。ロラン・バリエという男が九雀と、おそらくこの肉体へ向けた感情の『形』。『形』あるものまでも無下にするのは嫌だった。たとえ理解できないものであったとしても、それを受け容れなくなってしまったら――自分は最後に、『いつか』と同じことをしてしまう。覚えのない、『いつか』と同じことを。
だから九雀は、薔薇を受け取って呵々と笑ってから、できるだけ明るい声で、「すまぬな。感謝するであるよ!」と答えたのだった。そして、そんな仮面に、ロランは、ふ、と柔らかく目を細めてから、「どういたしまして」と微笑んだ。やはりこれが正しい行動であったようだ。九雀はどうも他人の機微に疎いので、こういう時は博打でもしているような気分になることがある。博打は盛り上がるが結果が残らないことが多いので、然程好きではない。
「喜んでもらえたなら、次は残しておいて欲しいというのが私の願いですかね」
「む、どうやって残せばよいのであるかな? オレは花の保存方法を知らぬであるよ」
「ドライフラワーの作り方、今度印刷して持ってきますよ」
「それまでに枯れておらんかなあ……」
「アハハ、そうかもしれませんね!」
来た時と同じく、先んじて歩き始めたロランを追って、九雀は屋敷の玄関まで戻る。そうして、それでは失礼しますね、と手を振って去った男の鼻と耳はすっかり赤くなっていた。
これが、二月の始めのことだった。
(→続く)