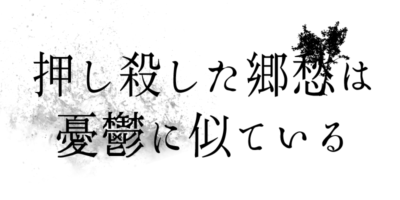※コミッションで書かせていただいた小説、「259頁の理想郷」の冒頭部分サンプルです。実際は文庫サイズのpdfデータです。
※無断転載、無断アップロードなどは禁止となっております。
※今後同人誌などを発行した際に再録される可能性があります。また、それに伴い、一部誤字脱字などの細かい改稿などが行われる可能性があります。
※この小説は株式会社トミーウォーカー運営のPBW「第六猟兵」の二次創作ガイドラインに基づき制作されたものです。
259頁の理想郷
理想郷があるのだとしたら、それはどんな景色をしているんだろうか?
●
――ああ、まずい、と思った。
それと同時に、さくり、と、得体の知れない影の牙が、まるでケーキでも食べるみたいにして、剣を握っていたアンテロの腕を食んだ。九雀が自分の名を鋭く叫び、ばね仕掛けのように跳ねて、一息に自分の方まで距離を詰めると、左足を軸にして跳び上がり、中々の勢いで宙を回って蹴りを放った。それに吹き飛ばされた影が、周りの風景に溶け込んで消える。一連の動作を見ながら、アンテロは、クジャク君は身が軽いんだねえ、などとどうでもよいことを考えていた。食われた腕はなくなっていた。着地した九雀が、自分を見る。
「……大丈夫なのであるか、あー、その……腕は?」
痛くはないのか、と九雀は言外に聞いていた。痛い――痛いのだろうか。モノクロームの非現実に侵食された肉体は、まるで少し昔の自分のようで、ひどく鈍い感覚を、じわじわと広げるだけだった。それに反して、シャツの袖を染め上げながら、白い床へぼたぼたと大量の黒い液体が落ちていくのは不思議な心地である。
「いや……これがどうして、少し切ったかもな、くらいの痛みしかないよ」
「絵画との同化が進んでおるのであるかな……何にせよ念のため止血をしておくか」
そう言って仮面が取り出した救急セットは、以前アンテロが贈ったものであった。
「それ、使ってくれているんだねえ」
「使わぬに越したことはなかったのであるがな」
有難く使わせてもらっておるよ、と仮面が、アンテロの千切れた腕を止血帯で固く縛る。
「正直使い慣れてはおらぬ故、さっさと出て治療をする必要があるであるな」
「まあ、最悪俺はこの仮体が死んでも、クジャク君が本体さえ持ち帰ってくれればいいんだけれどね」
九雀が片付けをしている間に、残った方の腕で剣を拾う。これまで持って行かれなくて良かった、武器がなくなるのは困るから。剣を握ったままだった手首は捨てた、どうせ仮体が死ねば戻って来る。九雀が、僅かな沈黙を挟んで、それから「ぬう」と唸った。
「いくら帰って来ると言ってもな。流石に目の前で死なれるのは寝覚めが悪いので勘弁して欲しいのであるが」
しかも半ば今回はオレのせいであるし、と――おそらくヒトであれば渋い顔をしているのだろうと推測されるような声音で九雀が言った。そんな仮面に、アンテロは笑う。
「クジャク君のせいじゃあないさ。俺も『面白そうだ』と思ったからこそ首を突っ込んだんだ」
それに報酬も出るわけだしね。そう答えれば、九雀が、フハ、と軽く笑った。
「お互い『面白そう』で大怪我をして帰りそうであるなぁ」
「まったく」
さて行こうか、と、二人連れ立って歩き出す。向かうは扉、次のページである。
「絶対に始末をつけてオレのコレクションに加えてやるであるからな……」
「ふふ、君のそういうところ、初めて見たよ」
「まあ、グリモア猟兵の予知が関わるとほぼ破壊が目的になるであるからなぁ」
あれはどうにも張り合いがない、などと、そんな他愛のない会話をしながら――アンテロと九雀は見つけた扉をくぐった。
●
それは、とある春のことだった。
「へえ、人を食う画集」
「そうなのであるよ」
適当に――ホテル代を稼ぐ程度の仕事を請け負うために――ヨーロッパの片隅にある、UDC組織の支部を訪れたアンテロは、葛籠雄九雀と鉢合わせしたのであった。何やら支部の職員――若い女だった。名前は知らない――と揉めているようであったので、久しぶりの挨拶もそこそこに近付いてみた結果が、冒頭の会話である。なお、近付いた理由は興味本位による。これが他の者であればおそらく面倒に関わりたくないとアンテロは迂回するか日を改めていただろう。
して、この画集、職員に曰く『人を食う』。文字通りの意味であるらしい。画集を開くと、どのページにも精緻なエッチングで描かれた美しいモノクロの絵画が載っている。絵画の題材はどれも一貫して、『人のいる風景』であるのだと、職員は言った。
荘厳な教会から長閑な田園風景、はたまた退廃に満ちた廃墟や耽美と呼ぶべき古城など、様々な内容の『景色』と思しきものと、その中に立つ人々を描いているのだという。景色と人物はちぐはぐで、廃墟にネグリジェの女がいたり、中世の街を描いたような場所で現代の服を着た男がいたりと、シュールレアリスムのような様相をしているが、あれは取り込まれた人間の末路であろうとは職員の言である。そのような画集であるから、初めのうちは被害者も、奇妙でこそあれ、美しい絵画だと思ってページをめくっている――が、気が付けば、あたりはすっかり『最後に開いていた絵画』の景色へと変貌している。
「出る方法は比較的簡単なんですよ」
絵画の中の謎を解き、『己が絵画の一部となる前に最後のページへ辿り着く扉を見つける』という、ただそれだけのこと。謎さえ難しくなければ、子供でもクリアできそうだなと話を聞いた直後のアンテロは思った。
しかし。
「そうは問屋が卸さないんですよね」
職員は、沈痛な面持ちでそう続けた。扉を見つけて出ようとすると、途中で必ず『怪物が出る』。尤も便宜上一括に怪物と称しているだけで、その姿は様々であることが、生還した被害者の証言でわかっているとのことであった。これを殺せた者は今のところ誰もおらず、生還者は皆、どうにか逃げるか、追い払っては隠れてやり過ごし、見つけた扉から出てきただけなのだと職員は――おそらく九雀にも同じ説明をしたのだろう、ややうんざりした口調で――説明を締めた。
そういうわけで、猟兵にどうにかしてもらおうとしていたらしいのだが。
そこで運良く――あるいは職員にとっては運悪く――遭遇したのが九雀だったのである。
「成程ねえ」
「いやはや、話を聞いてどうしても欲しくなってな……始末をする代わりにもらえぬものかと駄々をこねておったところなのであるよ」
恥ずかしいところを見せたであるなあ、と九雀が頭を掻いてハハハと笑った。そんな仮面に、揉めていた女職員が、溜息混じりに、胸に抱いていた黒い革のケースを――おそらく、そこに画集が入っているのに違いない――をいっそう強く抱きしめる。
「ですから、本当に危険なんですよ。帰って来る方法以外何もわかってないんですから」
「だからこそ猟兵に始末をつけさせようとしておったのであろう?」
「それはそうですが、それは主に外部からの破壊を想定していたので……」
最低でも封印などでした、と苦虫を噛み潰したような顔で女職員が目を逸らす。
「クジャク君はどうしようとしていたんだい?」
「む?」
仮面が、猛禽のように首を傾げた。威嚇ではなく、単純にモーションが大きいだけであるとアンテロは知っていた――何せ仮面は表情が変わらないから。
「簡単であるよ。俺が中に入って怪物を殺せば、画集だけ残してコレクションできるのではないかと思ってな」
「だからそれが出来た人がいないんですってば!」
女職員が、焦ったように言う。
「力不足で申し訳ないんですけれども、ツヅラオさんがこの本から帰って来られなくなっても、わたしたちじゃ回収出来ないですよ? というか多分死にますし」
「ふーむ……猟兵でも殺せぬものであるかなあ?」
「それはわからないですけど……それすらわからないのに単身異空間へ行くなんて危険すぎるじゃないですか! もう少し自分の身を省みてくださいよ!」
だから破壊してもらう予定なんです、と隠すようにケースを抱く女職員は、九雀の説得に相当苦労しているようであった。収集癖があると聞いていたけれど、どうやらそれが、存分に発揮されているようだ。ふうん、とアンテロは少し考える。人を食う画集――絵画の中に取り込まれる。殺せない怪物。絵の中を歩いて謎を解かなければ出られず、出られなければ絵画となる――成程、自分も少しだけ、興味が湧いた。覗き込むようにケースを見れば、女職員が『厄介な人が増えた』とでも言いたげに不安な瞳をする。
「な、なんでしょうか」
「いや何、少し質問があってね。そもそもその『怪物』とやらは、どういったものなんだい? 君たちでも殺せなかったんだろう、強いから殺せなかったのかな?」
「いえ、そういうわけではないんですけれども……」
女職員は口の中でもごもごと言葉を濁す。
「それじゃあもう一つ質問なのだけど――」
アンテロは、自分や仮面より頭一つ分以上小さい女職員の、怯える目を見下ろしたまま、にやりと悪戯な笑みを浮かべた。
「――『それ』の始末をつけたら、幾らぐらいもらえるのかな?」
●
「あのねえ」
シュコー、と、女のつけたガスマスクが音を鳴らした。
「とりあえず今後は、デカい男二人で女の子を取り囲むのだけはやめてあげてくれ」
キミら自分の身長わかってるか?と、灰色がかったブロンドの――顔が全面ガスマスクに覆われているので、その容貌はわからなかった――女、薄鼠・D・クロエはそう言った。画集を管理している部署の部長であるとのことで、最終的に、先程の女性職員が彼女に判断を仰いだのだった。
結果、女とアンテロたちは、画集の入ったケースを机に置いた状態で、現在応接室と思しき部屋で相対していた。画商に扮した支部であるからか、応接室はモノクロームに纏められた、モダンな――と称されるのだろう、アンテロは詳しくなかったが――テイストに内装を統一されている。清潔感の強い、中々好みのインテリアであった。
「取り囲んだつもりはなかったのであるが、すまぬ」
クロエの言葉で九雀が素直に謝ったので、アンテロも、「ごめんね」と謝る。特に悪いことをしたとは思っていなかったが。白い革の大きなソファに九雀と並んで座り、僅かに口角を上げたまま言えば、クロエは、ハー、とガスマスクの下で溜息をついて額を指で押さえた。
「キミらってやつは、まあいいけども。人格破綻、結構なことさ……」
第一キミらの場合、ヒトかも怪しいわけだしな、とクロエが体勢を崩し、同じく白い革の張られたチェアへと体重をかけた。机の上には画集の他、珈琲の一つもない。九雀とクロエは見たまま飲めず、アンテロは断ったからである。
「あー、そう、ミスター・ツヅラオは、ほんとに欲しいなら、今度から直接ワタシに言ってくれたまえ。ワタシのガスマスクなら覚えられるだろ? ヒラの子に食い下がったって駄目だって言うしかないからね。というか仕事が増えるから本気でやめてくれ」
「む。すまぬな、承知したである」
「それで、ミスター・ヴィルスカは単純に仕事が欲しいということだね……成程わかった、OK、全部了解した。いいよ。画集はあげるし、仕事もあげよう。ワタシは面倒なのが嫌いでね、ワタシに許可できることなら全部許可してあげるさ」
「本当であるか?」
九雀が興奮したように――おそらく実際興奮して――若干身を乗り出すのを、アンテロはやはり、珍しいな、と見ていた。
「本当だよ、本当。ただ、言っておくが命の保証は一切しないぞ。この件について、ワタシは――『ワタシたち』はキミらの命の責任を取らない」
「それほど危険なのかい」
質問してみれば、「そりゃそうさ」とクロエが言った。
「なんせ『どういうものなのか判明していない』んだからね。こいつはただ危険なことだけわかっているという代物なのさ。中へ入ると連絡さえ取れなくなる有様だ」
「だが帰ってきた者がいるんだろう」
「いるよ。ただ、その条件が判然としないのさ。画集、全二百五十九ページ――その『扉』とやらに辿り着いて、怪物に襲われながらも出て来られた者はまだいい。まだわかる」
「その他にもいるのかい?」
「いるよ。ただ、皆錯乱していて話にならなかったがね。最後のページを辿って出てきたと証言した者以外は、皆正気を失って病院で今も療養中だよ。ただ、何か大切なものを失ったようなことは口走っていたかな。尤も、そのおかげでこの画集のことがわかったんだが」
これが見つかった元々の理由は、古書店や図書館へ立ち寄った人間の一部が急に行方不明になったり入院したりしていると判明したからなんでね、とクロエは、黒いケースに、皺の目立ち始めている、皮の厚く、長い指を乗せた。
「『帰って来られた』一般人から情報収集をして記憶消去をした後、『死んでもいい人間』を何人か使って機械越しに読ませてみたりもしてみたが、現象は同様に発生した。残念ながらそいつらは帰って来ないか、同じように狂って出てきたよ」
ふうん、とアンテロは指先で己の顎を少し撫ぜた。九雀も何かを考えているようで、身を乗り出したまま、じっと画集を見ている。
そんな二人の前で淡々とクロエが続けた。
「だから少なくとも、現時点では、この画集において、中へ入って絶対に帰って来られると判明している条件は『最後のページに辿り着く』というそれだけなんだよ。それも、二十四時間以内に」
女の言葉に、ははあ、と九雀が、間の抜けた声を上げる。
「因みに、二十四時間という時間はどこから出てきたのであるか?」
「単に、この画集へ入ってから二十四時間以上経って帰って来られた人間がいない」
「では一応、二十四時間以上経っても出られる可能性もなくはないのであるな」
「やめた方がいいとは思うよ、ワタシは。大人しく二十四時間以内に帰ってくる努力をした方がいい」
帰って来られるものならばね、とクロエは――ガスマスク越しでもわかるほどはっきりと――笑った。その挑発に乗る形で、アンテロも足を組む。やっぱりあまり『仲良く』したい組織じゃあないな、などと思いながら。
「それで、怪物の詳細は? それくらいはわかってるんだろう?」
女が僅かに俯いたので、ガスマスクの向こうの瞳が見える。女の目は、灰がかった青色をしていた。目元や指から見るに、多少歳を取っているのだろう。何故ガスマスクをしているのかは知らないが。情報として優先順位が低いので、訊くことはなかった。
「……化けるのさ」
「化ける?」
「そう――何にだって化ける。人にだって、物にだって、それこそ暗闇の隙間にだって……だからこそ、逃げるのは至難の業なんだよ。正気で帰ってきた人間は全員そう言った」
「一体だけなのであるか?」
「多分ね」クロエが皮肉気な声で答える。「少なくとも同時に複数体が出現したという報告はないね。それと、最後の『扉』へ辿り着くまでは出て来ないようだ」
「討伐しようとはしなかったのかい?」
「しようとしたさ。だが、それなりに戦える五体満足の戦闘班を、完全武装で十人送って、帰ってきたのはたった一人の上半身だけだった」
「食われたのであるか?」
「単刀直入に訊くなあ……まあそうだ。何に食われたんだか知らないけれど、帰ってきた奴の下半身はどこにもなくなっていた。上半身だけでどうにか最後の扉を開けて帰ってきて、情報をワタシに渡してそのまま死んだのさ。頑張ってみたが……まあ、駄目だったね」
「成程……」
これほど強く警戒していて、画集に関わろうとするアンテロや九雀に拒否反応を示すのは部下が死んだからであるらしい。後悔と責任が怒りに転嫁していると言ったところか。
捨て駒の方については平然としていたように見えたが、部下について語る口調には感情が強く出ているように思えるのは、彼女の性格によるのだろうか。それとも単純に、少しずつ怒りが思い出されてきたのか。
「だから、ワタシは、この画集をキミらにあげてもいいが、命の保証はできない、と言うのさ――ワタシは部下の命を守ることさえできていないんだからね」
「ふうむ……」
九雀が体を起こして腕を組み、考え込むような仕草をした。
「そもそもね、『怪物を殺したところで画集が無力化できるかもわからない』んだよ」
誰も殺せていないんだからね、とクロエが言う。
「無力化できなかった場合は? 報酬はナシかい?」
「いや? 勿論帰って来られたのなら好きなだけ支払おう。『無力化できない』という情報に対する対価だ、キミらが『この画集に入って帰って来られるというのならば』、それは『それだけで意味がある』ことではあるんだよ」
「……」
アンテロは内心で首を傾げた。それならば、脅しのような言い回しで止める必要などないのではないだろうか。自分と九雀が画集へ入って帰って来られたならば、それだけで意味がある――であれば、万一自分たちが帰って来られなくとも、それは『猟兵でも内部からの破壊は難しい』という情報になるのであるから、組織としては多少のメリットになるはずだ。
(もしかして、心配してくれているのかな)
老婦人……と呼ぶには若いのだろうが、この女性は、自分たちが帰って来られなくなって死ぬことを、心配してくれているのかもしれない、とアンテロは思い当たる。
「クロエちゃんが心配してくれるのは有難いのであるが」
そんな考えを、先に形として女に伝えたのは九雀だった。
「これでもオレは、戦うことが義務でな。まあ専ら自分の気が向いた時にしか戦わぬが……一応、自分の命の責任を他人に取らせない程度の矜持はあるのであるよ」
「……キミから矜持という言葉が出てくるとはな。ただの変な仮面だと思っていた」
「フハハ、大体合っておるから否定も出来ん」
「だがまあ、そうじゃないよ。単に、自分の視界の中で他人が死んだら気分が悪いだろう」
なんだか自分のせいみたいに思うだろう、とクロエが僅かに、おそらく溜息をついた。
「……悪いけれど」
アンテロは笑う。マジックの種明かしをする子供のように。
「猟兵である限りそういう重傷で死ぬようなことはある程度回避可能だから安心して欲しい――まあ、画集に取り込まれたのなら話は別かもしれないけれどね」
特に俺は所詮仮体だし、と内心で付け足す。そこまで説明する義理はない。
「……ああ」
真の姿とかいうやつ、とクロエが自分の方を見た。
「……猟兵ってのは、体が半分千切れてもそれで元に戻るんだろうか?」
「さてね」
なったことがわからないな、とアンテロは肩を竦めて――
「もし結果がわかるようなことがあれば、教えよう」
――そんなことを嘯いたのだった。
(→続く)