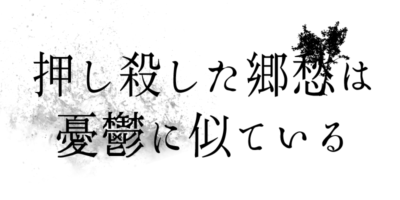小説リハビリの多分三月上旬くらいの話。青薔薇の話が少し出て来ます。
※名前ありのモブ職員に九雀が滅茶苦茶ひどい目に遭わされています。本当にひどい目に遭わされています。ご注意ください。また、少しグロテスクな描写を含みます。人が死にます。苦手な方はご注意ください。
死には遠い命を抱いて
「あのね、らお君。わたし、死体を埋めに行きたいんです」
だから手伝ってください。
女は――美潮香純は、ドローンで九雀を呼び出すなり、笑顔でそう言った。それを聞いた九雀が初めに何を考えたかと言えば、ただ一つであった。
絶対に、絶対に後でUDC組織に監督責任を問うてやる。
かくして、九雀は、女と共に死体遺棄を行うこととなったのである。
●
九雀が美潮香純と出会ったのは、UDC組織から「作戦が失敗し、現場に取り残された職員をどうしても自分たちだけでは回収出来ないから協力して欲しい」と依頼されて赴いた、冬の廃村だった。己の生活を保障しているUDC組織からの正式な仕事である以上、九雀に断る理由はなかったので、その出会いはある意味必然だったのだろうと思う。
はっきり言えば、然程容易な仕事ではなかった。その場で何が起こったのかを簡単に聞けば、何者かによって廃村に拉致されていた一般人を保護しようとしたものの、それが全員UDC怪物になった、とのことだった。その数、およそ四十余。言葉にすればそれだけだが、大惨事である。流石の九雀でさえも、聞いた直後は言葉を失い、数瞬の沈黙を挟んでから、呻く他なかったほどであった。グリモアによって予知された事件でもなく、殆ど偶然に発見されたもので、調査の結果、猟兵を呼ぶ必要はないとして未然に処理しようとし――UDCの戦闘チームが廃村へ踏み入った瞬間、一般人の中に潜んでいた邪教徒が、その場の全員を巻き込んでUDCオブジェクトを使用した。デコイだったわけである。結果、その場の一般人はすべてUDC怪物になり、戦闘チームは分断され――廃村は地獄絵図の戦場と化した。しかも、怪物に『なりきる』までにそれぞれ個体差があったのも悪かった。一般人か、怪物か。判断し損なって死ぬ職員がどうしても出てしまったのである。どれほど訓練しようと、培った倫理観を潰し切ることは出来ず、情に負けた者から死んでいった。ご丁寧に結界まで張られ、撤退すらできないまま現在に至る、とのことであった。更には、戦闘チームの一部もUDC怪物になっており、本当に手が付けられないと。
「教団の内通者がいたんです」作戦指揮をしていたという男は、感情がすべて抜け落ちたような顔で、そう言った。「当人も、あの廃村で既に死亡していますから、どこと通じていたのかも、すぐにはわかりません。調査結果も虚偽のものでした。この事態を収拾しないと、自分には死ぬことすら許されないのです」
「死んだら終わりであるよ」
九雀は武器の点検を終えてベルトに戻しながら返した。
「どうしても死なねばならぬと思うなら止めはせぬが、職員ちゃんが死んでも誰も戻って来んということは覚えておくとよいであるぞ」
そうですね、と答えた男は、それでも、凍り付いたような表情のままだった。
中から外へ出ることは出来ないが、外から中へ入ることは出来る。可能な限りのUDC職員を殺害しようとでも言うような構造の結界へ無闇に追加人員を送らなかったのは的確な判断だったのだろうと九雀は今でも思っている――無論、救いを求める無線に「無理だ」と答えるのは、酷なものであると理解した上で、そう思っている。
「それで、オレは結局どうしたらよいのであるか。正直、それほど発生しておるのであれば、グリモアで他の猟兵を呼んだ方がよいと思うのである。無論時間はかかるが、殲滅というのならば、おそらくそれが一番確実であるよ」
「いえ、いえ……それでは間に合わない」
葛籠雄さんには、まだ生きている職員を救って欲しいんです、と男は言った。結界が解除できて、私たちの方で用意した増援が、助けに向かえるようになるまで。それだけでいいんです。骨の髄から絞り出したような声音だった。最早手遅れではないか、とは、言わなかった。自分一人では共倒れになる可能性の方が高いようにも思っていたが、それも九雀は口にしなかった。優しさというよりは、ただ、面倒なことになるのが嫌だったのだ。だから九雀はただ一言、「左様か」とだけ答えて、黙ったのだった。
それに、依頼された仕事ならばやるだけだった。余程の無茶だと思ってはいたが、この仕事を蹴ることは禍根に繋がるとも理解していたので、断るという選択肢はなかったのである。
「結界の解除に、まだ時間がかかりますから……」
「どれくらいであるか」
「わかりません」
「……オレが怪物ちゃんたちを皆殺しにするのと、オレが戦闘不能になるのと、結界の解除ができるのと、職員ちゃんたちが全滅するのと……どれが一番早いかという話になりそうであるな……」
「そう、ですね」
「まあ構わんが……呼ぶ猟兵にオレを選んだ理由は? 言っておくが、オレは猟兵の中でも戦闘能力は低い方であるぞ」
「すぐ連絡がついて、手が空いていたのがあなただったというのもありますが」
あなたなら、こういう状況でも断る可能性が低いかと思いました。温度を失った黒い目が、九雀をじっと見ていた。
「それに、自分たちが死んでも――あなたは気に病んだりしないでしょう」
正直な男に、九雀は思わず笑ったものであった。話はそれで終わり、かくして踏み入った廃村は、話に違わぬ様相であった。血と臓物、それから肉片。その他汚物でめちゃくちゃになった村を、九雀は駆けた。然程強くないとは言え四十余のUDC怪物は殆ど残っており、窮地を助けたものの、既に致命傷を負っておりその場で死んだ職員もいたし、とっくに気が狂ってしまっていた者もいた。そうして軽く二ダース半はUDC怪物を殺し、途中で発狂した職員によって引き起こされた爆発に巻き込まれて多少の火傷を負ったりしながらも、どうにか片手の指より少し多いくらいの職員の正気と生存を確認し――最後に出会ったのが、当の美潮香純だったのである。
『それ』は、廃村の一番奥、神社跡地と思しき場所の、朽ちた境内に転がっていた。
――子供が乱暴に人の形へ切り取った、ピンク色の雑巾。
九雀が最初に思ったことは、それだった。
女の皮はぐずぐずに剥けて爛れ、全体的に平たく潰れていた。ピンク色に染められた髪は方々に広がり、ボディアーマーに覆われた体は大きくひしゃげ、手足に至っては二倍ほどの長さになるまで捻じられ放り出されていて、これまたピンクの液体が、下手くそに絞られた雑巾から溢れ出すように境内を染めていた。
暴れたい盛りの幼児と遊んだ人形でもここまでの有様にはならないだろうと九雀は思ったし、率直に、「嗚呼、死んでおるなあ」と思った。そうして周囲にUDC怪物もいなかったので、九雀は無視して通り過ぎようとして。
『待って待って待って、助けて、助けてくださぁい!』
凄まじいスピードで飛来してきた何かに、横腹を衝かれて吹っ飛んだのだった。
一瞬、完全に肉体の息が止まった。
受け身こそ取れたが、軽く二メートルは飛んで、火傷していた肉体の皮膚を思い切り石に削られて九雀は呻いた。ついでに言えば、敵だと思ったので、ワイヤーも投げた。手応えはなかったが。代わりに返ってきたのは、間の抜けた、合成音声だった。
『待ってぇ、お願いします、待って待ってぇ! これ壊されたらわたし、あなたとお話できなくなっちゃうぅ!』
「は?」
ひどく痛む腹を押さえながら立ち上がり、音の方を見遣れば、よくわからぬ――死体から零れる血と同じピンク色の、不格好な四足を備えた、拳大の塊がぴょんぴょんと跳ね回っていた。突撃してきたのはこれだろう、というのは、すぐにわかった。なぜ突撃されたのかはまるで理解できなかったが。
『こんなこともあろうかと! 用意していた! 私! 謹製! カエルちゃんです!』
「……は?」
頭が、理解を拒んでいた。ピンク色の髪に碌な思い出がない、と言うのを、何故か九雀はその時、ぼんやり考えていた。しかもメカニックだと? 最悪の組み合わせだ――九雀の記憶の空洞が、諦観と共にそう告げていた。トラウマとはこういうものだろうか、などと仮面は思っていた。
『可愛くないですか?』
およそ世間一般で言われる愛らしさからは色以外すべてかけ離れているのだろうと九雀でさえ感じる、その得体の知れない塊は、九雀の足元で、未だぴょんぴょんと跳ねていた。というか、その塊は、九雀の乏しい語彙で簡単に形容するのであれば、人間の脳に似ていた。デフォルメされ、小型化された脳に、獣のような四足が虫の如く生えているのだった。
「……」
『ね? ね? 可愛いですよね?』
そのままくたばれ。一瞬そんな言葉が頭をよぎったが、踏みとどまる。助けを求めている以上、このピンク色の雑巾はUDC職員なのだろう。刺激するのはよくない。続いた緊張のせいで錯乱しているのかもしれない。九雀はそう思った。
「そう……やも、しれぬな……」
なんとかそう答える。宥めるのは苦手だが、この場で最適な返答は肯定だろうと思ったのであった。
『はっ、いえそんなことはどうでもいいんですっ!』
「そのままくたばれ」
飲み込んだ言葉がストレートに出た。踵を返して他の生き残りを探しに行こうと駆けようとしたところで、雑巾曰くカエルちゃん、という塊が、再び九雀の横腹に突撃してきたので今度は避ける。
『待って、あの、助けて、頭だけでも、いえ、このカエルちゃんだけでも持って行って欲しいんです、まだデータ転送終わってなくって、このままだとわたし困るんです! この体が壊れちゃうのは構わないけど収集したデータが消えるのは嫌なんですぅ!』
「ならば最初からそう言わんかこの阿呆ッ!」
どうしてこの類の人間は、要件を話す前からわけのわからない話題へと脱線してしまうのだろうか。九雀には答えが出せそうにない永遠の謎であった。女の転がる場所が廃村の一番奥で、既に村の殆どの場所を見て回っており、ざっと他に助けが必要な職員がいないことを確認していたからこそ付き合っていただけで、これが道中での遭遇であったならば、九雀はとっくに見捨てていただろうと今でも思っているし、それが本当は正解だったのだろうと心底思っている。何故あの時、自分は女を見捨てなかったのだろう。疑問は尽きない。
大股で雑巾に近付き、半壊した頭部に纏わりつく髪の毛を掴む。よく見れば、女の体は、半分以上機械であった。成程、この体が壊れても構わないがデータは困る、というのは、そういったところに由来するようであった。
「それで、頭であるかッ? もぎ取ればよいのか!」
『やぁ、乱暴なのは嫌です、壊れちゃうぅ』
「このまま踏み潰して殺すぞ」
『乱暴過ぎます! らお君は比較的温厚なタイプだって聞いてたのにっ!』
「らっ……は!? オレのことか!?」
『そう、つづらおのらお。可愛いですよね』
「どっ――どうでもいいッ、否、貴様オレを知ッ、この――ッ、――あああッ! もうよい、このド阿呆ッ! それで!? オレはどうしたらよいのであるか!? 他に要救助者がおるやもしれんのである、早く指示しろッ!!」
『付け根のとこ、付け根のとこ押して引っ張って、外してくださいぃ』
「承知した!」
半ば本気で「こいつだけは放置して帰っても怒られないのではないか?」と考えながら、九雀は女の首の仕掛けを外して潰れた頭を抜き――すぐに地面へと放り出した。乱暴な扱いに騒ぎそうなピンク色の雑巾は、予想外に黙っていた。
尤も。
「……まあ、ここに集まってくれたのであれば、逆に他の職員ちゃんが助かっておる確率が上がるというものであるよな」
女の残骸と九雀を取り囲むように十体以上の怪物がいたのだから、それも当然だったのだろう。そこで騒ぐような者なら、最初からこんな場所に転がってはいまい。
『あ、わたし、今もう何もできないので……あと、もうデータ転送終わったので頭もカエルちゃんも必要なくなりました! ありがとうございました!』
「喋って歩く脳味噌になぞ、元より何の期待もしておらん。そして貴様は後で絶対に蹴り飛ばす、覚えておれ」
『のっ!? えっ!?』
のうみそ!?と騒ぎ始めた塊を放っておいて、九雀は投げ針を構え――背後からの一斉掃射で動きを止めた。無論、九雀を狙ったものではない。
結局、一番早かったのは、結界の解除であった。
そうしてどうにか惨事の始末をつけて、無意味に疲労した九雀は、指揮をしていた男から、女の名が美潮香純と言うことと、あの女の言う『データ』とやらが結界のものであり、あの女の転送したデータがなければここまで迅速に解除ができなかったので、助けてくれて本当に助かったと感謝をされ――宣言通り、女の『カエルちゃん』を、本気で蹴り飛ばした。ピンクの塊は綺麗な直線を描いて吹っ飛び、廃屋の壁を勢いよくぶち抜いて倒壊させた。壊れたかどうかは定かでない、そこまで九雀は確認しなかった。だが、瓦礫の下から例の合成音声で、『ストレス発散になったのなら幸いです!』と高らかに聞こえてきていたことを考えると、どうせ壊れてはいなかったのだろう。頑丈なものであった。
それが、美潮香純という女との出会いだった。
●
「らお君、元気ないですねぇ」
「何故オレは、香純ちゃんのドローンに気付いてしまったのであるかなあ……」
午前四時、朝靄にけぶる屋敷の一室にて、偶々その時間に目を覚ました九雀は、特にすることもなかったので、いつものように蝋燭をつけて本を読んでいたのである。と、そこで、窓の外を銀色の何かが飛行しているのを見つけ、普段の癖で無意識にそちらを確認した――それがいけなかった。その何かをはっきり視界に収めた瞬間、それが円盤型のUFOを模した香純のドローンであることに気付いたので、即座に無視しようとしたが時すでに遅く、顔を背けた瞬間、凄まじいビープ音で存在を主張してきたのだった。控えめに言って、UDC組織はこの女を自由にさせないで欲しい。本当に。切実に。倫理と常識をどこかへ投げ捨てた人間ほど性質が悪いものはないと、九雀は確かに『知っている』。だが、こんなところで、こんな形で再認識したくなかった。
いっそ屋敷の中に入ってきて正気を失ってくれればまだ対処のしようがあるというに、と思えども、美潮香純という女は、九雀が自分を苦手としていることを完全に理解していた。そして、屋敷のことも熟知していた。それ故にドローンを飛ばして九雀を呼んだのである。姑息であった。
「可及的速やかにオレを解放して欲しいのであるよ」
「駄目です。らお君はわたしと一緒に死体を埋めるんです」
「何故オレなのであるか……」
「そろそろ、サイボーグにした肉体のすばらしさを知って欲しくて」
「前から返事をしておるよな、オレはそう言ったことはせんと」
「何故? 痛みもなくなるし、いつでも取り換えられるようになるんですよ? 色も形も自由なんです!」
「興味がない。それに、そもそもこの肉体とオレが別個の存在である以上、合意もなく改造はできん」
「じゃあじゃあ、合意があればいいんですか? 脳波からイエスとノーを弾き出す装置、お貸ししますからぁ、ね? ね?」
「……」
屋敷の敷地を出て、何の変哲もない森の中を、女の後ろを三歩下がって歩く。なお、女は九雀の方を向いて、つまり後ろ向きに歩いている。何らかのセンサーがあるのか、転ぶ様子もぶつかる様子もない。薄いスカートが破れる様子すらない。未だ冷える三月の早朝に、汗をかく様子もなければ、吐く息が白くなるわけでもなかった。すべてが作り物の女は、絵画じみた生気のなさで、人間そのもののように振る舞っているのであった。ピンクの――女はストロベリーアッシュだと言った――緩い巻き毛が、ふわふわと揺れている。白いブラウスの、病院のような清潔さは、どうも不自然さを感じて好きになれなかった。
香純が、うっとりと指を組み合わせる。
「あー、でも、素敵です。らお君と一緒に死体を埋めに行けるなんて」
「……」
「ずっと、らお君もそうですけど、らお君のお知り合いの猟兵さんたちのファンだったんです、わたし!」
「あやつらの誰か一人にでも余計なことをしたら、オレは迷わずお前を殺すであるよ」
「やぁ! らお君、前から思ってましたけど、結構物騒ですよね」
「幻滅しろ。そして解放してくれ」
「しませぇん。というか、わたしはそうやって喋ってる時の方が、らお君の『ほんとう』っぽくて好きですねぇ」
「頼むから黙って欲しいのである……」
もう疲れた。スマートフォンの充電がなかったことを、ひいては屋敷に電気が通っていなかったことを、これほど恨めしく思ったことはない。何か発電機でも設置してもらおうか。そんなことを九雀は思った。UDC組織に連絡したい。今すぐ。この女を引き取ってくれ。あるいはこやつを殴り倒して、スマートフォンを奪い取って連絡するか。否、痛覚がない上、件の事件を経て、より頑丈なボディに換装したと自慢してきた――あの事件以来頻繁に、女から、九雀の屋敷を管理する支部の方へ、九雀宛のメールや国際郵便が届くのだ。何故律儀に読んで、時々は返事までしてやっているのだろうと自分でも思っている。支部長の老人なども、「こういうものは無視してもいいんですよ」と、珍しく芯から心配しているような顔で言っていた――この女のことだ、九雀程度の筋力では一瞬も黙らせることはできないだろう。最悪、顎に掌底の一撃でも食らったらこっちが――正確には肉体が――動かなくなる。
八方塞がりであった。
「うっふっふ、らお君はわたしを引き取ってくれって思ってるのだと推測しますがぁ、わたしは本日! 有給! なので! 皆来ません! わたしはただぁ、趣味の海外旅行をしてる! だけ! なのですよぉ! 海外旅行の先でぇ、うっかり、本当にうっかり、らお君のおうちの場所の近くだぁ、って? 気付いたので? お願いに来ただけなのです!」
「香純ちゃん。最早ストーカー寸前であるが、自覚はあるであろうか?」
「え? 最初からストーカーしてるつもりでしたけど?」
「開き直るなッ!」
誰か助けてくれ。さめざめと泣きたくなったが、仮面なのでどう足掻いても涙は出ないのであった。屋敷の扉に『美潮香純と死体を埋めに行く。戻りは未定。用がある者は後日に』と書いた貼り紙をしておいたので、誰かが気付いて止めに来てはくれぬものかと九雀は少しばかり思っていた。ビープ音に追い立てられて柄にもなく動転していたものだから、武器も持って来ていない。尤も、九雀は元々、冷静沈着な方というわけではないのだが。
「ところで、死体とは誰の死体であるか。誰ぞを殺したのならば、オレは自首をお勧めするであるな。埋めたところでどうせ見つかるものであるよ、嘘はいつか必ずばれる。何、刑務所に入っても、差し入れ……は、せぬが。健康に刑期を終えられるようにということくらいは片手間に祈ってやってもよいである」
「いい仮面ですねぇ、らお君。ストーカーのわたしのために祈ってくれるなんて……」
「前言撤回である。祈りさえ香純ちゃんには勿体なかったであるな」
「そう! わたしたちに祈りは不相応なのです!」
朝露に濡れた枯れ葉や小枝、羊歯などを蹴散らして、香純がくるくる踊る。帰りたい。
「一緒に埋めて欲しいのはぁ、たった一人、いいえ、『たった一人分』です」
「一人分?」
妙な言い回しである。首を傾げながら女の後ろをついて行けば、森の奥に、真っ赤な車が一台停まっていた。おそらく香純の車なのだろう。どうしてこんな場所まで入ってきているのだろうか、道もないのに。九雀はそんなことを思ったが、訊いて答えが返って来る、その一連のやり取りをするのが既に鬱陶しかったので、何も言わなかった。それに、考えてみれば、これくらい奥の方が、死体を埋めるなら丁度よいのやもしれぬ。そう自己完結し、九雀は香純が車へと駆け寄るのを歩いて追う。
「これです」
女が、車のトランクを開けた。
「……これは……」
何だ、と、訊くのはやはり――面倒だった。
女だった。年の頃は二十代の前半程度だろう。九雀が見る限り、だが。それが、透き通る素材のボックスに、バラバラにされて詰め込まれている。大小合わせて、二十は下るまい。ガラスなのかは知らない。ただ、それらの『部品』それぞれに、白く膨らんだ芋虫が、これまた大小生えている。種類は蛆から甲虫の幼虫と思しきものまで雑多であった。かと言って、女の死体からは腐臭など少しもせず、横でトランクを開ける女と同じく、ひどく作り物じみていた。質感は、蝋人形に近いのではないかと思う。芋虫たちは微動だにせず、肉を食んでいるわけでもないようだった。芋虫はおそらく、既に死んでいた。女の方も、きっと生きてはいまい。ボックスに収まった女の顔は、口元以外すべてを芋虫に覆われており、その人相は判別困難であった。
「これは、『わたし』です」
言われて、九雀は、香純の顔を見る。そう言われると、似ている――のだろうか。九雀にそれを判断することはできなかった。ボックスの女は黒い髪を雑に詰め込まれていて、綺麗に整えられた香純のそれとはまったく異なる。第一、バラバラ女の顔は、よくわからないのである。
九雀は――香純の顔を、覚えていない。
覚えられない、というのも確かにそうだったが、『見た覚えすらない』――ように、思う。もしかすると、本当に自分は、香純の顔を『知らない』のかもしれなかった。あの惨事の時、香純の顔は、すっかり潰れていた。それ以降、自分は、この女の顔を、一度だってきちんと見ただろうか。自分が知っているのは、メールと手紙だけではなかったか。
手首と芋虫の詰まったボックスを、ピンク色の女が手に取る。
「元々、美潮香純は、とある教団の司祭でした」
ぽん、と、お手玉をするように女が、手首を上に放る。回転する透明な立方体が、徐々に高くなり始めた日光を反射させて煌めいた。自分ではない誰かのことでも語っているかのように、女は、美潮香純を名乗ったはずの女は、淡々としている。
「まあ、司祭とは言いますが、八歳の女の子がね――小学二年生の、女の子が。お父さんとお母さんに、『今日から香純は、偉い人になるのよ』って言われて……よくわからないまま、諾々と、嫌々と、やってただけの――ええ、実質生贄だったんですよねぇ」
十二の頃には、もう体は駄目になっていました。女の掌に、手首が収まった。
「小学校には全然行ってません。それでも中学校の制服を夢見ていました。だけど高校は、絵空事でした。ましてや、大学に、成人式なんて」
女が、トランクに手首を放り投げる。硬質な音を立て、ボックスたちが衝撃に回った。
「それでも、月日は経つんですから、不思議なものです。生きたくもないのに、死ぬこともない。信じられます? 『これ』でも、こんな姿でも――美潮香純は生きているんですよ」
――まさか、生きていたのか。流石に些か驚いて、九雀は、ボックスの中に収まる白い女と虫の塊を見る。
「痛みもあるんです。あったんです。ずっと痛かったのに、すごくすごく痛かったのに、わたしから外へは何も伝えることができない……ぜんぶ見えてたのに。聞こえてたのに。口も指も、全然動かなくて。あんなにわたしを褒めてくれていた両親は、わたしのことを、もう褒めてくれていなかった。なんだかよくわからないかみさまを褒めるばかりで。だから、」
痛みだけが、わたしのともだちでした。女の言葉は静かだった。
「そうして気が付いたら、二十歳を過ぎていました。あんなに、来るかどうかもわからないと思っていた二十歳は、既に過ぎていたんです。わたしは、わたしの年齢を知らなかった。両親は、UDC怪物になって、組織に殺されていました。わたしの知らない間に。わたしが、組織の手で回収されて、この体を貰って、自分の年齢を、教えられている間に」
トランクの隅から、女が大きなシャベルを二本取り出し、九雀に差し出す。それを黙って受け取ると、仮面は土に突き立てた。
「……と、まあ、『わたし』こと、美潮香純の話はこれでおしまいです。やぁ、思い出話って難しいですねぇ。もっと簡単に、『これがわたしなんです! 驚きましたかぁ!?』くらいで済ませた方が良かったかなぁ、ううん、うん、そっちの方が良かったですね。もっとスマートな方が良かった。まぁいいです」
それじゃ埋めちゃいましょうか。そう言って、香純もまた土を掘るべくシャベルの先端を突き刺す。事件以来生身の肉を殆ど捨てたという女の膂力は、易々と地面に穴を穿った。
「――それで、」
女を見下ろしながら、九雀は一つ、問いかけをする。どれほど煩わしくとも、これだけは訊いておかなければならなかった――自分のために。
「それで何故、今更埋める気になったのであるか?」
「え?」女が手を止める。
「何故香純ちゃんは、『今』、『美潮香純』を、埋めようと思ったのであるか。その口振りであれば、組織に回収されたのは、ずっと前のことであろう」
「んん……まあそうです」
「では、何故、『今』なのであるか」
「……」
おそらく、初めて、女が言葉に詰まった。ブラウンの瞳を瞬かせて、「うーん」と唸る。
「んー。えっと。一応、前から、考えてはいたんですよぉ」
「ふむ」
「でも、んん、ええとぉ……『これ』。『これ』、『わたし』なのに、わたしじゃ触れないようにされてたんですよねぇ。隠されちゃっててぇ。この体があるからもう要らないのになー、って、ずっと思ってたんですけどぉ」
「……」
今度は九雀が黙る番だった。こやつ――どうやってそんな『自分』を回収したのだ。
「あの、大惨事だった、廃村のぉ、アレ。あったじゃないですかぁ」
「……あったであるな」
「あの村にぃ……あったんですよね。この、『わたし』が」
――武器を。
武器を――屋敷に、置いて来てしまったのは、失策だったのではないかと九雀は思った。
「UDC組織はぁ……こんなわたしを一つにしてくれましたし、わたしも、この痛くない、一纏めの体は気に入ってますけどぉ……やっぱり『要らないもの』がずっと残ってるのは、わたし、あんまり好きじゃないんですよねぇ」
それにわたし、『これ』、気に入ってないんです。女は、困ったように眉根を寄せて、ため息を吐いた。この女は、未だ息をしているのか、と九雀は頭の片隅で、少しだけそんなことを思った。彼女が肉体の何割を機械にしているのかは知らないが、殆ど生身を捨てたというのなら、呼吸もしなくていいように出来なかったのだろうか。仮面の知るウォーマシンは、おそらく皆呼吸をしていない。
そして、多分、仮面も。
「香純ちゃん」
「はぁい?」
「ああやってオレを足止めして……何をしておったのであるか」
女が、目を丸くして、それから、瞬きをした。
「やっぱり、らお君って、馬鹿じゃないんですよねぇ。愚かですけどぉ」
九雀はシャベルを握る手に力を込める。
「答え如何によっては、」「どうするって言うんですか。そんなによわっちくてぇ」
知ってるんですよ、らお君は武器がないと殆どユーベルコードが使えないって。女の言葉にあるのは、嘲りではなく、事実を口にする時の冷淡さだった。
「遠回り、独り善がり、エゴイスト。悪役にさえ為り損なった、無力な道化。それがあなたじゃないですか」
「散々に言うであるな」
「だってわたし、らお君のファンですから」
言って――女は、えへへ、と。
あまりにも、無邪気に笑った。
「――、」
息、など。
自分は息など、していないのに――仮面は、何故かひどく苦しくなって、シャベルの柄を更に強く握り締めた。女はと言えば、そんな九雀には目もくれず、子供のように、土へ刺したままのシャベルをぐりぐりと手のひらで弄んでいる。その拍子にベージュのショートブーツへ土がかかって、香純が足を軽く振った。
「って、如何にも悪人っぽくお答えしましたけど。実のところ、わたしはなんにもしてないんです、ほんとですよ? なぎちゃん……えと、柳みちるって言う女の子で。あの時、別の教団の密偵として動いてた子です。その子が、嘘の報告してるっていうのも途中で気付きましたけど、手出ししませんでしたもん」
ほんとに、『わたしは何もしなかった』んですよ。
女は、自分の言葉を微塵も疑っていないと言った表情で、拳を握り、力説していた。
「らお君についてはぁ、ちょっと想定外だったというか。悪いことしたなぁ、とは思ってます。ごめんなさい。殴っちゃったし。でも一応、『わたし』の捜索完了前に、あれ以上うろうろされてわたしのカエルちゃんズが見つかっちゃうと困るので――それに、折角らお君とお話できるチャンスだったし……えへへ。んん、えっと。とにかく、責められるようなことは何もしてないはずですっ! だって何もしてないんですからっ!」
「何も……であるか」
「ええ! わたしはただ、あの廃村で、騒ぎに乗じて心置きなく捜索できそうなタイミングを待ってただけなんです! ……まあ、わたしもぼろぼろにされちゃいましたがぁ。仕方ないですね。怪物強いんですもん……結界も中々解析できないしぃ……」
成程、『データ』に拘った理由はそこにもあったようだ。捜索のデータが消えるのは困る、嫌だ――簡単な理屈である。宝探しを中断させられそうになった子供の駄々。
「まあ、後でちゃんと回収できたので、別にいいんですけどねぇ」
「香純ちゃん。あの時、何人死んだか、知っておるか?」
意味などないとは理解していたが、質問してみる。女は、こてん、と首を傾げた。
「えっと。残ったのが……七人でしたっけ。あ、あの後病院で死んだ人が一人いましたね。じゃあ、十六人ですか」
二十二人で行ったはずなのでぇ、と女が言った。
「知っておったのか」
「引き算くらいできますよ! 何歳だと思ってるんですか! というかこれでもメカニックなんですからねっ」
「そうか」
そうか、と、もう一度九雀は呟いた。
「知っておるなら、オレから言えることは何もないであるよ。香純ちゃんに悪意があったわけでもないことはわかったであるしな」
「わかってもらえて何よりです!」
「早く埋めるであるぞ。うかうかしておると夜になる」
「はぁい!」
元気よく返事をして土を掘り始めた香純の横で、九雀もまた、シャベルを土に思い切り突き立てる。堅いな、と仮面は思った。それから、どうすべきか、と、思考を巡らせる。どうすべき――など。
どうにもならない。
どうする理由もない。
死んだら終わり。それだけだ。
死んでしまった以上、今更九雀が何を言ったところで、何をしたところで変わることなど何もない。過去は変わらない。
――UDC組織は知っているのだろうか。そんなことも考える。美潮香純が何を黙っていたか。何を回収したか。
存外知っていて――放っておいているのやもしれぬな、と九雀は思った。何しろこの女自体は『無害』である。子供だからだ。小学生で司祭になって、そのままこの芋虫の棺にいたのであれば、そこから成長していないだけで、悪意などない。真実、倫理と常識が欠如しているだけで――『性質が悪い』だけなのだ。
それに――九雀だって、自分の利益のために何かを見つけても黙ることくらいある。そんな自分と香純が、一体どう違うというのだろうか。今の仮面には、その違いをうまく説明することが出来ない。だから仮面は、彼女と自分は同じなのだろうと思う――利己的な沈黙を、自分も女も選択する権利がある。そう思うし、そうであるべきだと九雀は思っている。それを、きちんとした理屈もなく否定するのは好きではない。否定をするなら、その理由を説明できなければいけないのだ。少なくとも、九雀は、そうでなければ、『そう』したくない。
第一、香純が何をしていたとしても、そこに干渉するのは自分の仕事ではなかった。それを九雀は理解していた。彼女の行いが組織によって許されているというのであれば、それは自分に関係がないことなのである。
――いつだって、九雀は、すべてから離れた場所にいる。
「そう言えばぁ」
「うん?」
「あの、乙女ゲームの事件、あったじゃないですか」
「ああ、あったであるな」
女の墓穴を共に掘りながら、九雀は適当に返事をする。女とまともな会話をする気など、最早少しもなかった。ただ、返事をしないでいる方が面倒になると思ったから、返事をしただけであった。
「あのゲームの……主人公の女の子と、時々、話をするんです。あの事件を管理してる支部まで、休暇で出かけて……」
「左様か」
「ええ。名前の無い誰かだった……だけど今は確かに『何者か』であるあの子と、わたしは話をしています」
救われた、あの子と。
太陽はとっくに昇りきっていた。森の湿度と漏れ届く初春の陽光に、肉体が僅か汗ばむ。
「『自分』って、何なんでしょう」
「さてな」
「器が大事なんでしょうか。それとも、中身が大事なんでしょうか」
「それをオレに訊いて、答えられると思っておるのならば、とんだ見込み違いであるよ」
「安心してください、これに答えられるひとなんて、きっとどこにもいません」
だからみんな知りたがるんですけど、と香純が笑った、
「『わたし』は、『美潮香純』は……今、二人います。もしかすると、それ以上に。だって、わたしの体は、あの廃村で、一度ぐちゃぐちゃになって壊れたんですから」
「……」
「でも、『わたし』は、『美潮香純』であるはずなんです。……そう思ってるんです」
香純が、手を止める。機械の女と掘り続けた穴は、いつの間にか、それなりの深さになり始めていた。つられて、九雀も手を止める。
「だからこそ、わたしは、考えてしまうんですよぉ」
俯いた女の顔は、ピンク色の髪に隠れて、よく見えない。
「『わたし』は、『誰』なのかって」
わたしは、このわたしと、本当に同じなんでしょうか。女の、独り言にも似た疑問が、『美潮香純』のために穿たれた墓穴に落ちた。
「あのね、らお君。わたしは、UDC組織の技術でこの体から抽出された、記憶や人格――そう言ったものを、機械的に、まあ所々は魔術的に、『再現』したものなんです。簡単に言えば、ただのコピーです。わたしの脳味噌は、とっくに虫食いでしたからね。ほんとを言えば、全部を再現できているかさえ、わたしにはわからない。それをやったUDC組織にだって、わかってないんですよ。だって、他人の頭の中に真実何が入ってるかなんて、誰にもわからないんですから」
女は顔を上げない。
「それなら、『わたし』の正体は『美潮香純』じゃないのかもしれない。それなら、わたしは――わたしの今の状況は、『美潮香純』という女を、『美潮香純』だと思い込んでいる得体の知れない『なにか』が、殺そうとしてるってことになるんじゃないのかって」
九雀はただ、黙って女の言葉を聞いていた。
「ねえ、らお君」
地面を見つめる女が、縋るような声音で、呟いた。
「『わたし』は、『美潮香純』なんでしょうか?」
「……知るか」
吐き捨てるように答えれば、女がようやく、九雀の方へ顔を向けた。その表情が、あまりに、捨てられた子供のそれで――九雀はシャベルを再び動かし始める。
「本当にオレがその答えを知っていると思っておるなら、真の愚か者は香純ちゃんの方であるな。大体、オレはその質問に答える義理も義務もない」
「らお君……」
「ただ、」
いい加減、深さが出てきて掘りにくい。九雀は何も言わず穴の底に降りて、続きを掘る。女が、九雀を見ている気配がした。
――嗚呼。
「オレが知っておる『美潮香純』は、貴様しかおらん。それだけは確かであるな」
こんなことを、以前にも、言った――気がする。
だが、誰に。
「……」
女からの返事はなかった。だが、九雀にとっては、確かにそれが真実だった。というよりも、どうでもよかったのだ――相手の本質がどんなものか、など。そんなものに九雀は興味がない。九雀にとって重要なのは、相手が『何者であるか』ではなく、『何者であろうとしているか』である。何しろ前者はどうせ、どう足掻いたとて変えようのないものである。『何者であるか』を己の意思で変えられるなら、仮面も含めて、もっと簡単に、単純に、生きられているはずだ。きっと、誰も苦しまずに済んでいる。
皆、そう生まれついたのだ。それは、変えようがない事実である。
そう――仮面は、思っている。
「大体、最初から、香純ちゃん自身が言っておるのであるよな」
「え?」
「『他人の頭の中に真実何が入ってるかなんて、誰にもわからない』と」
九雀は、仮面は、元より察しが悪い。
心の機微などわからないし、何を望んでいるかもわからない。
それで、相手が何者かなど。
「わかるわけがないのであるよな」
水でも持って来たら良かったであるな、と九雀は思った。想定よりも肉体が汗をかいている、脱水は避けたい。
「オレはもっと簡単に物事を考えていたいであるよ。敵か味方か」
視界の外で、女がしゃがみ込む。何をしているのだろうか、とは思ったが、九雀は穴掘りを続ける。今更女の奇行に一々付き合うのは面倒だった。こちらは出来る限りさっさと埋めて帰りたいのだ。帰ったら風呂でも沸かすか。そんなことも考える。
「好きか嫌いか。楽しいか楽しくないか――」
バヂン!!
「――ッが」
けたたましい音が肉体の耳元で弾けて、首筋に、痛みとさえ認識できない衝撃が走った。混乱し、困惑する仮面を余所に、肉体の筋肉が一瞬のうちに硬直して、そのまま穴の底へと横倒しに倒れる。土が柔らかくて良かった、良くはないが。
一体何が起こった? 肉体が一切動かない。首さえ動かせないので、何が起こったのかもわからない。無論肉体から外れれば周囲を確認することもできるが、今この状況で行うのが正しい判断なのかどうか仮面にはわからなかった。
「……暫くは動けないはずですよ、らお君」
その言葉で、九雀は、今自分に――否、肉体に危害を加えたのが、香純であったと知る。何があった、とか、何の理由で、とか――そう言ったことは、最早考えの外である。
美潮香純が、この肉体に危害を加えた。
その事実に、仮面は声を荒げる。
「きッ、貴様……ッ!!」
女が、穴へ降りてくる。それから、硬直したままの肉体を担ぎ上げて、「えいっ」と可愛らしい掛け声と共に、ひと飛びで穴を出る。
「貴様、どういうつもりであるかッ!! 冗談にしては性質が悪いであるぞッ!!」
「んと……とりあえず、冗談ではないので、そこは安心してください!」
「何を!? 何を安心しろと!?」
「ぜんぶ、ですかねぇ?」
「何一つ安心できんッ!! 馬鹿か、お前は馬鹿か!?」
「ううん……やっぱり、馬鹿なんでしょうね」
わたし、ちゃんとしたやり方を知らないんです。地面に転がされ、肉体の腕を取られる。二の腕にゴムらしきバンドを巻かれて、女が注射器を取り出した。
「電気だけじゃ不安なので、薬も打っておきますね。ごめんなさい」
「……絶対に殺してやるからな……ッ!!」
「そんなに怒らないでくださいよぅ」
「これで怒らないやつはただのアホだッこの、この……ッ!!」
あまりの怒りに語彙が出て来なくて、仮面は言葉を失う。
油断、だったのだろうか。UDC組織の職員である以上、自分に危害を加えることはないと思っていた。信頼していた――のだろう。それが悪かったというのか? 自分の判断ミスだったというのか。
それとも、この女個人を、信じるべきではなかったのか。
――そう生まれついた、『生まれついてしまった』、この女を?
そう、生まれついたというそれだけで。
硬直していた肉体が、今度は弛緩して動かなくなる。こいつ、一体何を打ったのだ。指の一本も動かせなくて、仮面はただ、森の木々を見つめる。いくら自分のものとして動かせると言っても、動かすべき肉体そのものに異常が出ている現状ではどうしようもなかった。所詮仮面は仮面である。空を飛べるだけの仮面。
仮面はあまりに無力であった。
女の言葉通り。
しばらく、例のボックスを、墓穴に次々放り込んでいくような音が響いていた。それから、何かよくわからない機械で、それを穴の中でミキサーにかけるような音も。ガラスだかなんだか知らない素材と、肉と思しき物体がめちゃくちゃにかき回されていく音は、不穏で、不快であった。というか、こいつ、一人で全部やれるのではないか。まったくもって、最初から最後までふざけている。
自分はどうしたらいいのか。仮面は真剣に頭を働かせて、考える。肉体から外れて助けを呼びに行く。却下だ。自分がいないところで肉体が何をされるかを考えると恐怖しかない。否、自分がいたところでどうせ何の役にも立たないのだが。騒ぎ立てて意欲を削げたら良いが、まあ無理であろう。では、なけなしのコミュニケーション能力でどうにか説き伏せる。これも却下である。口八丁で切り抜けられる段階はとうに過ぎ、既に女は実力行使に移っている。ここでそれができるなら、今九雀はおそらくこんなことにはなっていない。
有効な打開策が見つからないまま、ついに穴を埋める音が聞こえなくなって、女が、動かない肉体の手足を、更に革らしき道具で拘束した。
「らお君」
整い過ぎた容貌の女が、九雀を覗き込む。その顔は、微笑みと呼ぶには泣きそうで、悲しげと呼ぶには歪み過ぎていた。
「わたしの――ともだちになってください」
――ピンク髪のメカニックには、二度と近付かん。
九雀は頭の中で、静かにそう決意した。たとえ既に遅くとも、次失敗しないようにするには、学習するしかないのだから。
次などあって欲しくはないが。
そうして仮面は、弛緩した肉体に被さったまま、トランクへ放り込まれたのであった。
(→続く)