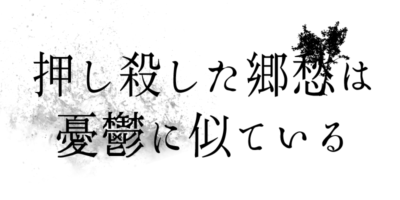過去話ふたつめ 命拾いする話
アンチ・アンチ・ヒーロー(ノット・ヒーロー)2
後悔するのは早かった。
確かに、拾われて、車に乗せてもらったところまでは良かった。だが、どこかの建物についた男が、面白いものを拾ったと言って、知らない女に向けて自分を上下に思い切り振り回した時、自分が生物扱いされていないことに気付いた。次に、何かやたら硬い金属のクリップに挟まれて――素直に痛かったが訴えは無視された――吊るされ、やたら温度の高いドライヤーで乾かされた時、己の前途の多難を知った。最後に、これまた堅そうな机に何度も叩きつけられ、その音で乾いたことを確認された時、なんだか色々と諦めた。そして、後悔した。やはり、自分の直感を信じるべきだったのだと。しかし後にするから後悔なのであって、つい数時間前の自分を責めようが、現実は変わらなかった。それに、雨ざらしで飢え死ぬのと、多少乱暴な扱いを受けても生きていくことの、どちらが良いか。そんなもの、考えるまでもない。だから名前も忘れた彼は、諦観と共に己の境遇を受け容れ――
「――やめろ! それだけは本当にやめろ!!」
今、絶叫していた。最早目の前の男に払う敬意などない。こんな狂人に、そんなもの払ってたまるものか。体はがっちりと鋼の小さな爪で台座に固定され、目の前には回転する小型ノコギリ。ギャアアアアアア、と、音を立てて構えられた刃が怖い。なぜ自分はこんな目に遭っているのだ? 俺が何をしたんだ? 生きながら回転ノコギリで真っ二つにされるようなことを、かつての俺がしたというのか。それは一体どんな罪だと言うのだ。
「死ぬ!! 死ぬから!! 俺は生き物なんだぞこう見えて!!」
「死ぬかどうかはわからないじゃないか。どんな調査も検査も、君が木製だということを示している。だから、真っ二つになっても、大丈夫だと俺は思うがね」
「思うで真っ二つにするな!! 本当に!! 死ぬって言ってんだろうが!?」
「縦に割ってみようと思うんだが、この場合、意識はどちらに宿るのだろう? 分裂するのだろうか? 双頭プラナリアの自意識は、どちらがオリジナルなのだろう? 我々にオリジナルというものは、存在するのだろうか?」
「知るかァッ!!」
声が裏返る。どうにか逃げられないかと体を動かすが、自分の身が削れそうになるばかりであった。この狂人をどうしたら止められるのか、皆目見当がつかない。どうする。死ぬ、本当に死ぬ。死因、回転ノコギリ。嫌だ、嫌すぎる。そんな死に方をするために生まれてきたわけではない、決して。そのはずだ。そのはずであって欲しい。ギャアアアアア。ノコギリの音が近い。自分が冷や汗を流すことができたなら、もうこの台座は自分の汗で散々に濡れていたことであろう。
「だッ大体なんで俺を真っ二つにしようとするんだ!!」
「うん? 面白そうだから」
男の表情は変わらない。穏やかなものである。そこに、狂気の匂いはない――だからこそ狂っているのだ。人懐っこそうな笑顔で、人好きのする優しげな声で、彼は回転ノコギリを構えているのである。こんなの説得できるわけがないだろうが。あばよ知らない世界。俺は死ぬ。そんな覚悟すら決めつつあった仮面を救ったのは、一本の電話であった。
「でっ、でっでっで電話だぞッ! 出なくていいのか!?」
「ああ。そうだな。出なくちゃいけない」
男がノコギリのスイッチを切って、置いた。だがまだ助かっていない。電話が終われば、間違いなく男は自分を再び真っ二つにしようとするだろう。どうしたらよいのか。考えろ、死ぬ気で考えろ。いや、死ぬから考えろ。はっきり言って、考えるのは苦手だ。何をどうしたらどうなるだとか、何が一番いいのかだとか、そういうことを考えたって、どうせ失敗する時は失敗するからだ。だから彼は、考えるのが苦手だ。誰かに頼れるなら、そっちの方がいい。失敗したって自分のせいじゃないし、責められたって、ごめんなさいと言えばそれで済む。だって、自分が考えたことではないのだから。彼の、多分良心だとか呼ばれるものは少しも痛まない。操り人形を怒る者は愚かである。何も考えず笑っていられるのが、彼は一番の幸せだと思っている――『生後』数時間の今の彼ですらそう思っているのだから、おそらくかつての自分もまた、そう思っていたのであろう。多分、生来そういう性格なのだ。
それでも今はそんなことを言っている場合ではない。ここは男のオフィスに併設された私室で、鍵がかかっていて、防音の実験室のようなものだった。だから自分の代わりに考えてくれる者はいないし、庇ってくれる者もいない。つまり己に、己の命がかかっている。
「そうか。わかった。それなら、九番は一度収容しておこうか。ああ。その状態ではもう仕事には出せないから。他のことに使うとするよ」
それでは。男が受話器を戻す。時間がない、ノコギリが回る。地獄はもう目前だ。
「玩具で遊んでいる時に仕事の話と言うのは嫌なものだね。それも、貴重な知能ある玩具なのに。『私』とは何なのか。我々の命題だと思わないかい? 二つになった君がどうなるのか、『完全なる一つ』でなければ動かないのか……中に何が入っているのか。俺は君の中身が見てみたいんだ。それに、さっき食べさせたツナサンドが、君のどこに入っているかも気になる。どう食べたかもわからないし、どう調べても、君の中にツナサンドがないんだ。つい五分前に食べたツナサンドがだ! 君はどうやって栄養を吸収しているんだ? 君の『飢え』とは、俺たちの『飢え』と同一なのか? 君は『何』なんだ?」
興奮しているのか、男は僅かに早口だ。ジュィン!と額すれすれをノコギリが掠めて、ヒィ、と仮面は悲鳴を上げた。
「そッ――それで真っ二つにするのか!? 玩具が一つ減るんだぞ!? 真っ二つにするにしても今じゃなくていいんじゃないのかッ!? 死なない程度なら言うこと聞くぞ俺は!!」
彼がそう口にしたのは、完全に単なる偶然、苦し紛れであった。正直に言ってしまえば、既に半ば死を覚悟していたし、最期の怨み言だって考えつつあった。辞世の句は少し彼には荷が重かったので、もし生まれ変わったら詠みたいものだなと思っていた。
だから。
「……なるほど」
男がノコギリのスイッチを切ったのは、彼にとって、青天の霹靂と言っても過言ではないことであった。
「それは一理ある」
言うことを聞いてくれると言うのなら、それも嬉しいことだ。そんなことを男は言った。
助かった――のだろうか。ノコギリを片付ける男を見る限り、助かったと思って良いと思うのだが、この男はどう考えても、自分の理解の埒外にある狂人である。となると、気は抜けなかった。そもそも、まだ自分は台座に固定されたままである。男が片付けに立ち去った今、彼に見えるのは明るい照明と天井ばかりだ。男は何かごそごそとしているようで、音が聞こえてくる。そう言えば、未だに自分は男の名前を知らない。知りたくもないが。
逃げたい。それが今の彼の切なる願いであった。
しかし現実はそれを許してくれなかった。残酷過ぎるじゃないか。柄にもなく泣きたいような気持ちになった。涙なんて出ないのだけれど。
「そうだな、まずはこれから試してみよう」
知能があればオブジェクトにも特殊能力は備わるのだろうか。オブジェクト。完全に生命体扱いされていない。男が帰ってくる。手には、何か、八面体の機械が握られている。
「これも元は拾い物なんだけれどね。制御できるよう、俺がカバーを付けたんだ」
ここをこうすると、面白いことが起きる。男が言って、がちん、と、八面体を捻った。
――そこから先のことを、どう表現すればよいのか。頭がおかしくなりそうな謎の知識であるとか、全身をズタズタにされそうな痛みであるとか、ありきたりだが耐え難い、素晴らしくも忌々しい、暴虐のオンパレード。そう、暴虐だった。拷問ですらない。目が回りそうな目的のない暴虐。殺してくれ!と何度叫んだのだったか。もう覚えていない。
一通りのことが終わった後、彼がすっかり男を苦手としていたのも――無理からぬことだと理解して欲しい。彼は、そう思っている。
(→続く)