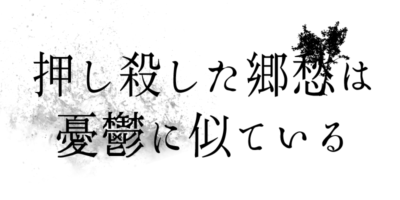過去話みっつめ ともだちをつくりにいく話
アンチ・アンチ・ヒーロー(ノット・ヒーロー)3
「……あまりに役立たず。無能の極みだ」
「人のことをあれだけ散々に扱っておいて、その言い草は刃傷沙汰だぞ」
「だが、本当のことじゃないか。俺はもっと……もっとこう、君には期待していたんだ」
「お前が勝手に期待しただけだろ」
「やはりオブジェクトにユーベルコードは宿らないのかなぁ……」
ため息を吐く男――あれから二週間以上が経ったが、やはり仮面は未だに彼の名前を知らなかった。勿論自分の名前も――が、デスクに肘をついた。そのまま、唇を尖らせて、文鎮代わりに置いていたらしい球状の何かを手に取ると、人差し指の先で、くるくると回し始める。それを仮面は、机の上に放り出されたまま眺めていた。
「ああ、でも、なんだかあれだな」
「どれだ。指示語で喋るんじゃねえ」
「あ――悪い、どうも最近、時々頭の中がおかしくなって。言葉が出てこなくなるんだ」
「お前の頭がおかしいのは前からでは?」
まともな感性と精神を持つ人間は普通、初対面の存在を、たとえオブジェクトと認識していたとしても、突然回転ノコギリで真っ二つにしようとはしない。そのはずだ。もしそんなことをする者が多い世界だと言うのなら、俺はいよいよ自死を考える。そんな狂人だらけの世界でこの先を生きていけるわけがない。
「まあ、それはそうだけど」男が、回る球に目をやった。「……そうか。前からだったな」
俺はあんまり変わっていないのかも。そんなことを言って、男が、球を回すスピードを上げる。台座に支えられた、地球儀にも似るそれは、男の指の上で、安定して回転していた。
「……そうだな、前より、口調がちょっと子供っぽくなったか?」
「そうかな? そうだっけ。そうかもしれない」
でもあんまり、『俺』には関係ないな。男がそんなことを言う。
「まあいい。それで、そう、君が、職員から驚かれていないなという話だ」
「ああ……」
そう言われればそうだ。ここに連れて来られた直後など、振り回されて悲鳴を上げた自分に、女――後で秘書だと聞いた――がひどく驚いていたのを覚えている。それなのに、あのわけのわからない暴虐の後は、なんだか『一個人』として扱われているような気がしていた。だからてっきり、この男が何か説明をしたのだと思っていたのだが。
「何もしてないのか?」
「してないね。何だったら、俺は君を、未だに壁の飾りか何かだと思っている」
この野郎、頑なに俺の部屋を用意したがらないと思ったら、言うに事欠いて壁飾りとは。宙を飛んで体当たりをしようかとも思ったが、一週間前にそれをやった際、本気の拳で叩き落とされて大変痛い思いをしたので、やめておいた。代わりに、「せめて全自動話し相手とかでいいから認識を格上げしといてくれ」とだけ言う。我ながら臆病なことだとは思うが、『これ』相手に余計な手を出せば、ひどい目に遭うのは自分である。頭に残る回転ノコギリの音で三日魘され、四日目に睡眠薬を貰い、五日目は副作用で丸一日意識をなくした。六日目に起きて男に「失敗だったかぁ」と言われ、動けるようになった七日目に体当たりを試み――叩き落とされて一週間が終わった。そういうわけで、仮面はもう、男に対してあまり多くのことを望まないようにしている。
と、不意に、パリ、と、回転する球体から静電気が弾けるような音がしたような気がして、仮面は体を起こした。だが、男は平然と回転させ続けている。聞き違いか?と内心で訝しみつつ、机の上にまた横たわる。男が素知らぬ顔ということは、問題ないのだろう。二週間程度の付き合いだが、男が己の持ち物で失敗したところは見たことがない。
「もしかして、それが君のユーベルコードなのかな」
「誰からも不審に思われない、とかか?」
「そう。空飛ぶ仮面であったとしても、違和感を覚えないとか」
「随分と限定的ってか、使い道がないな……」
「そうか? 使い方によっては使えそうだけれど」
でも、いつから君が『違和感を抱かれていなかったのか』が正確にわからないのだよな。男は拗ねたように、球をまた指で弾く。
「いつから? 二週間前からじゃないのか」
「どうだろう。君が最初に見た彼女、いるだろう」
「ああ、あの」
「あの子は、『急に叫んだから驚いた』と言っただけだった」
それはつまり――『仮面が叫んだから驚いた』わけではないのか。
「……じゃあ、俺はやっぱり」
「ユーベルコードが発現しているかわからないね」
だから無能と言っているんだ。男が回る球体から、バヂン!と、閃光と衝撃が走って、仮面は僅かに跳び上がる。いやこれ絶対気のせいじゃないだろ。
「な、何やってんだお前!?」
「うん? 球を回している。手持ち無沙汰だから」
「そうじゃねえんだよ!! それは『何』だ!!」
「これか。よく聞いてくれたね。回転速度が一定を超えると、周囲半径三十メートルくらいに電撃を放つ――」「止めろ今すぐ!!」
男の言葉を遮って、仮面は叫んだ。この野郎、またわけのわからないことをしやがって。全部が全部理解不能なんだよ! 部屋どころかフロアまで焼けるだろそれ!? 仮面がそうまくしたてると、男は、「説明は最後まで聞くものだ」と言いながら、渋々――本当に絵に描いたような渋い顔で、球の回転を止めた。
「この部屋は多少ユーベルコードで遊んでもいいように作ってあるから、そう目くじらを立てなくてもいいじゃあないか。軽い模擬戦闘くらいは出来るんだ、ここは」
「俺が死ぬとは思わないのかお前? まさか俺は死んでもいいと?」
「今のところ、君に利用価値はあまりないからね。正直に言うと、死んでもいいかな」
こいつハッキリ言いやがったな。利用価値ってなんだ、そんなもんが全存在にあると思ったら大間違いなんだぞ。価値がなくても生きていくんだ、普通は。つーかそんなもんを文鎮代わりにすんじゃねえ。言いたいことは色々あったが、結局仮面は何も言わなかった。言っても無駄なことは、嫌と言うほど知っている。
「何やら文句がありそうだ」
「ないと思ってるのがすげえよ。尊敬する」
「褒められてしまった」
「褒めてはいない」
「知ってるよ。全部冗談だ。君が死んだら俺は悲しい」
「もう少し悲しそうに言ってくれねえと、流石に信憑性がゼロだぞお前……」
疲れるなあ、こいつと話すの。他のやつを担当にしてくれないかな、と仮面は思った。だが、この男が自分を気に入っているらしいということも知っていたので、多分無理なんだろうな、と、この二週間で何度も繰り返し出した結論を、また頭の中で考える。何しろ、どこへ行くにも、男は仮面を連れて行くのだ。ここへやってきてから、男と別れて行動した時間は、眠っている時を除けば、一時間にも満たないはずだ。尤も、男と一緒にいる時はいつも、彼が持つボストンバッグの中なのだけれど。
「――そう言えば、何か特殊能力はないのか?」
「特殊能力?」
また変なことを言い始める。
「そう。いや何、確認だよ。何かそれらしきものが現れた時、元から持っていた力でした、じゃ拍子抜けだろう」
「特殊能力ねえ……」
そう言われても、何が特殊なのか、仮面にはよくわからない。自分は見ての通り、自力で飛んでうろつけるが、それも男には特殊と言われてしまうし。ふーむ、とひとしきり考えてみて、仮面は、一つだけ思いつく。
「そう言えば、他人に仮面として装着させることで、俺のものとして動かせ、ルッ!?」
突然勢いよく掴まれて、声が裏返った。
「お前……ッ! 予備動作をもっとわかりやすくしろ! 毎回怖いんだよ!」
「まだそんなことを言ってるのか。いい加減慣れて欲しいね」
時は金也、思い立ったが吉日さ。男が立ち上がり、実験室を出ていく。その足取りは急いているようにも思えたが、いつもこんな調子であるようにも思えて、仮面には彼が何を考えているのか、推し量ることはできなかった。
「何だ? 俺がなんかしたか? 謝るから火炎放射器に晒すのはもうやめてくれ頼む」
「そんなことあったかな」
こいつ、俺のトラウマベスト3に入る出来事を、さらっと忘れてやがるだと。一瞬だけ強い怒りがこみ上げたが、いつものことなので、やはり仮面は諦めた。これに世界の常識とか良識とかそういうものを求めても無駄なのだ。男が仮面を強く掴んだまま、エレベーターに乗り込む。どうやら、目的地は地階であるらしい。地階ってなんだっけ。駐車場だったか。何かを回収しに行ったり誰かと取引したりする作業に連れて行かれることが多かったが、その時は毎回、鞄へ雑に詰め込まれて持ち運ばれていたから、実はよく知らないのだ。
……そう言えば、俺はこの男が何の仕事をしているのかもよく知らないな。
社長代理とかミスターとか何か色々呼ばれているのは鞄越しに聞いているが。社長代理って、これが代理の会社とか、早晩潰れてしまうのでは。明らかに正気じゃないぞこの男。ポン、と軽い音がして、エレベーターが開く。やはり、駐車場だ。男が、ジーンズのポケットから、何かキャラクターのストラップがついたキーを取り出す。
「さっきのことは謝るよ」
「……。……ン? あ!? 謝る!?」
信じられない言葉に理解が追い付かない。何を。いやこれまでの所業をまず謝れ。話はそれからだぞお前。
「君のおかげで、とても面白いことを思いついた」
「面白いこと?」
「ああ」
ピッと電子音と共に男が車のロックを外して、仮面を助手席に放り込む。ドアにぶつかることもない完璧なコントロールで座席に落ちた仮面は、運転席に男が乗り込むのを見ながら、椅子の背へ凭れるように体を起こした。
「ここしばらく、廃棄処分を検討していた者がいてね」
「はあ」廃棄処分って何だろうなあ。仮面は呑気に、そんなことを思った。いつも鞄の中だから、男の実験室以外を見たのは久しぶりだ。
「ああいや、まず、君が他人の体を動かせる条件を聞きたい」
「条件?」
「あるんだろ。条件もなく他人を勝手に乗っ取れる、そんな都合のいい能力なんて、ないと俺は思っているよ」
それに、出来るんなら、君はとっくにやろうと試みているだろうしね。俺に対して。エンジンをかけ、男が車を出す。以前、運転手は雇わないのかと聞いたことがある――俺が運転する方が上手い。それに車を走らせるのが好きなんだ。男はそう答えたと思う。
「条件っていうか……心を通わせると出来るようになるな」
「そうか。それは友情ってことでいいのかい」
「友情以外でも、なんでもいいんじゃないか。でも俺、やったことないからな……」
やってるやつを見たことはあるが。――どこで。殆ど真っ白な記憶は、相変わらず埋まる気配を見せない。それなのになんだか、もうここでの滅茶苦茶な生活に慣れてしまった。車の窓から見える青空は、とても綺麗だ。
「そうか! 面白いな――とても面白い」
それ故に価値がある。男は笑いながら、小さな車を走らせる。派手な車は好きだが、好きな服装と似合わないからあまり使わないのだと言っていたか。
「テンション上がってるとこ悪いが、何のことやらわかんねえんだよな、俺は」
「うん? 簡単なことだよ」
一人、友達になって欲しい子がいるんだ。
赤信号で止まりながら、男はそう言って笑った。
(→続く)