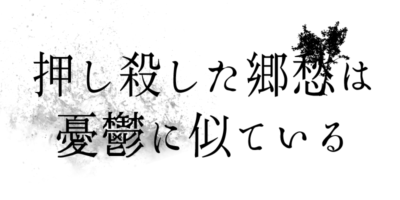過去話むっつめ 冗談じゃない話
アンチ・アンチ・ヒーロー(ノット・ヒーロー)6
えへへぇ、とまた馬鹿みたいな笑顔を浮かべて自分を見た青年に、あー、と仮面は溜息めいた声を漏らした。そこにあったのは、めんどくせえなぁという思いである。いや、これこそが彼の目的に近いはずだとは理解できているのだが――それにしても、面倒なものは面倒なのだ。
懐かれている。
その事実に気付いたのは、図鑑を読んで聞かせてやり、絵本を二冊ほど更に読み、何か薄らくたびれた、襤褸よりはマシだなと言えるような布を抱き締めてうつらうつらし始めた青年をベッドに寝かせて毛布をかけ、彼が眠りに落ちたのを確認してから自分も眠る、というのを二日分繰り返して迎えた、三日目の昼のことだった。起きるなり、青年はまず仮面を探した――らしい。らしい、というのは、その時偶々、仮面はあの男に呼び出されて進捗報告をしており、その場に居なかったからだった。三日目で進捗報告もないだろと思いながら適当に話をして帰った自分が見たのは、玩具箱をひっくり返したみたいに惨憺たる有様となった部屋と、べそをかきながら「いなくなっちゃった」と布を握り締めて床に寝転がる青年の姿だった。
正直、ヒいた。
実年齢が伴っているなら、まあうぜえなで済む。だが十九歳だ。図体のでかい、十九歳のガキが、床で縮こまってべそべそと泣いているのは、はっきり言って、いっそ恐怖だった。なんせ六フィートを超えている。男に聞いたので間違いない。身長だけなら男よりこの青年の方が少しばかり高いくらいなのだ。
冗談じゃない、と思った。相手との関係というのは、どんなものであっても、対等であるからこそ初めて成り立つものではないかと仮面は考えている。誰しも足を踏み入れてはいけない領域がある、それをお互い察して、不可侵のところを維持しながら、何となく上っ面で楽しく過ごすようなものが、仮面の知っている円満な『人間』関係だ。それが、これにできるのか。多分無理だろうと仮面は思った。である以上、友達になれと言われたけれど、最早やれるとは到底思えなかった。
子供の扱いを、仮面は、自分が想定していた以上に知らなかった。ベビーシッターって凄すぎねえ? これから見る目変わるな。そんなことも思ったりした。
仮面は早くも、引き受けたことを後悔し始めていた。なお、仮面と一緒に部屋へやってきた男は、部屋を見るなり表情を失くし、それからすぐに困ったような笑顔を取り繕うと、青年に仮面を返した。青年は喜び、男に感謝を述べ、それからすぐに部屋を片付けた。片付けは、ひどく手際が良かった――十九歳という年齢に似つかわしく。その横顔に子供の幼さはなく、大人の理知があった。くしゃくしゃにして床へ落としたシーツの端を、きっちり合わせて正方形に畳むその姿は、実態を知らなければ、単なる一人の青年のものでしかなかった。
だから、仮面は男に問うたのだ。
あれは本当に壊れているのかと。
男の返答は、疲れたような肯定だった。
(……あいつが肯定するなら、そうなんだろうなあ……)
多分――万策尽きたのだ。でなければ、自分にこんな仕事など頼むまい。あの男のあれは後悔なのかな、とぼんやり思ったところで、オレンジ色の髪を短く切った青年が、赤茶色の目をきらきら瞬かせながら、また分厚い本を仮面に見せる。世界の毒草図鑑。こいつ変な本好きだな。こないだは世界の怪物図鑑だった気がする。
「ずかん、読んで」
「あのなぁ、お前ほんとはちゃんと読めるだろ?」
あの男曰く、元々はそれなりに賢い青年であったとのことである。それがどの程度のものを指すのかは知らないが、少なくとも文字が読めないわけはあるまい。
「自分で読めよ。俺だって読むの疲れないわけじゃないんだぜ」
言えば、んぅ、と青年が拗ねたように唇を尖らせた。
「ちょっとは読める」
「ほらな」
「でも、むずかしいのはわかんない」
「難しいのを自分で勉強して読めるようになるんだよ。じゃねえと身につかねえぞ」
まあ俺、まともに勉強したことねえけど。そういや、この世界の言葉って俺の元居た世界と同じなんかね。普通に会話できるし、文字も読めるが。
(……ラッキーだと思っとこう)
これで言葉が通じなかったら、初日で真っ二つになって終わっていたわけであるし。これは幸運に類していいものだ。そのはずである。
「べんきょう、ねぇ、あのね、オレ、昔のオレの本とか見るんだけどね」
「おう」
「むずかしすぎて全然わかんないの。あんな字も、書けない。あれは今のオレのものじゃないよ。でも、しょちょうはオレのことを、前のオレと同じって言うの。あれが、『オレ』なんだよって」
「お、おう……」
もしかして本人に結構説明してるのか、あいつ? それは少し残酷なんじゃあないのか。お前は『元の誰か』が壊れた結果なのだと幼子に突き付けるなんてこと、流石の自分もやろうとは思わないのだが。仮面は不安になりながら、青年の話を聞く。
「最初はね、元に戻してあげるって言ってたの。でも、いつからかな? よくおぼえてないんだけど。どうしても元に戻せないってわかったから、オレはもう、オレのままでいいよって言って。でもね、なんだかすごく、笑ってるんだけど、かなしそうでね……」
「そ……そうか」
おいおいおい、お前が何しようと勝手だが、ガキ泣かせんなよなあ! それはどうかと思うぜ、所長さんよ。泣きそうになっている青年を持て余しながら、仮面は声に出さず男を非難する。男は元に戻すつもりだったから説明したのかもしれないが、少なくとも、状況が確定するまでは説明すべきではなかった。あるいは、男も焦っていたのか。あの男が、焦るところなど想像もつかないけれど。そもそも、男は廃棄処分を検討していたはずだ。その程度の存在が壊れたところで、対処を間違えるほど焦るのだろうか。ああだが――
(俺は、あの男の何を知ってるわけでもねえな)
そう思えば、何となく一切が冷えて、静かになったような心地がした。自分が知らないところで、あの男は何かを考え、そうすることを選んだのだろう。そしてそれは、仮面が考えることではない。理解すべきことでもない。『他人の踏み入られたくない領域には入らない』。それが、最適だ。勝手な推測などしない。それが見えたら、ただ思考を止めて回れ右。だから仮面は、泣きかけの青年に、「それで?」とできるだけ柔らかく声をかける。
「前のお前と今のお前は、違うって言いたいのか?」
「そう。でもさ、前のオレと今のオレが違うなら、オレは、一体誰なの?」
「そりゃあ、『九番』だろ。俺はお前の本名知らねえからそうとしか呼べないがよ」
「でも、」
「ばーか。何難しく考えてんだ。お前は誰だ? お前は今、自分を誰だと思ってる?」
「んと……」
「本名は要らねーぞ。俺は名前ってのが嫌いなんだ。忘れても覚えてもめんどくせえ、碌なもんじゃねえよ」
「じゃあ、『九番』」
「それならそれでいいじゃねえか。つうか、俺は元のお前を知らねえからな。俺にとっては、お前が唯一の『九番』だよ。安心しな」
言ってやれば、青年が、目をぱちくりとさせて、それから、また「えへへ」と笑った。
――こっちこそ、笑っちまうぜ。
(責任取る気がねえからこんなこと言えんだよな、結局)
それが、仮面にはわかっていた。くだらねえ、と思った。くだらねえ、冗談じゃねえ――本当に、冗談じゃ。
(……冗談でこんなことやってられるか)
進捗を聞かれて、仮面が答えた後。男は、良ければ一つ簡単な仕事をしてもらいたいなと言った。何かしら運ぶだけの仕事だと言う。能力的には支障がないけれど、集中力がまったくないので、一緒に行って軌道修正してやって欲しいとのことだった。
死ぬかもしれないから、気を付けてくれよ。
言いながら、男は、笑っていた。何の思考も読めないそれに、自分は何も言えなかった。
マジで安請け合いなんかするもんじゃない。
仮面は、つくづくそう思ったのであった。
(→続く)