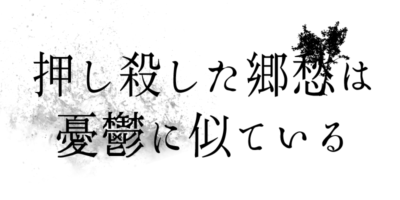おそらく五月くらいの話
よく晴れた初夏の話
葛籠雄九雀は――葛籠雄九雀と己を称している仮面は、いつものように、肉体へ被さった状態で目を覚ました。見れば、天井が無闇に高い。この高さだと、自分が転がっているのは床だな、と九雀は気付いた。そう言えば、昨日はベッドに入らなかった気がする。厳密に言うのであれば、昨日も、と言うべきか。ここ一週間で、ベッドに入った日が、一回以上あった記憶がない。興味があることに没頭してしまうと、どうしてもそれ以外を忘れてしまうのだ。自分はともかく、肉体の方はちゃんとベッドで寝かせてやった方が良いというのは知っていたが、この場合不可抗力なので仕方がないと思う。風呂にも入っているし、歯も磨いているから、大目に見て欲しい。誰ともなしにそんな言い訳じみたことを考えながら、のそのそと体を起こせば、革表紙の本が胸からばさりと落ちた。確か、読んだ者は必ず発狂するという本――UDC組織からはくれぐれも読まずに燃やしてくれと頼まれていたが、面白そうだったので勝手に読んでいた――である。さて、どこまで読んだのだったか。躊躇いなくページをめくっていけば、本を開いたままで眠りに落ちたせいだろう、開き癖のついたページに行き当たって、ああ、と九雀は呟いた。そう、男が子供と出会ったところまで読んだのだった。さて、続きはどうなるのであるかな。期待と呼ぶのが相応しいような気持ちで、九雀は更にページをめくる。
(しかし――発狂と言うが、これのどこに狂う要素があるというのであるか?)
甚だ疑問であった。何しろ、中身はただの戯曲である。それも、随分と出来が悪い。記憶を失った、名もなき主人公の男が、悪神に出会って戦に身を投じ、無垢なる子供と出会って――今、己の何たるかに懊悩している。欠伸が出そうなくらいつまらない。床へ敷いたラグの上にあぐらで座り、本を読み進めながら、九雀は、最後に何かあれば良いのであるがなぁ、とぼんやり思った。例えば、不可思議な力で異世界の知識を無理矢理植え付けられて頭の中をかき回されるようなことが起これば、それはそれで面白いと思う。外宇宙の知識やら、人知を超えた生命体の論理を知るのは、世界が広がって楽しいから好きだ。ページをめくる。男が、子供を殺して捧げよと悪神に命ぜられていた。その犠牲こそが、悪神を強くするのだからと。
――違う。『子供を犠牲にしないために』、『男は子供を犠牲にするよう頼まれたのだ』。
ふと、そんなことが頭を過ぎって、九雀は手を止めた。何故そんなことを思ったのか、よくわからない。大体、矛盾している――犠牲にしないために犠牲にする、とは。結局それは、子供を犠牲にしているのに違いないだろう。しかも、命じられたのではなく頼まれたなどと、それではまるで、悪神と男が対等であるかのようではないか。この本の二人は、明らかにそんな関係ではない。
(……ふむ)
まあ良いか。いくらかの思索を経て、九雀はその結論へ至った。何のことはない、ただ、面倒になったのだった。元より、考えるのはさして得意ではない。おそらく、生来からそうなのであろう。第一、下手の考え休むに似たりと言うではないか。そういうものはそれを得意とする者に考えてもらえば良いと九雀は思っている。己の判断に責任が伴う局面でのみ、九雀は考えることとしている。今度は間違えたくない――と、思うからだ。そう考える理由はわからない。だが、元より自分の頭は、失くした記憶の虚で穴だらけである。そんな中をいくら探し回ろうが、理由が見つかるとも思えない。ならば、深く考えたって、仕方ないのだろう。そういうものだ。
それより、九雀は今、本の続きが気になっている。
男は子供を殺せなかった。だが、それを怒った悪神が子供を殺してしまった。よくある話だ。これを書いた作者は、凡夫ではあるまいか。そも、悪神は怒ったのではないと思うであるが。悪神は、子供を生贄として欲していたのではなくて、ただいつまでも自分の手元に置いておきたかっただけであろう。九雀はそう思う。なんとなく、である。それに男を利用しようとして、失敗し、挙句拒まれたので、結果として自分の手で殺すことになった。――というのが、この真相だろう。
であるから、全て頓珍漢なのであるよな、この戯曲は。なおもページをめくっていくが、内容のつまらなさに段々飽きてきて、九雀は姿勢を崩すと、本を床へ置き、前のめるようにして読む。それでも止めずに読み続けるのは、単に『読めば発狂する』という前評判が気になっているからに過ぎない。
九雀は、自分が少しおかしいことには気付いている。というより、人格と記憶に幾つもの修復不可能と思しき欠落があることに気付いているというのが正しい。それらのおかげで、九雀は自分を自分で定義しなければ自分を保てない。壊れているのだ――壊された。そして彼は、それが常人にはない欠落であることも理解している。だからと言って、それらを疎ましいと厭うたことはない。その欠落があってこその自分なのだと思っているからである。
けれど――そんな自分が狂えばどうなるのか、試してみたいとは思うのだった。
破滅願望ではない。只々、純粋な興味本位である。何故ならそれは、おそらく『楽しい』ことだからだ。それが『楽しい』ことだと、九雀は、『知っている』。
――そうして最後の一ページを読み終わって、九雀は、本を閉じた。
「……拍子抜けであるな……」
何も起こらなかった。読めば発狂するとは一体何だったのか。男が悪神を殺し、男がまた記憶を失って、放浪するという結末は、いかにもチープである。こんなもので観劇料は取れんであるぞ、と九雀は本を、その辺りに積んだ。つまらんな。UDC組織に言われた通り、後で暖炉にでも放り込んで燃やすとしようか。とは言え、この環境配慮に煩い昨今、暖炉なんぞに本を突っ込んで燃やすと怒られそうな気もするが。それに、こんな呪本が、大人しく炎にまかれて燃えてくれるものであろうか。燃やした後に本棚を見たら、何でもない風を装ってそこに鎮座している、などと言うことも有り得そうである。それならば、燃やす労力と薪が勿体無いだけではないか。
しばらく考えた末に、九雀は、やはり面倒になって、燃やすのをやめた。UDC組織も、九雀が収集家であることは知っている。その上で彼に渡すということは、この本が収集物の一部になっても構わないと考えてのことなのであろう。うむ、そうに違いない。九雀は一人頷いて、ばね仕掛けのように飛び起きると、ぐんと背伸びをした。それから、積み上げた本の山を幾つか跨いで窓へ近付くと、厚いカーテンを勢いよく開いて外を見た。いつもの薄暗い森である。時間はわからない――この部屋に時計はない。
とは言え、森を見る限りまだ日も出ている。最近は予知もないし、日光浴と運動がてら、グリモアベースにでも顔を出して、面白い仕事でもないか探すとしよう。出来れば、コレクションが増えそうな依頼が良い。
そうして、九雀は装備を整えると、上機嫌で屋敷を出たのであった。
(了)