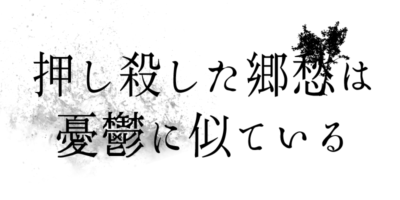小説リハビリの一篇。モブUDC職員二人のビデオ通話。枯れ山梔子直後、青薔薇前の話。
※「我らに祈りは届かない」と「エイミー・ギーズは葛籠雄九雀が嫌いである」のモブ職員二人の話です。
時差数時間の日曜日
「いやあ、失敗しましたね」
『おや、失敗しましたか?』
日曜日、デスクトップのパソコンに映し出されたビデオ通話の画面では、白頭にモノクルの老人が一人、微笑んでいた。現在時刻は昼の二時である。老人の方は、おそらくまだ明け方か。自分としては別にもっと後の時刻でも構わないのだが、何故かこの老人は、必ず陽の方に合わせて日程調整をしてくれる。こんな時間から起きていて疲れないのだろうか、とも思ったが、老人はいつも「この老い耄れにはもう、夢なんて眩しすぎるんですよ」と言うばかりなので、陽は話題に出すのをやめていた。それに、話に聞くところによると、この老人は、陽以外の誰に対してもそうであるらしい。いつ寝ているのか、甚だ疑問であったが、仕事に差し支えがないのであれば、特に問題はないだろうと言うのが自分の、そしておそらくこの老人の持論でもあるのだった。世界がそれで回るのであれば、老いた小男一人の寿命が多少短くなることくらい、本質的にはどうでもよいのである。きっと。
そんなことを考えながら、陽はため息交じりに「失敗しましたよ」と言葉を続ける。
「あの人があんなに怒っているとは思いませんでした。折角、あなたから対応の仕方を教えてもらっていたのというのに……」
『ははは。木戸君もまだ若いですねえ』
「まあ、あなたに比べたら、そうですよ」
静かな部屋には、自分と老人の声しか聞こえていない。欲しくなかったので、陽の家には家族などいない。ペットもいない。大体、棺桶にちゃんと死体を納めてもらえるかどうかもわからない生活をしているのだ。そんなもの、足手纏いにしかならないだろうと思う。陽に兄弟などおらず、親は既に他界している。事故や病気、自殺他殺などではなく、単なる老衰であったので、葬儀は恙なく、今は小さな仏壇が一つあるばかりである。五十にもなれば、そんなものだ。
――神も仏も今更信じちゃいないのに、何故だか位牌は欲しくなるのだから、人間というのはたちが悪いと陽は思っていた。
邪神邪神というけれど、陽はあれを神とは思っていない。陽にとってあんなもの、単なるデカい怪物であった。あれが神を証明すると言うのなら、自分は何度でもそれを殺そう。故に、陽の世界に神はいない。無論仏も。
椅子の背に体重を預けると、ぎ、と鈍く音がした。
「やはり表情がわからないと、致命的なところで失敗しかねませんね。怖いですよ」
『あんなにわかりやすい御仁もそうそういないんですけれどねえ』
「調子がいい時は、実際、あれほどわかりやすい人もいないとは思いますよ、私も」
狂人の相手というものを、陽や老人は、仕事上、よく行う。あの仮面はその類で、あれと相対するのは、悪く言えばうんざりする、よく言えば慣れた――仕事だった。正気が怪しい部下なんて、陽の元にも、老人の元にも、当然の如く存在していた。何かが切欠で爆発する者もいれば、勝手に狂気の渦に落ち込んで帰って来られなくなる者もいて、それらを、陽たちはいつも管理しているのだった。少し大きな事件があれば、医療チームにさえ正気を失う者が現れ始める。そう言う仕事だった。
だから、それを考えると、あの葛籠雄九雀という仮面は、どちらかと言うと、御しやすい類の狂人なのは間違いがなかったのだ。誰彼構わず暴力を振るうわけでもないし、物を与えておけば部屋に籠って大人しい。時折論理の飛躍を見せる時はあるものの、大概の場合話も通じるし、肉体の方を粗雑に扱わなければ、比較的『気の良い男』という立ち位置で動いてくれる。考えていることも割合はっきり言ってくれるので、仕事のパートナーとしては、然程悪くはない狂人なのだった。少なくとも、陽にとっては。
「あの人が、自分の肉体に関すること以外で怒ることがあるとは思わなかったんですよね」
『ああ、なるほど』
「もっと、他のものはどうでもいいと扱っているのかと」
言いながら煙草に火を点けると、老人が『お互い体に悪いものが好きですねえ』と笑った。
「肺癌で死ねたら幸いですよねえ」
『死ねたら、確かに幸運ですよね』
何しろ死体が残るし、カバーストーリーも必要ない。遺品整理も、ずっと簡単だ。
「異次元に連れて行かれて死んだりするのは、出来れば御免ですよねえ……」
『はは、木戸君は、それが一番嫌な死に方ですか?』
「と、言うか、せめて死体は残って欲しいんですよね……」
空っぽの棺桶を火葬に出す度、陽は思う――『この棺桶に入る人間は、本当に居たのだろうか?』と。肉以外の何が残っていたって、そんなものは、『確かなもの』では有り得ない。『事実を覆い尽くす虚構』というものを、自分たちはどれほど作り上げてきたと思っているのか。自分たち全員で作り上げたあまりに尤もらしい虚構が――この棺を生み出したのではないと、誰が言いきれるのだろうと。誰が、己らの正気を証明できるのかと。
この棺を燃やすことこそが、我々の狂気の一端なのではないか、と。
「証拠が……欲しいんですよ。私は。私がいたことの」
だから、死体が残らない死に方は、どれも嫌です。陽はそう言って、煙草の灰を皿に落とした。カーテンも閉め切った夏の部屋には、パソコンの唸りと、エアコンの溜息が満ちるばかりである。
『肉は証拠足り得ますか?』
「ええ。……私にはね」
『ふふ、同じですよ、木戸君』
「何がです?」
『葛籠雄君も、同じなんですよ』
そこに『在る』ことを、肉でしか実感できない。
『逆に言えば、肉以外は、判断の外なんです。だから、あの人は、他人の肉を損なうようなことは、嫌がるんですよ』
「……それはつまり、志弦が『他人の肉を損なうようなことをしたから』怒った?」
そして、肉を損なわないので、怒りで志弦の精神にヒビを入れるようなことをした。
肉を損なわないから――『許せない自分』を殺してしまう、ということができる。
『そうそう。それだけですね』
「はあ……成程」
『多分ですがね、形の無いものがわからないんですよ、彼』
言葉でも、肉でも。
感情でも、心でも。
――陽が吸う煙草の煙に、形はない。老人が続ける。
『彼は実存に縋るしかない。本質はとっくに失われているので』
「……彼曰く、空っぽだから?」
『そう。そこに在ることだけは確かだと、それだけが、彼の持つ唯一のよすがなんですよ。おそらくね。なので、何かしらの形にして伝えてあげるといいですよ。それと、存外、あの御仁は倫理的と言いますか、それだけはやってはいけないだろう、のラインを持っているようなので、そこに触れると多分怒ります』
そこは私もやったことがないのでわかりませんが、と老人が笑った。
「でもあの人が、何かしらの事件において『こんなひどいことはやめろ』というか、こう、それこそヒーローのような言動をしているところは見たことがありませんが」
何なら、時々――陽の言う、『頭の調子が悪い』時だ――、一般人を殴り倒している時もある。仕事の邪魔だったからとか、そう言う理由で。およそ良心のある者の行動ではない。
『ああ勿論、常人よりはラインが非常に下だと思いますよ』
「それはないのと同じでは?」
『そう思っていると痛い目を見ますよ』
あの人以外のところでね。老人は笑っている。
『私たちは簡単に、そして一言で、狂っている、と言いますがね。狂人と呼ばれる人たちは、私たちとは首の向きが違うだけなんです。彼らの道理があり、倫理があるだけなんですよ』
私たちの大多数とは違うところを見ているから、狂っている、と称するだけで。
『あの人たちから見れば、私たちの方が狂っているのかもしれない。それをちゃんと弁えるべきです。ゼロと限りなくゼロに近いだけのものを一緒にするのは、迂闊ですよ』
「……すみません」
陽は素直に謝った。老人の言が正しかろうと、間違いであろうと、確かに、『そこを一緒にしてしまう』のは、危険だとは思ったのだった。
限りなく死に近いことは、死とは同義でない。
それと同じことだった。
「因みに、あの人は、今どうしています?」
『どうも何も、普通ですよ。いつも通り、屋敷に籠っていらっしゃる』
「予知などは?」
『特にありませんねえ』
「そうですか」
まあ、次もまた陽の管轄地域で事件が起きるとは思わないが。日本も広い。
『それじゃあ、私もそろそろ仕事の用意をしますのでねえ』
「承知しました」
ありがとうございました、と締めて、陽はビデオ通話を終了した。
――しかし。
(形の無いものがわからない――というのは)
見ようによっては、哀れなのだろうな。そう言えば、あの仮面は、魔術や呪術が記載された本や、本そのものに問題がある類のオブジェクトは欲しがるが、口伝の怪異譚や感染型UDCなどの、『無形』のものには然程興味を示さない。怪異譚が本としてまとまったものなどは偶に読もうとするが、それだけだ。
「……『許せない自分』を、殺して葬って……」
『許せる自分』として生きる。
あの仮面は、そうやって生きてきたのだろうか。
これからも生きていくのだろうか。
狂人は、向いている方向が違うだけ。老人の言葉を、陽は考える。
空の棺を――陽は恐れている。
形の無いものを。
(……位牌を)
欲しがるのは。
たちが悪いな、と陽は、やはり思った。形が欲しい。容が欲しい。多分我々は、肉の檻に入っている限り、『肉体』という棺桶に収まっている限り、その欲を捨てられないだろう。
いずれにせよ、次はもっと上手くやれる。
陽は煙草を皿に押し付けて消すと、欠伸を一つして、休日の午後を惰眠に費やすべく、寝間着に着替えるとベッドに滑り込んだのだった。
(了)