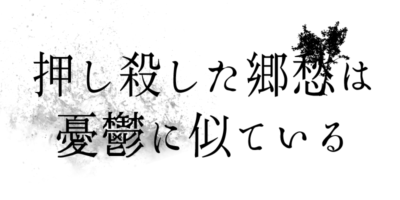去年隙間で書いていた枯れ山梔子の蛇足のような話。彼と別れて喫茶店に行くまでの二十分間。
※名前有りのモブUDC職員が二人ほど出て来ます。また、九雀がモブに割とひどいことをしています。
※問題があれば消します……。
我らに祈りは届かない
支部の廊下を、仮面の男が歩く。黒にくすんだ木製の仮面には、視界を得るための穴も、呼吸のための穴も一切ない。何の継ぎ目もない、一枚の板から削り出されたと思しき仮面で顔を覆った男は、およそ真っ当な人間とは思えぬ様相である。構造上、まるで前など見えぬはずのその仮面で、猫背の男は、廊下をすたすたと迷いなく進んでいた。
異様である。だが、通りすがる職員たちは、誰も男を指摘しない。それは男が猟兵であるということも理由だったが、どちらかと言うと、現在の支部において、男に話しかける余裕のある者がどこにもいなかったと言う方がより正しい理由だった。
とある研究者との面会を終えた眼帯の猟兵が去った支部の中は、妙に慌ただしく、そして騒々しかった。男は――否。男がつけている仮面――葛籠雄九雀は、その理由を問い詰めに来たのだった。なお、件の猟兵は現在同行していない。必要もないし、今回九雀が明らかにしたい内容はあまり愉快な話にならないだろうと言う予感があったので、それくらいならばどこかで待っていてもらった方がよいと判断したのであった。
はっきり言えば、九雀は、彼にしては珍しく、やや怒っていた。最初に取りつけた予定と今日の面会の内容が違ったからである。『猟兵ならば多少のことはどうにかできるだろう』。そんな根拠無き楽観によって予定を変えた職員がいたということが、九雀は気に入らなかったのだ。とは言え、自分一人であったならば、然程気にはしなかっただろう。いつものようにどうでもよいと言って、早々に屋敷へ帰っていたはずだ。面倒なのである。では何故こうして、一人支部の中を彷徨いているのか。理由はひとつだ。
今回は、自分が転送させた他人が同行していた。そこが、どうにもいけなかった。これでも九雀は、グリモアを使う責任があると思っていた――それは『誰かを戦地に送り出す力』だからである。
自分のミスで自分が傷つくのは仕方がない、ただの自業自得というものだ。他人のミスで自分が傷つくのもまあ別に構わない。謝ってもらえるならば勿論、謝罪がなくとも、離れてしまえばよいだけであるし、一々目くじらをたてるものでもない。よって、『自分だけが傷つく』というのは、彼の中では比較的どうでもよいことに分類される。怪我をすると肉体も痛がるような感覚があるので、できれば傷つきたくはないが、そもそもその事態に陥ったのは九雀及び他人のミスによるのであり、そこに対してああだこうだと難癖をつけても、責任の所在は変わらない。論って攻撃するのは面倒くさいし、やる気もない。すべてのものはミスをするようにできているからだ。上手く動く機械ですら、それこそ神ですら、失敗する時はする。失敗を否定するほど、九雀は己が上等でない自覚があった。だからこそ、九雀はそれを『どうでもよい』と判断するのだった。
しかし九雀がグリモアで他人を巻き込んでいる時に、彼の協力者が『およそ納得できない都合で、不利を強いてきた』となると、まるで話が変わってくる。
その場合、傷つくのは九雀ではない。彼が巻き込んだ他人である。痛い思いをするのも、血を流すのも、他人だ。その痛みと血の責任は、九雀にある。九雀は自分のせいで他人を傷つけるのは『もう二度と』御免だった。猟兵である以上死ぬことはないと知っていても、傷に痛みを伴わないわけではないと彼は理解している。
更に言えば、九雀は基本的に、武器がないと何も出来ない類の猟兵だった。だから、今日のように完全なオフの状態で急遽そんなことを言われてしまうと、大層困るのだ。本当に。一度武器を取り上げられたままUDCの事件を解決しに行ったことがあるが、あまり何度もあのような状況には遭遇したくない。あの時の裁縫針は、今も屋敷の机の引き出しで眠っている。九雀は裁縫が出来ない。
大体、武器を持ってくるなと言ったのは支部の方だった。件の猟兵の方については構わないが、知らない猟兵が武装していると真澄を刺激するかもしれないから、出来るだけ軽装で来てほしいと、約束を取りつけた際の職員は言った。成程それも道理であるなと思ったからこそ、九雀は武器を屋敷に置いてきたのであり、それを言い出した方から反故にするのはどうかと思ったのである。
そんなに器用な、あるいは万能な生き物ではない――少なくとも九雀は。武器だって、投げることしか出来ないのだ。この肉体を使い始めてから多分三年か四年ほど経っていたと思うが――正直曖昧だ。そんな記憶さえ、既に欠け落ちている。ただ、春を、それくらいの数だけ見たと思う――、それくらいしか、九雀は未だに上手く出来ない。
だからこそ、彼は予知の際も出来る限り情報を集めてから頼むのであり、その責任があると思っていた。『自分の判断のために他人を傷つける』のは、もう、嫌なのだ。――傷つけたのはいつなのか、誰なのか。そんなことは一切、覚えていないけれど。
(……何者が死のうが、さして興味もないはずなのであるがなぁ)
そんなことを考えて、仮面は少しばかり首を捻る。そもそも、九雀は、自分が優しくないことを知っていた。正しく言うなら、自分が極めて薄情な類であることを知っていた。他者を殺すことをよいこととは思っていないが、死んでも別に気にしない。興味のないことに対しては、地面を歩く蟻程度の認識しかない。それが誰かの死であったとしても。九雀はそういう性質だった。第一、弱者だから守るだとか、死なせてはいけないとか――そういうものは、どうにも理屈が通らない気がして好きではなかった。傷つけてはいけないというのなら、どんな相手でも傷つけてはいけないのだ。敵であろうと強者であろうと痛みは等価であるのに違いなく、そこへ線引きをするのはどうも性に合わない。だからやはり、単に薄情なのだと九雀は己を評していた。等しく興味がない。それだけだ。それにどうせ、『もう、誰のことも特別にはしない』。その確信があった。
そんな自分なのに――自分の判断で他人が傷つくことだけは、たまらなく嫌だと思う。
責任を取りたくないからではない。『そう言うことはもうやめた』――もう、と考えるならば、昔は『そう』だったのだろうか。相変わらず記憶にはない――つもりだったし、そも、それを承知の上で九雀は判断をしている。だから、責任を取ることに異論はないのである。では何故嫌なのか。正直に言えば、何か具体的な理由が思い浮かぶわけではなかった。漠然と、ただ、胸の内側がざわめいて不愉快になる。『それだけはもう嫌だ』と思う。それなら、自分が盾になった方が余程よい。だから避けたい。それしか九雀にはわからない。
『もう』。
九雀の行動原理には、流石の仮面でも気付くほどには、『もう』が多い。もう二度と、もうやめた、もう嫌だ、もう特別は作らない。つまり自分は――多分、何か取り返しのつかないことをしでかしたのだろう。形を失った、過去の底で。後悔したかは定かでない。後悔というのを、九雀はあまり好かないからだ。「あんなことをするんじゃなかった」と言うのは何の意味もない思考だと思うし、どうせ同じく思考をするなら、「次はこうしよう」と考える方が建設的であるはずだと仮面は思っていた。だからやはり、後悔はしていないのだ。それはおそらく、単なる変化だった。分岐で、欠落で、断絶だった。自分の空虚は、そういうことだ。
悔やむことさえしないから――がらんどうなのやもしれぬ。そんなことも思った。
食べたのか捨てたのか。どちらにせよ、チョコレートの箱は既に空っぽだった。焦げた箱の中には最早何もない。どんな味だったのか、形だったのか。きっと九雀は、もう一生知り得ないのだろうと思う。
それでも仮面は、その中身を愛していたから、その箱を未だ大切にしている。
そのようなことを考えながら、仮面は目当ての場所に辿り着いて立ち止まった。
(……はてさて。どうしてくれようか)
閉ざされた白い扉の前で様子を窺えば、聞こえて来るのは言い争うような、語気の強い、複数の声だ。流石に何を言っているかまではわからないが、まさかこの調子で楽しくお喋り中というわけではあるまい。面倒臭い。率直にそう思った。ここでなければよいのになあと部屋名を確認するが、プレートはどう読んでも第三小会議室だった。面倒には面倒が重なるものであるな、と九雀はげんなりして肩を落とした。先程適当に捕まえた職員から聞き出した情報によれば、ここに今日の面会に関与した者がいるはずだと言う。他人の顔をまともに覚えられない九雀が何故そんなことを聞き出せたのかと言えば、単純に、今朝、迎えの職員より予定変更を告げられた際、誰からの指示でそんな変更があったのか、名前を聞いていたからというそれだけによる。
支部の喧騒から薄々察してはいたが、どうも中々面倒なことになっているらしい。事情を聞いて文句の一つも言ってから、今後はあまりしてくれるなよと釘を刺して帰るだけのつもりだったのだが、思ったより時間がかかりそうであった。これなら後日にすべきだったかとも思うが、事実というものは時間が経てば経つほど手に入れにくくなるものだということを九雀は知っていた。記憶と真実と事実は別の物である。そして今九雀が欲しいのは、記録に基づいた記憶でもなく、誰かの主観による真実でもなく、自分が精査すべき事実だった。そう考えると、逆にこの状況は幸いであったのかもしれない――面倒の渦中に首を突っ込むという行為の煩わしさに目を瞑れば。丸まっていた背を伸ばし、そう言えばそろそろ肉体の方に水分を摂らせねば、と九雀は現実逃避のようなことを考える。これだけ暑いと脱水になるだろう、熱中症は困る。これが終わったら何か飲ませるか、と思いながら、九雀はノックを二つ三つして待つ。中から開けられるのを大人しく待っていたのが何故かと言えば、カードキーだったので、彼では開けられなかったからというそれだけである。開けられるのであればとっくに中へ入っていた、そもそもこのように明らかな内輪揉めに付き合う義理など、九雀にはないのだ。保障された生活の分は働いているつもりである。
ポケットからスマートフォンを取り出して、時間を確認する。あまり時間がかかるようなら流石に諦めるか、と思いながら元に戻したところで、扉が開いた。現れた黒髪黒目に黒いスーツの――九雀は彼らを記憶することを半ば諦めつつある――男が、少し微笑んで、九雀を見た。首から下げた社員証には、木戸陽、と書いてあった。名字は『きど』でよいのだろうが、名前の方はどう読めばいいのか、振り仮名がなかったので九雀にはわからなかった。
「ああ、葛籠雄さん。丁度良かった」
「む?」
どうやら、彼らの方も九雀のことを求めていたらしい。柔和な――それでもどこか苛立ちか何かを滲ませた――顔立ちに微笑みを浮かべて、男が「少し確認してきますので」と背後に声をかけてから扉を閉めた。
「お連れの猟兵さんは?」
「今はおらんであるが」
「それは、」そこで男は顎に指を当て、一度言葉を区切ってから言った。「益々丁度良い」
「ふむ、どういう意味での『丁度良い』であるかな」
思惑によっては、オレも出方を変えねばならんが。九雀は淡々と言う。武器がなくても、オブリビオン相手以外ならばやれることは多少ある。万一攻撃された場合、そこまでされて黙っているつもりはあまりなかった。木戸が、慌てたように手を振る。
「ああ、悪い意味ではないんです。むしろ、安心しているというか……」
「つまり?」
「あの猟兵さんは、真澄のことを……ええ、まあ、少なくとも、差し入れをするくらいには気にかけておられるでしょう。だからあまり、この場に居て欲しくなくてですね……」
「……成程」
漸く話が見えた。
「その部屋におる者が、真澄を、……ふむ、察するに、殺そうとでもしたのであるか?」
「仰る通り――と言う程はひどくないのですが……」
「死なせるつもりはなかった?」
「死なせても構わないとは思っているようでしたね」
「はあ」
過激派と言うのはどこにでも居るのであるなあ、と九雀はどうでもいいことを思った。
「あの猟兵さんが使っておられたユーベルコードがあったでしょう。あれを使っていただくつもりであったようですね」
「なにゆえ、そこまでしようとしておったのであるか」
「真澄には薬が効かないのです。術の類ならば、まだどうにか効くのですが」
「ふむ、そうなのであるか?」
「ええ。詳しいことはお伝えできませんが」
「とすると、その職員ちゃんは――真澄を信じられなんだのであるな」
「はい。……尤も、彼を嫌う者は一定数いますので、その者が特別というわけではないのですが……」
ここに来た以上仲間なのだから、受け入れてしまえばいいのに。
木戸が小さくそう言うのを、九雀は聞いていたが、無視した。部外者の自分が肯定するのも否定するのも違うだろうと思ったのであった。「それで」と、仮面は続ける。
「それで、わざわざ直接会わせてまでユーベルコードを使用させようとしたわけであるか。……オレたちのことを、道具か何かだと勘違いしておらぬか、その職員ちゃんは?」
「申し訳ない」
「責めておるつもりはないのであるが。すまぬ、少し呆れておる」
「呆れられるようなことをしたとは思っています。ですから、我々としても、猟兵さん方との関係が悪くなるのは避けたかったので、丁度良かった、と口にした次第です。怒るにせよ何にせよ、ネガティブな感情は抱かれるでしょうから」
「ふーむ。個人と組織を一緒にするような性質の者ではないであるし、特にそのあたりは問題ないと思うであるがなぁ」
否、実際のところなど、九雀にはわからないのだが。自分は彼のことをそこまでよく知らない、というか先ず、九雀はあの事件の当事者ではない。あの場にいた彼らが何を考えて『そう』したのか、九雀は本当の意味で知っているわけではなかった。自分が知っているのは、過程を省いた、結果だけである。
そしてそれは、目の前に居る職員も、中に居る職員も、おそらく同じのはずだった。
あの結末の場に、UDCの職員は、一人もいなかったのだから。
「というか、聞いた以上どうせオレが伝えるのであるが……一緒ではないか?」
「この場には、当人が居るので」
「別に、激昂して職員ちゃんを殺したりはせんと思うであるぞ」
「ああ、いえ、そちらを心配しているのではないです。あの方はそんなことしないでしょうから。逆です」
「……嗚呼、承知した」
九雀は一つ頷いて、男の言わんとするところを理解する。彼らは、『職員が激昂して、猟兵に襲い掛かる』ことを危惧していたのだ。UDC職員が、猟兵を傷つけることを。
「流石に、その時はオレが間に入るであるぞ」
「それが一番怖いんですよ。葛籠雄さん、あまり手加減しないでしょう。いつ頃のことでしたかね、情報を吐かせようとして信徒の眼球を抉ろうとしたことがあったじゃないですか」
「む……職員ちゃんにそこまではせんであるよ」
「ちゃんとあなたの思考の下で動いている時は、でしょう、それは。咄嗟の事態に『反射で動いた時』、どうなるか。葛籠雄さん、あなた――」
木戸が、鋭い目で九雀を――否、『九雀が使っている肉体』を見る。
「――その体、何らかの戦闘訓練をしていたものだとお見受けしますが、その肉体の『反射』を『抑え込んで』、『手加減する』ということが、ご自分にちゃんとできると思ってらっしゃるんですか? 『殺す気で襲ってきた人間』を相手に?」
「……わからん」
正直に答える。第一、自分は、この肉体がどんな訓練をしていたのかも知らない。木戸がため息を吐いて、「ですよね」と言った。
「しかも葛籠雄さん、誰かを庇った時などに自分を強化できる類のユーベルコードをお持ちでしたよね? それで容赦なく急所を狙われたら、最悪死にますよ」
「何か、暗に責められておらんであるか?」
「責めてはおりません。事実を述べております」
「事実」
「事実です」
まあ確かに事実であるな、と思ったので、九雀は何も言わなかった。彼の体術は元より、肉体の反射に助けられている部分が大きいので、それを主体に動くことが多い。要するに、木戸の言う通り、九雀の意思による手加減がしづらいのだ。自分の性格的にも、咄嗟に制止がかけられる類ではない。男の言葉はまったく間違っていなかった。
「ですから、『丁度良かった』んですよ。本当に」
「ふぅむ……」
「ところで、当人から話を聞いていきますか?」
「今、木戸ちゃん本人から『会わない方がいい』と言ったような意味合いの言葉を聞いた直後であったように思うのであるが?」
「会わない方がいいとは申しておりませんよ。あなたが誰かを庇うような状況になるのは良くないです、と申しました」
「そうであるか?」
「そうです」
「そうであったか……」
何と言うか、大分癖の強い職員であるなあ、と九雀はぼんやり思った。九雀の住む屋敷を管理している支部の支部長も相当癖と押しの強い男なのだが、この木戸陽なる男性職員も中々である。もしかすると、UDC組織なんぞで働いている以上、多かれ少なかれ職員は皆、変人ばかりなのかもしれない。
「心外ですね。それに、葛籠雄さんは人のこと言えないと思いますが」
「そういうところなのであるよなあ。読心術でも備えておるのか?」
「読心術も何も。葛籠雄さんはだいぶわかりやすいですよ」
「……そんなにわかりやすいであるか?」
むしろ、一般人などには、表情の変わらぬ仮面であるため、怯えられがちなのだが。
「まあ、『頭』の調子が良い時のあなたは、と但し書きはつきますが。私たちのところへ来る時は大概調子がいい時ですからね、あなた」
「ふむ。頭の調子?」
「頭の調子です。調子が悪い時の葛籠雄さんは結構やりにくいので、出来れば近寄らないで欲しいですね。滅茶苦茶なことをする時ありますし。UDCオブジェクトの一つや二つ、貸与も譲渡もしますから、少なくとも私個人としては、あの屋敷に籠って居て欲しいです」
ひどい言われ様であった。
「木戸ちゃん、周りからいい性格をしていると言われんであるか」
「ええ、言われます。性格が良いと評判で」
「それは絶対に意味が違うと思うのであるよなあ」
「それで、会われます? どうします?」
「……そうであるなあ……」
暑さによる気怠さと、ここへ至るまでの面倒に対する憂鬱はあったが、九雀は元より、『それ』を知りに来たのだった。スマートフォンを取り出して、時刻を確認する。まだ、彼と別れて十分程度か。
「ふぅむ。五分程度、時間を作ってもらえるか?」
「わかりました。話をしてきますね」
木戸が「少し待っていてください」と言って、部屋の中へ帰っていく。そうして、一分と経たず再び顔を出した木戸に招かれて、九雀は会議室へと入った。
然程広い部屋ではない。飾り気のない時計が一つかかった白い壁と、窓を覆うブラインドがどこか妙な息苦しさを感じさせ、九雀としてはあまり好ましい部屋ではなかった。座っているのは数人の男たちで、カタカナの『コ』の字に並べられた机に、『きちん』と座っている。その光景に、九雀は、記憶に彼らの顔を留める努力を、完全に放棄した。
何しろ、全員代わり映えのしないスーツを着用していた上、ほぼ同じような短い黒髪に黒目で、まあ眼鏡をかけたり小さな黒子があったりはしたものの、およそ特徴らしい特徴がなかったのだ。無論、一応区別は出来る――区別は。出来るだけだった。
しかし、何か既視感のある配置である。これは過去に関係なく、見たことがあるものだ。新聞か何かだろう、おそらく。
「どうぞ、こちらの椅子へ」
「ああ、すまぬ……」
木戸が――名札という発明に九雀は感謝している――、キャスター付きの椅子を引いて、九雀を座らせてくれる。どうやら、彼が今まで座っていた席に座らせてくれるらしい。オレは立っていてもいいのだが、と言いかけて、木戸が自分の傍らへ立つ意味に気付いて、言葉を止めた。この位置は、九雀を制するにも、件の職員を制するにもよい位置だ。何しろ。
「……何を考えているんですか、部長。猟兵を連れて来るなんて。……しかも、無関係の。彼はただ、予知をしただけの猟兵じゃないですか」
「そうだね。だから、そう構えなくてもいいよ、シヅル君」
机を挟んだ木戸の正面に、件の職員がいる。
コの字型に並ぶ机、その真ん中に一つ、椅子が置かれていた。その椅子に座る、シヅル、と呼ばれた男と、木戸の席は、机を挟んで、対称の位置にある。そこで漸く九雀は気付いた――成程、裁判所に似ているのだ。となると、木戸の位置は、裁判長なのか。これは最早、既にほぼ査問会なのではないか?と九雀は少しばかり思った。失敗したかもしれない。首の名札を見れば、シヅル、とは、志弦、と書くらしかった。初見で読む自信はなかった。今朝聞いた名前と違わぬ名字である。確か、シヅルアキユキ、だったか。名札によると、漢字は志弦明之と書くようだった。
「ただ、君が考えていることをどうしても知りたいと仰るので、来てもらっただけだ」
いやどうしてもとは言っていない。できれば知りたい、程度だ。誇張して伝えるのは勘弁願いたいのだが。そう思ったが、他人の会話に口を突っ込んで話をややこしくするのも嫌であったので、九雀は黙っていた。
「……猟兵さんたちまで巻き込んだのは、申し訳ないと思っていますよ。やるなら、自分でやるべきだった」
「そうではない」木戸が、先程までとは打って変わって冷たい声音で言う。「何度でも言うが、『仲間に危害を加えようとした』ということなんだ、君の問題は」
志弦が、目を見開いた。しかし、この男、かなり若いように見受けられるが、一体幾つくらいなのだろう。人間の年齢はよくわからない――正直に言えばどんな種族でも――ので、九雀はいつも、当人や周囲が扱うように扱うことにしている。特に当人の自己申告に従っていれば、それは本人が『そのように扱って欲しい』ということなのだから、問題が少ないだろう、と考えている。そもそも、彼の周囲には、齢百でありながら見た目は若い青年に見える者たちや、まず年齢ではなく稼働年数と言った方が正しい者――あるいは物――が多い。自分自身についてもそうなので、九雀にとって、年齢という概念は、あってないようなものなのだった。
「……仲間?」
そんなことを考える九雀の前で、志弦が口を開く。震える若い男の声は、どこか興奮したように上ずっていた。
「あの男が、仲間ですって?」
「そう、仲間だ。志弦君、君は若いから、わかっていないのかもしれないね。我々が行っていることは、『仲間を信じなければ、明日の朝日すら拝めなくなる』ようなことなんだよ」
「わかってますよッ!!」
木戸の言葉に、志弦が叫ぶ。
「だから、僕は! 僕は、あいつから、本音を聞かなきゃいけなかったんです!」
「本音を聞いたら、信じられたのか」
「……ッ」
「違うだろう」
敵であることを確かめたかっただけだろう、と木戸は言った。
「しかもそのために、何の承認も得ずに、真澄と猟兵を会わせたね。真澄が――あるいは彼に類する扱いの研究者たちと外部の誰かが直接の面会をするには、然るべき手順での承認が必要なことは、知っていたはずだ」
「……知っていました」
「真澄を信じられないのは、仕方がないよ。理解をしてあげられる。だがね、志弦君」
九雀の傍らで志弦を追い詰める木戸の声は、何の感情も滲まず、淡々としている。これが本来の木戸なのか――などとは、思わなかった。
「君は……その感情故に、『私たちを裏切った』。それは確かなことなんだよ」
『仲間を、自分たちを、せめて信じて欲しかった』。
木戸はただ、そう言っているだけだった。
「この場での裏切り者は、君なんだ」
「……、っ、……!!」
絶句した志弦が、椅子を蹴倒して立ち上がる。暴れるわけでもなく、ただ立って、木戸を睨んでいた。
「――人殺しを、」
若い男が、吐き捨てるように言う。
「人殺しを、どうして信じられますか。仲間だなんて、言えますか。あいつが家族を教団に殺されたのがどうしたって言うんですか。だから、人殺しを許せと言うんですか。結局、自分がされたのと同じことを、あいつも他人にやったんじゃないですか!!」
「そうだね」
「部長だってわかってるんでしょう! あいつが殺した被害者たちにだって、あいつが率いて操っていた所員たちにだって、買い取った女の子たちにだって、家族はいたんだ!!」
「そうだ、そうだよ。君は正しい」
「そうでしょう!? 自分がひどい目に遭ってきたからって、他人にその怒りを、悲しみを、ぶつけていい道理なんか、権利なんか、どこにも、誰にも、ないじゃないですか……ッ!!」
「そうだ。ないよ」
「だったら、」
「でも、それは君にも同じことが言えるんだ――志弦君」
わかっているんだろう、と木戸が言った。
「『だから』、私はね。彼に、この支部で研究者として生きていく道を提示したんだ。勿論、私だけが決めたわけではないけれどね」
「……だか、ら……」
「それと」よろめく志弦に、木戸は続ける。「所員たちは操られていたわけではない」
彼らは自分の意思であの工場に集っていたんだよ。
「どんな形でも、もしかしたら、それは『救い』だったのかもしれない。それを取り上げたのは、我々だ。いつだって我々は、『誰か』の『何か』を『取り上げている』んだ。それを、忘れてはいけない」
「……そんな……そんなの……」
「それにね」
傍観していた九雀の方を、ちらりと木戸が見る。
「猟兵が、狂気に陥らないと、君は思っているのか?」
「え、」
「あのひとたちだって、別に万能じゃない。『世界を救ってくれる』だけだ。私たちよりも、ずっと上手くユーベルコードを使えるだけだ。猟兵も、狂う時は狂うんだよ」
真澄が本当に、所員たちを操っていて、更には腹に一物持っていたとして。
「万が一、真澄に、猟兵が二人も操られた場合の責任を。一時的にでも狂ってしまった時の責任を――君は取れるのか?」
あれは、不完全でも、自身を贄に神を降ろしたことのある男なのだぞ。
「……」
オレなら絶対嫌であるな、そんなものの責任を負うのはなあ、などと考える九雀の前で、真っ青になった志弦が後退り、倒れた椅子に躓いて後ろにひっくり返った。その様子を見るに、そこまで考えた上での行動ではなかったらしい。
「もう一度、はっきり言おう。この場における『裏切り者』は君だ、志弦君」
崩れ落ちた男は、最早項垂れるばかりで何も言わなかった。
「……さて、葛籠雄さん。お待たせしました。何か彼に質問されたいことはありますか?」
「この状態でそれを訊くのであるか?」
流石に驚いて、聞き返してしまった。志弦とやらは既に呆然として、何を訊いたとして、答えられるかどうか定かではないというのに。木戸が首を傾げる。
「ええ。今回葛籠雄さんたちは被害者でいらっしゃいますし、自白剤を飲ませてでもご質問には答えさせますが」
「いや……」
そこまではしなくていいのだが。というか周囲を見てみろ、憐れみの視線が志弦ちゃんに集まっておるではないか。尤も、九雀としては、木戸の言葉は大凡同意できるものであったので、仕方があるまいな、としか言いようがないのだが。当然のことしか言っていない。志弦の主張も理解はできるが、『チーム』で動くのであれば、こう言った独断専行は致命的なものになり得るのだから。そんなことを考えながら、九雀は時計を見て、「特に思いつかんな」と答えた。これ以上長居をして、この査問会の前哨戦に付き合いたいとは思わなかった。
「事実は解ったであるし、オレはもう帰ろう」
「承知いたしました」
立ち上がった九雀が座っていた椅子を戻して、どうぞと木戸が扉まで案内する。そうして男が扉を開けようとしたところで、「ああ」と九雀は手を打った。
「最後に一つだけ訊きたいであるな」
「何でしょう?」
「間違っていれば誠に申し訳ないのであるが、明之ちゃんは――」
振り向けば、九雀が名前を出したためか、僅かに顔を上げて、こちらを見ていた。
「――『人を殺したかつての自分』を、きっと、『許して欲しくなかった』のであるよな?」
許されてしまったその日から、ずっと。
そんな権利などないのに、『他人に怒りと悲しみをぶつけてしまった』日から、ずっと。
「ずっと、『許された自分』が、『許せなかった』のであるよなあ、明之ちゃんは」
「……あ」
何かが。
「そして、今、正ちゃんに対して、同じことをした。今度こそ『許されない』ために」
「あ、あ」
志弦という男の中で、壊れたような――表情だった。
「ああああ……ッ!」
「可哀想になあ。今度こそ、『許されなかったら』よいであるな」
弱々しく呻いて蹲り、頭を抱えて丸まった男に、乾いた哀れみを投げながら、正解だったか、とだけ九雀は思った。往々にして、自分のこういう勘は外れることが多いのだが。満足して木戸の方に顔を戻すと、カードキーを持ったまま、木戸の顔は引きつっていた。
「……葛籠雄さん、志弦のことをご存知で?」
「うん? 否、何も知らぬが。話から、そう言うことだろうと思っただけであるよ」
「そうですか……」
本当に葛籠雄さんは時々、かなり惨いことをしますよね。木戸が引きつった顔のままキーを扉に翳す。
「ふーむ」
開いた扉から外へ出る頃には、志弦はすすり泣きを始めていたが、扉が閉まってしまえばそれも聞こえなくなった。首を捻りながら、帰るために木戸と共に支部の廊下を歩く。もう用は済んだので、木戸は来なくともいいのだが、何故か男は九雀について来る。
「結局オレも、別に怒らんわけではないということなのであるよな」
こう見えて。
だからやはり、珍しく――九雀は、怒っていたのだった。
九雀の力を使って、他人を危険に巻き込んだ、志弦に対して。
「怒っていたのですか……」
「うむ。実は、ずっとな」
「そうですか」
確かに、考えてみれば当然でしたね、と木戸がため息を吐いた。
「わかりやすい、というのは撤回します」
「左様であるか? まあ、それはどうでもよいのであるが」
ただ、と九雀は言う。
「他人にぶつけるほどの怒りがあり、自分自身のことを『許せない』、『許さない』と言うのであれば――骨の髄まで『許さぬ』べきであるとは思わんであるか?」
許せない自分を完膚なきまでに殺して、葬って、その上で、『許せる自分』として振る舞うべきではないだろうか。
「どうせ、『許せぬ自分』など、要らぬであろう。そんな自分になど、何をしたって構わぬと思うのであるがなあ」
それをせず、真澄に対して筋違いの怒りをぶつけた、その性根が。
「既に自分を『許している』と思うであるし、自分が救われようとしているように思うのであるよな、どうにも」
許せない自分を、救おうだなどとは烏滸がましくはないか。
「『許せぬ自分』に、『救い』など、『幸い』など――要らんであるしな。否、あってはならぬ」
「……そこまで、自分に対して苛烈にはなれませんよ、普通は」
自分自身をそこまで憎むことは出来ないんですよ、と木戸は言った。それが不思議で、九雀は歩きながら首を傾げる。
「そうであるか?」
「そうです」
「そうであったか……」
何分か前にもしたようなやり取りをしてから、九雀は支部のロビーに辿り着く。外は晴れて、灼熱である。地面に陽炎が見えて、九雀は呻いた。さて、彼はどこに居るか。
「あの猟兵さんなら、近くの喫茶店にいると思いますよ」
「む? 何故わかる」
「この辺りでこの時間に座って長時間涼めるのは、あそこだけなので」
「成程。情報感謝であるぞ!」
上機嫌で答えて、「ではな」と九雀は自動ドアから出て行く。最後に振り返って、閉まるガラス越しに手を振れば、木戸は、同じく手を振りながら、呆れたように笑っていた。
(了)