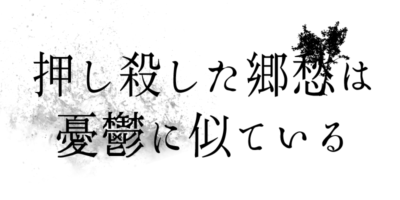小説のリハビリに書いていた多分九月上旬くらいの話。月光や青薔薇、自身の宿敵依頼への九雀の所感を含む。
※題名に出ている名前有りのモブUDC職員が半分以上出張る上に九雀を蛇蝎の如くディスります。本当に滅茶苦茶ディスります。ご注意ください。また、鼻血程度ですが、九雀→モブへの暴力表現があります。
エイミー・ギーズは葛籠雄九雀が嫌いである
何日か続いた霧のような雨で、森も屋敷も嫌な湿気に冷えていた、ある初秋の日だった。
「ツヅラオさんは」
無駄に広い屋敷の玄関ホール。
「『その
そこに立ったUDC職員の女が、自分を見上げていた。
九雀は、返事をせずに――多分、少しの驚きと一緒に――女を見下ろす。赤茶の髪に青い目をした女であった。顔に目立った傷はない。ほくろの類もない。眼鏡もかけていない。刺青などもない。狭い額を疲れたように垂れる長めの前髪に、乾燥したストレートの後ろ髪を項のあたりで結んだ、特にこれと言って特徴もない、若い女だった。着ているものもただの黒いスーツで、九雀は、明日以降にこの女を認識できるかどうかわからぬな、と思った。辛うじて、その髪と目で判別がつくかどうか。目鼻口のパーツ毎には把握できているし、目の前にあるものが一つのものだとして見えてもいるのに、どうしても記憶の中で一つの形にまとめられない九雀は、『顔』を覚えることができない。だから必然的に、個人の備えるパーツを覚えることになるのだが、それはつまり、他人と似たパーツしかないと、九雀は判別ができなくなるということでもあるのだった。
猟兵ちゃんたちのパーツは比較的個性的であるから判り易くてよいのであるがなぁ、などと思いながら、九雀は首を傾げる。
「何故、そんなことを聞くのであるか?」
女は、九雀が先程渡した、定期報告書――コレクションとして置いている様々なものと、屋敷そのものに異常がないことを完結に記した、手書きの紙――を挟んだ分厚いファイルを胸に抱えて、奥二重の瞳を、自分に向けて来ていた。そこにあるのは何だろうか。他人の感情には、然程聡くない。女が、ふと目を伏せた。
「……すみません、ツヅラオさんは、『その
少し思っただけです。細い肩を内側に丸めて、女がか細い声で言った。
「……」
沈黙して、考える。何故、この女はそう考えたのだろう。そんなことを望んでいるような素振りを、自分は一度だってしただろうか。はっきり言えば、そういったことは全く求めていないので、するはずはないのだが。空白の寂しさを埋めてみたいと――思うような性格はしていない。と言うより、求めているのであれば、とっくの昔にそう要請している。何かに遠慮したり隠し立てをしたりしようとして内に秘めておくのは好きではない。大体、求めているものがすれ違うと惨事が起きるのは『知っている』。
「ふむ、何故そう思ったのであるかな?」
純粋に疑問で、重ねて質問をする。出来るだけ、柔らかく問いかけたつもりだった。上背のある肉体と表情の変わらない自分が配慮をしない場合、怖がられることがあるのは既に学習済みである。だが女は、それでも責められたと思ったのか、「ごめんなさい」と口に出した。
「さ、差し出がましいことを」
「いや、別に怒ってはおらんのであるが……そう怯えられると逆に困るのである」
実際問題、今、心底から困っている。話が進まなくなるので、理由を訊かれただけで意思疎通に問題が出るほど怯えるくらいなら、最初から話を振らないで欲しかった。それとも、何か違う――事に依ると、彼女の好奇心を満たすように感傷的な――答えが返って来ることでも期待していたのだろうか。それは申し訳ないと思うが、そういったことは元よりあまり考えない性格なのだから仕方がない。あるいは、答えが返ってこなかったどころか質問で返されたので、機嫌を損ねたと判断したのだろうか。
さて、どうしたものか。宥める。向いていない。事実として、これほど自分に向いていないものはない。今まで猟兵として赴いた依頼の中で、一度だって、誰かを優しく宥めてやることができたか。否だ。まず、前提として、自分は髪の毛一筋ほども優しくないのである。そうする演技さえできない。ではいっそ、もっと極端に、鬱陶しいとでも断じて話を切り上げてしまうか。九雀は頭の中で、その考えを一笑に付した。それは今後の関係に影響があり過ぎる。無論、マイナスの。なお、当の女はと言えば、さっさと話を切り上げて立ち去ればいいものを、足の先まですっかり硬直してしまって、身動きが取れないようだった。うぅむ、と九雀は内心で唸る。本当に、どうしてこんな質問を、この女はしたのだろう。
回答するのは簡単だ。答えはどちらもNOである。調べられたところでこの肉体は『もうどうにもならない』と、自分は『知っていた』。そんな記憶はどこにもないが、それは多分、確かなことだった。それこそ、奇跡でもない限り。そして、自分は、奇跡などと言うものを信じていなかった。また、望んでもいなかった。九雀は今が楽しいのであり、それが『最も重要』なことだった。『楽しい』、『今』。それ以上のことは、最早求めていない。
(……ああ、)
そう言えば、あの終わりは。
初夏の頃、今日と同じ雨の中で男を連れ戻した、あの事件の結末は――奇跡と呼べるものだったのだろうか。神の贄として肉塊に成り果てた一人の男を救った、あの顛末は。
そんなわけがあるか、と九雀は頭の中で強く否定した。あれはあの事件に会した猟兵たちがその場での最善を尽くした結果であって、奇跡でもなんでもない。それを奇跡と呼ぶのはその結果を齎した者達への侮辱であろう。それくらいは、いかな自分でも理解できている。奇跡など存在しない。全ては積み重ねたものの結果に過ぎない。
では――この女は、一体如何なる積み重ねによって、そんな質問をしたのであろう。
九雀は、それが、なんとなく気になっている。
「……ついて来るがよいぞ。どうせ外は雨である、茶でも飲んでゆけ」
結局、九雀は女を招き入れて茶でも振る舞うことにした。あまりに何も思いつかなかったので、場所を変えるのがよいかもしれぬと考えただけだった。場所が変われば、自然、話題も変わる。更に、選択肢を提示すれば、この凍った女とて選ぶ必要が出てくる。断って帰ろうが、受け入れてついてこようが、どちらでも良かった。この膠着状態を打破できたことには違いない。
薄暗い玄関ホールで、女に背中を向けて歩き出せば、あ、だの、う、だのと言った意味のない呻きが二、三聞こえてから、低いヒールの足音が後ろをついてきた。静けさの中に響くその音を聞きながら、九雀は、日々の掃除以外で殆ど足を踏み入れないパーラーに女を招いたのだった。
●
エイミー・ギーズは葛籠雄九雀が苦手である。植物状態になった他人の体を好き勝手動かしているのも気持ち悪かったし、飄々とした口調で喋りながら、笑顔のまま表情が変わらない――仮面なので――のも、どこか薄ら寒い嫌悪感を抱かせた。あの有害極まりないUDCオブジェクト群を面白がって収集しているという事実も、エイミーに、おそらくある種の、憎しみと呼べるものを抱かせていた。同じくUDCオブジェクトである屋敷に住んでいるのも、はっきり言って、最低だと思った。無理矢理持たせたスマートフォンのGPSで、組織も常に屋敷の――あれが連絡手段を持ち歩かないなんてことは、最初から承知している――場所を把握してはいるけれど、ある日突然屋敷ごと消えてしまって、その辺の森の木に内臓がひっくり返った状態で引っかかっていた、なんて事件が起きてもおかしくないだろうなと彼女は思っていたし、そして、それが起きてくれたらいいのにな、なんて、多分、考えてはいけないと知っているけれど、考えていた。ユニコーンに心躍らせる少女のような心地で。でも猟兵は死なないそうなので、そんな事件は、天地がひっくり返っても起こらないのだった。きっと。消えた屋敷の『後始末』をするだけだ。その日はきっと、彼女の人生の中で、五本の指に入る最悪な日の一つになるだろう。それを考えると、今から既に憂鬱だった。大体こいつ、UDC怪物やオブジェクトが殲滅されきったら、どうすんだろ。私たちの仕事ってそれなんだけどな。他人の体で、また別の、こいつ曰く『面白そう』なものでも探して、崖っぷちでお道化るような生き方をすんのかしらね。そうだとしたら、そんなのって、あんまりにも、『けったくそ悪い』じゃないの。更に言うなら、どうせUDCの被害はあの極東の島国に集中しているのだし、その日本風の偽名を活かせるよう、そっちの方に移住したらいいのになとも思っていた。こんな屋敷、さっさと処理させてよ。恨み言なら、腐るほどあった。他の職員がどう思っているかは知らない。意気投合してる奴もいた、それも厭な事実だけど。
要するに、エイミーは、葛籠雄九雀という猟兵が、骨の髄から大嫌いだったのだ。
だから、定期報告書を受け取ってきて欲しいと――電子機器に弱いらしく、いつまで経っても書類を電子化しないところも気に入らなかった。こういう無駄な手間が無尽蔵に増える――言われたエイミーは、保険会社に偽装した支部から車を出して、愛するバッハを流しながら、このクソッタレな仕事をやり過ごそうと決めていたのだった。雨も降っていた。雨は嫌いではないけれど、森へ入るために、纏わりつく湿気の中を歩いていかなければいけないというのが、彼女の機嫌を損ねていた。
うんざりだった。UDCなんてものには。そしてそれを楽しいと称するこの仮面にも。
だから。
「ツヅラオさんは」
無駄に広い屋敷の玄関ホール。
「『その
何となく――彼女は、それを口にした。さっさと治して解放してやんなさいよ、とか、そんなことを、直前まで考えていたと思う。『それ』が、治るものなのかは知らないけど。現代医学なら、あんたがついてなくたって『生かしておく』ことくらいはできるでしょ。まして私たちの技術なら、ずっと容易いわよ。そんなことを、きっと。
だが、そんな考えは、直ぐに吹き飛んで消えてしまった。
その言葉を口にしたその瞬間、目の前に立っていた仮面が、おそらく『初めて』、エイミーを個体として認識したからだ。
あ、やっぱりこいつ嫌いだな、と反射的に脳裏を過ぎった。こいつ、他人なんて、全員、『どうでもいい』んだ。『個』として見てない。もしかすると、少しくらいは、『個』として認識して気に入っている存在もいるのかもしれないけど――例えば、時々話をしているらしい、一部の猟兵とか――少なくとも、それは、私たちのことじゃない。エイミーのことじゃない。『エイミーたち』じゃない。敵対する必要がないから『偶々味方だった』だけ、違う、『自分が使ってる肉体と同じ種族だったから』とか、『親しくしている猟兵と同じ種族だったから』とか、もっと簡単に、『外聞が悪いから』とか……そう言う、それだけの理由で『敵になってないだけ』の、『何か』だ。
ぞっとした。嫌、こんなの、さっさと殺しちゃってよ! 気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い!! そう強く願った。でもそれだけはできないんだよな。なんで? 致命傷からでも生き残る手段が、こいつにはあるから。こいつは世界に選ばれたから。『これ』は、『世界を救う』から。
(意味わかんない、意味わかんない。なんで? こんなの、こんなやつ、世界なんて、少しも、絶対、好きじゃないわよ!)
エイミーは世界が好きだ。両親が好きだ。祖父母が好きだ。兄弟が好きだ。街角のパイ屋さんが好きだ。広場の曲芸が好きだ。明るい日差しが好きだ。山を登るのが好きだ。海を歩くのが好きだ。穏やかな風に舞い上がる綿毛が好きだ。ぬいぐるみの柔らかさが好きだ。他にもたくさん、好きなものがある。
エイミー・ギーズは世界が、彼女の愛するものに満ちた世界が、好きなのだ。
愛している。
光り輝く今日と言う日を、心から、愛している。
それ故に、UDCを許せない。世界を蹂躙するのが許せない。
それを面白がる、つまり世界を愛していない、葛籠雄九雀を――許せない。
許せ、ない。
許せないから――どうだと言うのだろう。仮面が自分を『見』ている。これが腕を伸ばしてエイミーの首に手をかけ、縊ったら。それは、荒唐無稽な夢想ではなかった。あまりに脆く薄いレースのカーテン越しに揺れる、間近の現実だった。ふとした拍子に柔らかな風が一筋吹いて、そのカーテンが巻き上がったら。この仮面が、『エイミーならば殺しても構わないか』と判断したら。エイミーの『敵でない』ことをやめたら。
彼女は、死ぬ。
これは――そういう類の、質問だった。カーテンを揺らがす風になり得る。エイミーの首を絞めるに値する。『敵でない』ことを、やめさせ得る。
「何故、そんなことを聞くのであるか?」
仮面が首を傾げた。それは、猛禽の仕草に、少し似ていた。
(答えを間違ったら死ぬかもしれないな)
これでも、日本へ手伝いに赴いて、UDC怪物の始末をしたことだってある。その戦いが告げていた。中途半端に首を突っ込んだな、と。やってしまった、と思った。死への恐怖で思わず目を伏せる。大きな武器なんて、全部車の中だ。辛うじてスーツの下のホルスターに一丁だけ拳銃があるけれど、そんなもの、どれほどの役に立つというのか。ショットガンが欲しい、ライフルが欲しい、その他UDC組織から渡された色々な武器が欲しい。どれも、ここにはないけれど。だって、気に入らない猟兵から報告書を受け取るだけの仕事だったはずだもの。それにこいつは、毒を使う戦闘スタイルだったはずだ。解毒薬がなければ、武器があったとしても、相討ちになりかねない。エイミーは、一部のエージェントたちのように、UDC怪物をその身に宿してはいない。この、『世界から与えられた』、うつくしい――自然のままの肉体に、そんなものを宿すのは、心底嫌だったから。だから彼女は戦闘訓練を積んで――でもそれは、武器がある時の話だ。相手が不死身でなかった時の話だ。
目の前にいるのは、生命の埒外にある、『何か』なのだ。
「……すみません、ツヅラオさんは、『その
辛うじて、それだけ言った。それが、仮面の求める答えだったのかは知らない。車の中で流していたバッハが恋しかった。二つのヴァイオリンのための協奏曲。
勿論、今、殺されるというわけではない。これは阿呆な道化の素振りをしているが、真実阿呆というわけでないのは流石に理解している。そこがエイミーにとって嫌いなところでもあり、現状において最も恐ろしいところでもあった。これは阿呆でないが故に――今ここでエイミーを殺すということがどういうことか、理解しているはずなのだ。
だから、これはきっと、エイミーを殺さない。
そう、おそらく殺さないのだ。自分の手では、決して。それどころか、助けようとさえするだろう、この仮面は。そうして、『死ぬ機会』を待ち続ける。見殺しにしても文句を言われないようなタイミングを、「仕方なかったよ、お前は悪くない、よくやってくれたよ」と言われるような瞬間を――静かに待っているだろう。
エイミーを殺すために。
エイミーが死ぬところを見るために。
元より、UDC怪物と相対するなどという危険な仕事である。こいつは、一番よい時を見計らって、沈黙しているだけでいい。沈黙。たったそれだけのこと。一瞬だけ、振り向くのを遅らせる。一瞬だけ、武器を投げるのを遅らせる。一瞬だけ、怪物の攻撃で動けなくなってみせる……そういう、色々な、たったの『一瞬』。
自分は、それだけで、無惨に死ぬだろう。
世界を救うプロセスの中に、エイミーの命は入っているだろうか。
きっと、入っていないと彼女は思った。彼女が死んだって、きっと『世界は救われる』。
エイミーは世界を愛しているけれど、世界はエイミーを別に愛していないから。
世界は、『世界が救われれば』、きっと、それでいいんだから。
仮面が、言葉を、続ける。
「ふむ、何故そう思ったのであるかな?」
あんたが――あんたが、『他人の体を、好き勝手してる』からよ。この、××××野郎。そんなことは言えなかった。
『世界に見限られたくなかった』。
エイミーは世界を愛していた。
「ごめんなさい」
柄にもなく、声が、か細く震えるのがわかった。自分は怯えている。あんまりにも馬鹿らしいけれど――確かに。間違いなく。
「さ、差し出がましいことを」
「いや、別に怒ってはおらんのであるが……そう怯えられると逆に困るのである」
そうでしょうね。あんた、『怒ってはいない』のよ。だから怖いのよ、厭なのよ、嫌いなのよ、憎いのよ、うんざりするのよ、死んで欲しいのよ消えて欲しいのよ。
あんたが。
あんたが――『私に怒る』くらい、『他人を信頼して』いたら。
『他人』を、『世界』を、『愛して』いたら。
(私、きっと、こんなに怖くないわ)
何も信頼していない。信用していない。期待していない。愛していない。つまり、『どうでもいい』。どうでもいいから怒らない。怒っていないから、宥めることすらできない。だって、ごみを捨てる時、私たちは怒っているわけじゃない。ただ邪魔だから、不要だから捨てるのよ。
愛してないから、捨てられるのよ。
こいつには、願望も希望も欲望も、本当は、ないんじゃないか。そう思う。
空っぽだから――何にも響かない。
何にも要らない。自分の外に守りたいものもない。
故に、『恒常的な味方には決してなり得ない』。
(だから、『敵でないだけ』の生き物なのよ、こいつは!)
仮面が何も言わないので、エイミーも動けなかった。何を考えているのか、まったくわからなかった。これの思考など、今までわかろうと思ったこともないが。俯く視界の端にあった男の足先が、不意に、方向を変えた。
「……ついて来るがよいぞ。どうせ外は雨である、茶でも飲んでゆけ」
雨なんて、どうでも良かったけれど。
仮面の誘いを断るのも、やはり恐ろしくて、彼女は、その背を追いかける。
そんなエイミーの背後で――鼠の足音が、騒々しく駆けていった。
●
さて茶か。
適当に紅茶の用意をしながら、九雀は棚に入れていたクッキーの缶を引っ張り出す。
(茶菓子は……一応黴こそ生えてはおらんが。大分湿気を吸っておるであるなあ)
缶の中の除湿剤は、連日の雨に、殆ど役に立たなくなっていた。アーモンドやマカデミアナッツ、ピスタチオにチョコチップ。様々な味のクッキーたちはどれもしっとりと、と言えば聞こえはいいが、湿度のせいで元の食感を失っているようであった。
……まあよいか。悩もうと現実は変わらないので、九雀は早々に諦めた。別に、茶のために呼んだ者でもない。むしろ、想定外の来客であって、かの女も、そこを問題視はしないであろう。おそらく。するのであれば、流石にUDC組織の方に一言文句を言いに行く所存である。
ケトルを乗せたカセットコンロに火を点けて、茶用の湯を沸かす。無論キッチンにレンジ――電子レンジのことではなく、中に火を入れて調理に使用するもの――はあったが、料理をするわけでもないこの状況でわざわざ火を用意するのは面倒だった。欲しいものは一杯の紅茶であり、それ以上ではないのである。まあ、そんなことを言っておいて、別に普段ならレンジを使用しているかと言われると、そうでもないのだが。特にここ数日は薪用の枝が濡れて役に立たないので、専らこちらを使っていた。炭もなくなっていたし――連日の雨で外へ出るのが億劫になっていたために、買いに行くのを渋ったのだ。水たまりを見ると、どうにも胸のうちがざわめいて、幸せな、それなのにどこか苦しい気持ちになってしまって――もうどこにもいないはずの『誰か』に、「お前はそこで遊んでいいんだ、もう怒らないから」と言ってやりたくなって、たまらなくて――とにかく、あまり楽しくはなかったから、外に出なくてもよい手段を選ぶようになっていたのであった。尤も、不燃ごみが増えていくことを考えると、これもこれで不便ではあるのだが。
冷めきったレンジに凭れて、湯が沸くのを待つ。居間の方に座らせた女は、静かにしているだろうか。UDC職員である以上この屋敷の扱い方は知っているだろうから、要らぬことはしていないだろうが。帰っていても別に構わない、その時は自分で飲むだけである。
時代錯誤なキッチンに、科学の青い火が、静かに燃えていた。
その火から視線を外し、何となく、己のグリモアを取り出して眺める。薄っすら輝くグリモアの中には、雀蜂が一匹入っていた。本当にこれが雀蜂なのか――それともそれらしく見えるだけの何かであるのか、九雀は知らなかった。そもそも、これを手に入れたのも、つい去年だかなんだかのことで、元はヒーローズアースを記憶も当て所もなく、何となくうろついていただけだった。自分が猟兵であると言う自覚も、殆どなかったと思う。ただ、これを手に入れた自分は、もっと楽しいものと出会いたくて――これまた記憶にない『誰か』が、『知らないものを知りたいと願っていた』のを『知っていた』から――『楽しく過ごしたくて』、この琥珀に導かれるようにして色々見て回った結果、最終的にUDCアースへと落ち着いたのだった。UDCアースのUDCオブジェクトは、あの時見つかっていた世界の中で一番九雀の興味を引いたし、同時に、『誰か』も好きになりそうだなと思った、のだったと思う。よく覚えていない。九雀の記憶は、しばしば流動して、時にはつい先日のことでさえ、ばらばらになった過去の隙間に落ち込んで行方が知れなくなる。
ヒーローズアースで何をしていたのかも、実際のところ、まともに覚えているわけではなかった。ただ、適当に、復讐を願う誰かの手伝いをしていたことだけ、漠然と覚えている。戦わなければいけなかった。それが、自分が生活をするために必要なことだと思っていた。けれど、自分には戦う理由も動機も一切なかったので――他人の『理由』と『動機』を拝借していたのだった。
(……否、戦いと言うのは烏滸がましいであるな)
琥珀を指先でくるくると回しながら、自分の考えを否定する。要するに、人殺しである。他人に優しくないことを理解している九雀は、正直に言って、人を殺すことそのものに然程抵抗があるわけではない。彼が他者を殺すことを嫌がるのは、『死んだら終わり』だからだ。何者も死んだらそこまでであり、そこから先には何もなくなる。終わり、というのは、存外重たい。罪も罰も、そこで清算される。そうして、愛や幸福もまた。そうやって一切合切が終わってしまうことこそが死だ。だから、九雀は、『殺人に抵抗はない』が、『殺人をひどく好まない』という、矛盾を抱えている。似たような矛盾は、九雀の中には山ほどあった。そして、自分でも理解しているその矛盾たちは、時折彼を不安定にさせるのだった。
指を離して手のひらに転がしたグリモアが、直立した格好で僅かに浮かんだ。不思議な物体だと九雀は思った。これは何なのだろう。あいつなら調べられるのだろうか。あいつとは誰だ、知らない。九雀は知らない。それを知っていたのは、『葛籠雄九雀』ではない。九雀の胸の中は依然、空っぽである。
拝借、と言うのなら、今でもそうだった。九雀自身は理由を、動機を持たない。世界など本当はどうでもよかったし、この肉体が生きていける場所が必要なので、今のところ世界と敵対するつもりも、見捨てるつもりもないだけだった。それに、自分が万一――死ぬことはなくとも、『死んでいないだけの状況』に陥ることは十分考えられた――この肉体を守れなくなったら、誰かにこの肉体を預けなければいけなかった。それこそ、UDC組織にでも。九雀はこの肉体を死なせたくなかった。死なせないためなら簡単に傷つけられる程度には、九雀にとって、この肉体の『生』は無類のものだった。腕は、足は、命の代わりにならない。最悪内臓が一つ壊れたって、生きてさえいれば、生きてさえいたなら、治してもらえる。治してもらえたら、絵本を読んでやるから。お前の好きな話。優しい盗賊の話。それとも、鮫の話がいいか。飛び出すやつでもいいな。図鑑がいいかな。動物のにしようか、昆虫がいいか。なんでもいいか、そうだな、そうだ。ゆっくり眠ればいい。だから――だから、そう、九雀はこの肉体を死なせない。死なせないために、一緒にいる。
また脈絡のない思考をしている、と九雀は思った。絵本を――読んでいたのだろうか。読んでいたのだろう、あのUDC-Pへそうしたように。この肉体はおそらくとっくに成人しているはずだが、そんなに何年も一緒にいたのか。子供の頃から? よくわからない。記憶はない。ケトルの中の水が、音を立て始めていた。
そう言えば、いつ頃の話だったか。グリモアベースで、ヒーローズアースの予知をしているのを聞いた。グリモア猟兵が予知をするのは当たり前なのだが、その内容に――既視感があった。『知っていた』。自分は、あの予知の事件を起こしたオブリビオンを、知っていたのだと思う。ヒーローズアースに現れるオブリビオンは、皆死人だ。自分は、その死人を……知っていた。きっと、おそらく。あの時は嫌な予感しかしなかったが、今なら、思い浮かぶものがある。
笑う――男。狂った男。自分の子供を――壊してしまった――男――だ。
何者にも関わらず、自分自身ですら等しく、燃やしてしまえた――男、だった。
子供を失った男。それでも、己が選んで積み重ねた結果を、愛していた男、だった。と、思う。
その言葉たちに、覚えているのだろうか、とも考える。否、覚えていない。本当に、何も覚えていないのだ。名状しづらいのだが、『なくなってしまっている』という感覚がはっきりと存在していて、『覚えていないし、取り戻せもしない』ものなのだと、九雀は理屈抜きに理解できているのである。故に虚ろは虚ろであり、それ以上のものではない。だが、虚ろとは――空洞とは――即ち、必ず輪郭を持つから。
その輪郭が――九雀に、欠落の断片を寄越すのである。
――ふと見れば、硝子で出来たケトルの水が、ぐらぐらと沸いていた。
九雀はグリモアを握り潰すようにして仕舞うと、ポットに茶葉を入れて、壁にかけていたミトンを取って、ケトルから湯を注いだ。考えても仕方がないことだった、欠け落ちて消え去ったものに想いを馳せたとて、戻って来るわけでもない。食器棚から適当に選んだ皿の上に、缶から何枚か選んで乗せると、湿気たクッキーも多少は見栄えがした。
「……いつの日にか、オレは、それと、まみえるのであるかな」
かの、死人と。
ぽつりと呟いてから、九雀はトレンチに紅茶のポットとカップ、それからクッキーの皿を乗せると、キッチンを出た。雨に沈む屋敷は、やはりシンと冷えて、静かだった。
●
ここから、逃げ出す算段が思いつかない。
雨にけぶる森を、ガラスの向こうに見る。湿度が蛇のように渦を巻いていた。息苦しささえ覚える部屋は、カーテンで閉ざしてもいないのに薄暗い。あの仮面は、今ここに居ない。この間に、外へ出ようか。そう思った。仕事は終わった、このまま帰ったって問題はない。それなのに、何かが――エイミーの足を床に縫い留めていた。否、わかっている。恐怖だ。
自分は、恐れている。あの仮面が『敵でないこと』を、やめてしまうのを。
天井を、鼠がタタタと軽やかに走っていく。この屋敷、うるさいな。姿の見えない鼠。食害も糞害もないのに、鼠の足音だけが響く。それがこの屋敷の特徴の一つだった。こんなにうるさいなんて、思わなかったけど。なんであの仮面、平気なんだろう。あいつには聞こえてないのかな。確かに、実験だと、実験体によって聞こえ方に差が出てたけど。肉体の方は聞こえていたりするのかな。それなら可哀想だな、ストレス凄そう。でも、意識が殆どないんだっけ。なら大丈夫なのかしら。というか、意識がないって言うけど、どれくらい『ない』んだろう。あの仮面から聞くに、調子がいい時は痛みなども感じているらしいけど。そんなことを、ぼんやり考える。現実逃避だとはわかっていた。
(植物状態、って一口に言っても色々あるし)
何があってあの肉体とあの仮面がああなっているのか、エイミーは知らない。ただ、呪いの気配がするのは確かだった。肉体と仮面がいつも一緒に居るので、どちらからのものかはわからなかったけれど――あるいは両方からなのかもしれない――あれが解ければ、もしかすると記憶とか、そう言ったものが戻って来るのかもしれなかった。だが、見る限り、肉体の方は脳も損傷していそうなので、そちらは無理かもしれないとも思った。多分、あれは、本当に『生きているだけ』の肉体だ。だから余計、エイミーはあの仮面を気持ち悪いと思うのだけれど。
あれを生きていると称してしがみつくのが――心底気持ち悪い。
猟兵として活動した際の報告書などを読んでいると、あれは、あの肉体が『死んでいる』と言われるのをあまり好まないようだが――果たして、『生きている』とは、どう言ったことを指すのか。エイミーは、魂という言葉を考えている。それが本当に実在するのかどうか、彼女は未だに判断しかねるけれど、そう称されるような『何か』がないのなら、ただ『呼吸をするだけの肉塊』であるなら、それは、『死んでいる』のと同義じゃないかと思うのだ。
それで言うなら、あの肉体は、とっくの昔に、きっと『死んで』いた。
人は、一体どこで、『死』を判断しているのか。
あの仮面と肉体を見ていると、そんなことを、どうしても考えてしまう。
エイミーは、あの肉体を、『死体』だと……感じてしまう時が、どうしても、ある。
それに、あの状態で生き延びることを、あの肉体は、その家族は望んでいたのだろうか。どんな経緯であの仮面が肉体を支配するに至ったのかを知らないので、無論一概に「望んでいなかったはずだ」だなんて傲慢なことは言わないが、それでも少しは考えてしまう。あの仮面が、肉体を支配する条件とか、そう言うことを知らないから、余計。
まさか――自由に動かせる手足が欲しくて、奪ったのだろうか。
(……もしそうなら、反吐が出るわね)
他人の死体を引き摺り回して、『生きている』と主張して。望む狂気の中で踊る生活は、さぞ楽しかろう。
あまりに悪趣味な人形遊びだった。
――ダダダ。鼠が。機関銃みたいな足音を立てて走っていった。うるさい。うるさいな。この屋敷もあの仮面も、嫌いだ。嫌いだ、嫌い。
音も立てず開いた扉から、現れたのは、件の仮面だった。
「待たせたであるな」
紅茶の匂い。安っぽくはない――来客用に、ある程度上等なものを置いているのかもしれない。この仮面もそう言った気配りができるのか、とエイミーは僅かに驚いた。もっと無神経な奴だと思ったけれど。でも茶菓子は適当過ぎる。ティータイムを彩るのは紅茶だけではない。そりゃ勿論、エイミーだって、これが急な来客なのはわかっている。だからそんなに厚かましいことは言いたくないけど、流石に湿気たクッキーはないんじゃないの。それは急とか予定通りとかそう言う問題ではなく、あらゆる状況で一貫して、客に出すものじゃないと思うんだけど。それくらいなら無くても別にいいし。いやあった方が嬉しいけど、それは湿気たクッキーじゃない場合だから。ついでに言えば、クッキーが可哀想。多分これもそんなに安いクッキーじゃないのに。美味しく食べられる機会を失ったクッキーを、エイミーは何となく悼んだ。食べてはあげよう、哀れなクッキーたちのために。椅子へ座ったままの彼女の前で、仮面が茶を注ぐ。そしてエイミーはすっと眉根を寄せた。凄く、雑。
「……雑ですね」
思わず口をついて出てしまった。自他ともに認める几帳面、というか神経質な性格をしているのだが、なんというか――仮面が好きとか嫌いとかそう言うところではなく、雑なのが許せなかった。同じことを恋人がやっても、同じように怒ったと思う。そして怒鳴り合いの喧嘩に発展するのである。それを知っているので、エイミーは食卓の用意を恋人に任せないことに決めている。考えているうち、カップが紅茶で満ちたので、仮面が「ハハハ」と演技みたいな調子で笑ってから、ポットを置いた。
「すまぬな、慣れておらんのであるよ」
「いえ、こちらもすみません。つい」
「これでも丁寧にしようとは思っておるのであるがな。どうも慣れぬ」
この肉体も、料理なんぞはしたことがないようでなあ。そんなことを言いながら、仮面がエイミーの向かい側に座った。本人は茶を飲まないつもりであるらしい。
「ツヅラオさんは飲まないんですか」
「うん? ああ、飲まぬ。毒など入っておらんから、安心するがよいぞ」
まあ、職員が毒殺されたら問題でしょうしね。一口飲んでみた紅茶は、渋かった。だからあんた、何もかも雑なのよ……。無神経というより雑なのだな、とエイミーは悟った。物でも人でもこうやって雑に扱うので、無神経であるように見えるのだろう。それは無神経とどう違うのかと思わなくもなかったが、気を遣うという発想自体はあるようなので、気の遣い方が雑、という結論へ至った。帰ったら口直しにお気に入りの店に行こう。エイミーはそう静かに決めた。
「さて」
仮面が椅子の背に凭れる。
「落ち着いたであるかな」
――そうだった。そう言う話、だった。何故私は今、この怯えを一瞬でも忘れてしまったの? 自分自身が信じられなかった。カチン、と、カップがソーサーをぶつかって硬質な音を立てた。
「……ふむ」
仮面が、何事か考えるような仕草をした。蒼褪めた自分に、何を思ったのだろう。
「職員ちゃん――すまぬな、オレは職員ちゃんの名前を知らんのである。職員ちゃんは、何をそんなに怯えているのであるか?」
「何、を」
「オレは今まで、UDC組織の職員ちゃんたちに何かしたことなど、一回もなかったと思うのであるが」
何もしないでくださいと釘を刺されたことはあったかもしれぬが、と仮面がまた、演技じみた笑い声をあげた。そう、演技なのだろう。多分、全部演技だ。
「あなたが、」口が、勝手に動く。「あなたがそうやって、『何か』を演じて、肉体を好き勝手に使っているから」
仮面の動きが、凍ったように止まった。ああ、死んだな、私。それが解った。何故だか知らないけれど。
「演じて――いるのであろうか」
「演じているんでしょう」
「わからんのであるよ。オレには」
「役者は皆そう言うものです」
「そう――であるか」
仮面の言葉に感情は滲んでいない。実はこれが本当の仮面で、感情なんていつかのどこかへ置き去りにしてしまって久しいんじゃないか。エイミーは、少しだけそう思った。
「職員ちゃんには、オレがこの肉体を、好き勝手使っているように見えるであるか」
「ええ」
「そう、ふむ……そうであるか……」
のろのろと、融けるように、仮面が動き始める。前へ重心を移すようにして、座り直す。ぎ、とアンティークらしい椅子が軋んで音を立てた。
「オレは、『わるいやつ』に見えるであるかな」
「悪い、奴」
足元から、何度目からわからない、鼠の足音がした。気持ち――悪いな。この仮面には、これが聞こえていないのか。湧き上がる吐き気を抑え込んで、エイミーは答える。
「見えます、よ」
私には。そう言った瞬間、仮面が。
「く、」仮面が。「く、く、く」
「――……っ」
息を呑む。これは演技じゃない、これは、これは『葛籠雄九雀』の笑い方じゃない。こいつは、私たちの前でこんな笑い方はしない。いつでも朗らかに、『楽しそう』に、『今が最高だ』と言わんばかりの……笑い方をするのだ。だからこれは、『葛籠雄九雀』の笑い方じゃ、ない。絶対に。
じゃあ、『何』の?
「くくく、く」
雨降る森の、薄い太陽が差し込む一室で、テーブル越しに向かい合った仮面が、身を震わせることもなく、声だけで静かに低く笑っている。そこに在る感情は一体何だろう。
「そう見えるなら、オレはおそらく、『本望』なのであろうよ!」
尤も、オレは元より『善い奴』ではないであるがな。そう言って仮面が体を起こせば、先程垣間見えた『何か』は消えてしまって、跡形もなかった。
「成程、好き勝手使っているように見えたから、オレが自由惜しさに、この肉体を元に戻すのを厭うておるのかと思った……というところであるか?」
「……そう、です」
「そうか、そうか」
ハハハ、と仮面が哄笑をあげた。
「まあ、それだけは有り得んであるなあ」
「……」
「それに、調べてもらったことがないわけではないのであるぞ?」
「え?」
初耳だ。この仮面が、肉体を他人に見せることがあるとは。
「以前、健康診断をしてもらったことがあってな。オレでは肉体の病を見つけられん、であるから、有り難く受けさせてもらったのである」
「け、結果は」
「UDC組織の方でもどうしようもないと聞いたであるぞ。どうも、得体の知れんものの細胞やら呪術やら何やら……聞いてもよくわからなんだが、とにかく厳しいと言っておった。頭の方もだいぶやられておるらしい、少なくとも一朝一夕では無理であろうよ」
それは――否、それじゃ。
「……それじゃ、あんたは、『味方にならない』じゃない」
「うん?」
「『敵でない』だけじゃない……」
「敵でないのは事実であるが。ふむ」
仮面が、また考え込むような振る舞いをする。オーバーなリアクションをするのは――こいつには表情がないから、伝えやすくするためなのだろう。そこがまた、演技臭くて気持ち悪いのだけれど。
「ふぅむ。確かに、オレは、UDC組織の『味方』になったつもりはないであるな」
そも。仮面が言う。鼠が走っている。うるさい、うるさい、うるさい! 騒音で頭が痛い、何十匹、何百匹の鼠の気配が、そこらじゅうで走り回っている。なのに、鼠の姿は一匹も見えない。気持ち悪い、誰かこれを止めてよ! こいつには聞こえないの、これが!?
「そも――オレは『正しさ』やら、『人間』やら、『世界』やら……そう言ったものの味方になったつもりも、今後味方になるつもりも、ないのであるよなぁ」
「せかいの……みかた、じゃない」
なによ。
なによ。
なんなのよ、それは。
紅茶の匂いがする。クッキーの匂いがする。雨の匂いがする。頭が――頭の中が、めちゃくちゃになる。これは、この仮面は、世界を救うために選ばれてるんじゃないの。どうしてこんなやつが世界に選ばれてるのよ。
「だが、オレは、」「――うるさい!!」
叫んで、立ち上がる。座ったままの仮面が、エイミーを見上げていた。こいつの表情が変わるのなら、きっと、ぽかんとした顔をしていたのだろう。
「うるさい――うるさい、どうしてあんた――こんな、鼠の――中で、平然と喋ってられるのよ――ッ!!」
「……鼠?」
仮面が、女を見上げたまま、それを吐き出す。
「そんな音は、少しもせんであるが……」
「……え」
音がしてない? どうして? どうして聞こえないの? 待って、この屋敷って、どういう特性があるんだっけ。枯れない井戸。見えない鼠。迷彩する庭。それだけだった? どうやって扱えばいいんだっけ? 『屋敷が無人の場合』。それから、『屋敷に住人がいる場合』。確か、扱い方が違ったはず。ああ、鼠が五月蠅い、たまらない。
「鼠の音がしているのであるか? まさか、ずっと?」
「……」
動かないエイミーに、仮面が立ち上がる。
「職員ちゃん、今すぐ屋敷を出るのである。オレが扉まで連れて行ってやるから――」
「……うるさい……」
胸のホルスターから銃を抜いて、仮面に――否、その肉体に突き付ける。当然のように、仮面の動きが止まった。そうよね、あんたは、その肉体を傷つけたくない。『死なせたくない』。なら、止まるわよね。馬鹿らしい、そんなに大事なら、病院でチューブにでも繋いでおけばいいのよ。そうしたら、死ぬとか、死なせるとか、そう言う話からは遠ざけていられるのに。
だからやっぱり、あんたのそれは、ただのエゴなのよ。
「あんたが……」
鬱陶しい――なんで、私が、こんな、UDCオブジェクト如きで――苦しまなきゃ、いけないのよ。こんなやつら、殺して、壊して、滅ぼさなくっちゃ。
「……そうか」
あのくそったれUDCどもと、こいつは、おんなじなんだ。きっと、こいつも、UDCオブジェクトなんだ。よくあるじゃないか、人間を乗っ取るタイプのオブジェクトは。だから、この足音も聞こえないし、世界の味方にもならないし――意識の無い肉体をこうやって好きにしてるんだ!
エイミーの家族は。
エイミーの恋人は。
皆重度の植物状態で、もう二度と動けない。
かつてのエイミーが知らずに持ち込んだ、とあるUDCオブジェクトのせいだった。知らなかったのだ。あんなものがこの世界にあるなんて。
それは、エイミーが望むものを与えるために、彼女の大事なものをすべて取り上げた。それから、『完璧にエイミーの望む形にして』、再度与えた。そうして、最後にエイミーがそれらを拒んだ時……大事なものたちはすべて、玩具のように捨てられた。
完璧など、完全など。
求めるべきではなかったのだ。
不完全でも、腹が立っても、すれ違っても、それが、エイミーの愛したものだったのに。
それが、エイミーの愛した、世界だったのに。
用済みの人形たちは、今も、UDC組織が運営する病院で生命維持装置に繋がれ、ただ、息をしている。
あれを、エイミーは。
エイミーは。
エイミーは――生きている、と。
人は。
人は、一体どこで、『死』を判断しているのか。
私は、一体、どこで。
この屋敷に来てから、この仮面と肉体を見てから、女は、そればかり考えている。
鼠の足音が止まった。耳が痛くなるような静寂。私は。
私は、世界を。
「……職員ちゃん? 大丈夫であるか?」
「……殺す」
「は? 何を、」があん、と、音がして、仮面が伏せてテーブルに隠れる。鼠の足音が戻って来る、あの、気が狂いそうに不快な騒音が。
「避けるなよ、くそったれ!」
飛び上がり、クロスのかかったテーブルに乗る。いた。再度発砲すると、転がるように仮面が跳んで避けた。案外すばしっこいな。
「待て、待つであ――無理かッ」
仮面が素早く体を起こし、エイミーの乗ったテーブルをひっくり返す。ポットとカップが床に叩きつけられて、ばしゃん、と大きな音を立てた。それを見もせずに、エイミーはテーブルを蹴って跳び上がると、丸腰の仮面に照準を定める。
死ね。死んでしまえ。
「死んじまえ!」
「くっ!」仮面が避ける。「流石に笑えんであるぞ!」
「うるせえ! 気持ち悪いんだよ――お前ら! UDCも猟兵もッ!」
着地し、仮面が後退するのを追うように撃ちながら、エイミーは叫ぶ。世界が好き? クソが、そんなわけねえだろ。あるわけねえだろうが。
「私の家族は全員植物状態だよ、全部、全部全部全部UDCとか言うくそったれのせいだ、それをなあ、全部めっちゃくちゃにしてやるんだ私は! ぐしゃぐしゃにしてやる、あんなものッ!」
「それは好きにしたらよい! 猟兵は関係なかろうが!」
「ある!!」
「断言したであるなッ――」
八発目の銃弾が、花瓶を割った。空になったマガジンを交換する隙をついて、仮面が扉から逃げていく。
「ちいっ!!」
あいつに武器を回収させるのはまずい。あれは本来、遠距離から攻撃するのが得意だ。しかも毒を使うため、掠っただけでもある程度のダメージを喰らう。
「逃がすか……!!」
世界なんてなあ。
「世界なんて――私の愛した世界を奪った、世界なんて――」
いつの間にか、エイミーは泣いていた。
「――世界なんて、大嫌いよ」
そうよ、葛籠雄九雀、あんたが猟兵だと言うのなら。
救ってよ。救ってみせてよ、猟兵。
過去を殺すことしかできない、猟兵ども。
世界を救うと言うのなら、救ってみせろ。
過去に消えてしまった、私の、『世界』を。
世界はエイミーを別に愛していない。それを、エイミーは知っていた。
愛してなど、いなかったのだ。
●
(……どうするべきであるかなぁ)
九雀は、道中あった部屋の一室に飛び込んで窓の鍵を外しながら考える。
猟兵を招いていた時はこんなことがなかったので、すっかり油断していた。そう言えば、この屋敷はUDC――世界を破壊する意思を持つものなのであった。つまり、あの女性職員はそれに支配されてしまったということなのだろう。まあ、正直に言わせてもらえば、UDC職員ならば、そんなことにならないで欲しかったと言う気分だった。迷い込んだ一般人に襲われるならまだしも、正気を失った職員に襲われるとは。何のために研究をしていたのだ。大体、他の職員たちは、普通にこの屋敷で本を読んで帰ったりするのである。ということは、今回訪れたあの女性職員に原因があるのだろう。こちらは職員のパーソナルデータなど知らないのだから、組織側でしっかり注意して配置して欲しい。今更愚痴を言っても仕方ないのだが、溜息の一つでも吐きたい気分だった。別に九雀は人間のような呼吸をしているわけではないので、吐きたくとも吐けないのだが。なお、ではどこから声を出しているのか、と訊かれると、「さあ?」としか答えられない。仮面の裏側に食事を放り込んだら消えるし、食感はわからないが味もわかるし、『空腹』が『満たされる』感覚もある。比較的その感覚を好むので、九雀は食事を摂るのを好む。よくわからない生き物である自覚はある。他のヒーローマスクが同様なのかは知らない。ただ九雀はそういう生き物だった。
それはさておき。
(流石に、殺すのは忍びない……というより、他の職員ちゃんからの評価が怖いであるな)
どこに行った、と叫ぶ女の声を聞きながら、九雀は漸く鍵を外せた窓から出る。降り続ける雨で、全身はすぐ濡れた。これが終わったら風呂でも沸かすか、と九雀は思った。
オキザリス・パルマで宙を蹴り、九雀は二階に跳ぶ。とりあえず武器を手に入れなければ話にならない、職員に書類を渡すだけで終わるつもりだったから、全て自室――というより、単純に一番よく使う部屋――に置きっぱなしにしてしまっていたのだ。目的の部屋の窓に辿り着くと、九雀は張り付くように枠に掴まり、雨が降っているので閉めていた窓を、強引にこじ開ける。ここからガゼボの様子を見ることが多いので、すぐ声をかけられるようここの窓には鍵をかけないようにしていたのが幸いした。尤も、かけていたらガラスをぶち破っただけなのだが。この屋敷は殆どの場合『傷つけられるのを嫌う』が、己の『住人』か、その『客人』が行ったことならば許してくれる。と、言うより、住人と客人に対しては、不干渉となるのだ。要するに、住んでいる者と、それに招かれた者にとっては、殆ど普通の家なのである。
だからこそ、あの女性職員が正気を失った理由がわからない。
九雀はあの職員を、『客人』として認識していたはずだった。
濡れた体を中に滑り込ませ、振り込む雨に部屋が晒されぬよう窓を閉める。積まれた本を避けながら、コートハンガーに引っ掛けていた武器ベルトを回収したところで、二階に走って来る女の足音が響いた。くそ、と毒づいて、九雀はベルトからワイヤーを外す。どうやら、ベルトをつける時間は与えてくれないらしい。存外これは、装着に時間がかかるのだ。
(まあ構わん、下手にユーベルコードを使って殺してしまったらかなわぬ)
本音で言えば、殺してしまってもいいかとは思っているのだが――迷いなく肉体を狙ってきていたことが、九雀は少しばかり気に入らなかったのだ。あの迷いのなさには間違いなく、『九雀』ではなく、『肉体』への憎悪があった――九雀とあの女性職員では、まず『正当防衛でした』は通用しないだろう。手加減をしようと思えばできる筈だからだ。加えて言えば、『猟兵は致死ダメージからでも真の姿さえ解放すれば助かる』のである。それは、あの女と九雀における決定的な違いだった。それがある限り、どう説明したとしても、信用と評価は落ちるだろう。それは避けたい。
ただ――この肉体が傷つくくらいならば、九雀はあの女を殺すつもりである。
UDC組織がどう思っているかは知らないが、彼らからの評価のためにこの肉体を犠牲にするなど本末転倒にも程があるのだ。彼女と自分のためにも、出来る限り穏便に済ませたいものであった。
あー、と、溜息代わりに呻き声を漏らして、ワイヤーを構える。面倒であるなぁ。頭の中で吐き捨てる。ポットとカップも割れたし、服も絨毯もずぶ濡れだし、彼女のために使った茶葉もクッキーも無駄になった。現時点で、およそ碌なことが起きていない。
「そこ、か――ッ!?」
扉を蹴破って銃を構えた女に向けて即座にワイヤーのフックを投擲し、引っ掛けて強引に巻き取る。跳ね上がるようにして拳銃が吹き飛び、床の上に転がった。それを拾おうとする女より先に飛び込んで、部屋の隅まで蹴り放す。女が舌打ちして、拳を構える。よく見れば、女は泣いているようだった。何があったのか、九雀にはわからなかった。
「武器がなくとも!」
「諦めてくれんか!」
近接戦は苦手なので、やりたくはなかったのだが。首めがけて放たれた鋭い手刀を、半身を捻って避け、手首を掴む。やはりこの女、『肉体を狙っている』。肉体が動かなくなれば九雀は殆ど無力化できるからだとか、狙いやすいからだとか、明らかにそう言った理由ではない、殺意がある。何故だ。考えるより先に肉体が動いて――この肉体は時々、こう言うことがある。おそらく一連の動きがこの体の『癖』であり、『反射』なのだろう――女の腕をねじり上げた。悲鳴を上げる女をそのままうつ伏せに床へ叩きつけ、体重で抑え込む。あまりに自分の意思を離れた動きだったため、本当は自我を取り戻しているのかとも思い、頭の中で肉体に話しかけてみるが、特段そんなことはないようだった。呼びかけが響くのはいつもの、漠然とした、茫洋とした、霧のような、無我の海である。
「――む?」
それが少し、ざわついていたような――感覚が、僅かにあった。……気がした。気がしただけであった。把握する前に、海は凪いでしまった。
(……怒っていた?)
まさかな、とは思えど、一応この体も、外部の刺激には反応するのである。怪我をすればさざ波程度であるが痛がっているような反応が伝わって来ることがあるし、そう言ったこともあるのかもしれない。九雀は人間に詳しくないので、ないとは言い切れないのであった。
「さて、職員ちゃ――」「あ」
あ?と九雀が首を傾げたのも束の間、女性職員が絶叫を上げた。断末魔とほど近いそれに思考を揺さぶられ、一瞬完全に意識が吹き飛ぶ。何、今度は何だ。ええい、次から次へと厄介事ばかり起こる。今日は何であるか、こう、日本で呼ぶところの厄日というやつなのであるか。日頃の行いが悪いか、そうか。いや、本当に悪いか? 悪いか。悪いであるな。少なくとも、良くはない。吹き飛んだ意識で自答して、九雀は彼方から戻って来る。
「――喧しいッ!」
最早ここまでくると、我慢しようと思って出来るものではなかった。勢いで怒鳴り、女を見下ろす。大体、この肉体を殺そうとした人間にまで優しく丁寧な対応をしてやれるほど、九雀は大人しい性格ではなかった。
「何なのであるか、先程から! いい加減にして欲しいのであるぞ!」
「い、いいいいいい、ああああああああああああああ――――――」
駄目だこれは。完全に錯乱していて、聞く耳がない。こうなると、あまりやりたくはないが、仕方ないだろう。怨むならUDCに飲まれた己を怨んで欲しいし、叱るなら九雀ではなくこちらを叱って欲しい。頼む。うんざりしながら、大音声で叫ぶ女の髪の毛を掴んで、九雀は床にその顔面を思い切り叩きつけた。鈍い音が鳴り、そこでようやく女が黙った。肉体の鼓膜が心配だった。
「……落ち着いたであるかな」
先程と似たようなことを口にして、九雀は髪の毛を掴んだまま、顔を上げさせる。鼻血で赤黒く染まった顔と、焦点の合わぬ女の目が、自分の方へ向く。
「ね、鼠」
「またそれか。ほれ、さっさと出るであるぞ」
髪の毛から手を離し、襟首を掴んで引き摺り立たせる。体から力が抜けていたので、もう抵抗しないだろうと踏んだのだ。案の定、女は黙って九雀の言う通りに動くだけであった。さっさとUDC組織に引き渡して、風呂に入りたい。切実に。ああでも、暖炉に火を入れるのは面倒だから、今日はもう、別の場所でシャワーでも浴びてくるか。帰ってくる時に結局雨で汚れてしまうが、それを差し引いても、疲れが溜まっていた。それから、壊れた家具や小物の修繕についても検討せねば。そんなことを考えながら、猫でも連れるように二階を降り、玄関ホールへ辿り着いたところで――それは起こった。
「……ツヅラオさん」
「今度は何であるか……」
もう二度とこの女を屋敷の敷地に入れないで欲しい。組織にはそう打診しよう。そんなことを思いながら、引き摺っていた女を見下ろせば――女は、真っ青な顔で、九雀を見上げていた。
「鼠が。鼠が、私の足を、齧っているんです」
「は……?」
また妄言の類である。そんなものはどこにもいない。一匹も。
「い、いや、私を――私を、たべないで!」
九雀の腕を振り解き、女が何かから逃げるように扉へ走った。だが、転ぶ。そのまま女が丸まって動かなくなるのを、仮面は振り払われたままの姿で見ていた。
「……は、ま、待て!」
突然のことに硬直してしまったが、我に返って追いかけ、転んだ女の襟首をまた引っ掴むと、今度は立たせずにそのまま引き摺り、扉を蹴り開けて外へ放り出した。シャツの布地と女の重さに巻き込まれて、バキ、と爪の折れる音がしたものの、そんなことに構ってはいられない。どちゃ、と、ぬかるんだ地面に女が転がった。屋敷からは出せたが、どうか。
「……生きておるか」
女を覗き込んでみて、九雀は一つ頷き、全てを諦めた。そうして屋敷から傘を一本持って来ると、女のスーツから鍵を取り、敷地の外へ止めてあった女の車まで赴いて、中に置いてあったスマートフォンで組織に電話をした。内容は簡単だった。「職員ちゃんが一人再起不能になってしまったようであるのでな、迎えを寄越してくれ」。それだけだった。
●
「いやあ、災難でしたねえ」
「災難でしたねえ、ではないのであるよなぁ」
殺されそうになったのだが、こちらは。九雀は応接室のソファへ深く腰掛けて、目の前の男――老爺と呼んだ方がよいか――を見る。白髪の、小男である。九雀が一緒にいるこの肉体より、二回りほど小さい、痩せた老人は、これでもこの辺りの支部の支部長であった。要するに、九雀の生活の一切については、彼に管理されているようなものなのである。因みに、名前は知らない。九雀が覚えていないのではなく、ただ単に、誰もこの男の本名を知らないのであった。爺さんとかとかなんとか、自由に呼ばれている。九雀はと言えば、彼を『老人』とだけ呼んでいた。見たままである。
「元に戻りそうであるか?」
「はっはっは」
「いや、笑われてもオレは困るのであるが」
本当に。今回はまったく、信じられないくらいのひどい目に遭った。尤も、あの女性職員――エイミー・ギーズと言ったか、あの女もそう思っているのであろうが。現在彼女は、精神科の病棟で拘束されて投薬され続けている。それがどういう状態を指すのか、想像には難くなかった。
「まあ、いつかは」
「いつか……」
「いやあ、はっはっは」
「いやあ、ではないのであるぞ。笑っておるが、あれは何だったのであるか」
「知りません」
朗らかに即答されたので、九雀もオウム返しに「知りません」と言ってしまった。言うに事欠いて知りませんと来たか。仮面は疲れてきて、自分の額を抑えた。
「……知りません、であるか……」
「いえ、まあ、推測は立ちますよ。ギーズ君は、あなたを嫌っていましたからねえ」
「オレはエイミーちゃんの顔も知らなんだがなあ?」
「それは葛籠雄君だからですねえ。実はこの支部の中でも何回か遭遇していますよ」
「なんと」
「そう、なんと」
「……職員ちゃんたちの『カタログ』でも貰っておいた方がよいかもしれんであるな」
「どうせカタログを見ても、現物と顔が一致せんでしょう?」
「目の前に居たら流石にわかるであるよ」
「目の前に居ても意識に入れなければ無意味なんですがねえ……」
小男が、モノクルの位置を少し直した。
「ううん……まあ、ギーズ君はねえ、実際、正気の危ういところがありましたからねえ」
「そんな者を寄越さんでくれぬかな……」
「葛籠雄君が、メールで書類を送ってくれるようになってくれたら彼女も行かなくて済んだんですけどねえ。あの日、手すきなのは彼女しかいなかったんですよ」
「む、ぐ……」
使えないわけではなく、積極的に使いたくないために我儘を通している、と言った立場の九雀は、老爺の言葉に言葉を飲み込んだ。だがそもそも、あの屋敷は電気がないのである。仕方がないのではないだろうか。否、そこを言うのであれば、あの屋敷に住むなという話になってくる。あの屋敷にはまだ住んでいたかったので、九雀は沈黙した。
「ギーズ君ねえ。『ドールハウスに並べた人形たちを、植物状態になった家族だと思い込んでいる』、可哀想な子でしたね」
我々が間に合ったのでね、彼女の家族は助かったのですが。
「彼女は助からなかった。真っ暗な部屋で、与えられた人形を抱き締めて泣いていた。それが彼女の家族になってしまったんですねえ、哀れにも」
狂人にも道理はあるんですよねえ、と老人は淡々と言った。
「本物の家族は?」
「生きてますよお。ただ、ギーズ君は、彼らを自分の家族だと認識できませんからね。下手に立ち入られても困るので、家族の方々にはギーズ君に関する記憶をすべて消去して普通に暮らしてもらっています。彼らにエイミーという家族は、もういないんですよ。いえ、最初からそんな人間はどこにもいなかった」
「滅茶苦茶なことをするであるな……」
「そうですか? 人道的でしょう」
「そうであるかなあ……」
そうは思わんであるがなあ。九雀は唸るようにそんなことを呟きながら、ローテーブルの上に出されていたクッキーを半分に割った。ちゃんと乾燥しているクッキーだった。仮面の下から差し込んで、肉体に食べさせる。もう半分は、己の裏側に放り込んだ。うむ。甘くて美味い。
「エイミーちゃんの『それ』は、治るものなのであるか?」
「どうでしょうね? 時間をかければ、治ることもあるとは思いますよ」
「左様か」
それだけ答えて、九雀は肉体の喉を動かすと、咀嚼したクッキーを飲み込む。何故治してやらないのか、であるとか、そう言ったことを訊く気はなかった。老人が言う。
「人である、というのは、どう言うことなんでしょうねえ?」
「知らぬよ。オレは人ではないであるし」
「だから聞いているんですけれどねえ。人同士でそんなこと話し合ったって不毛でしょう」
「身も蓋もない……まあ、オレには、人の容をしてさえおれば、人に見えるであるがなあ」
「ははあ、成程ですなあ。『目に見えるもののみを信じている』というわけですねえ」
「信じるも何も。それが全てであろう」
「では、ギーズ君は、『正しかった』わけですねえ。見えるものが全てなのであれば、彼女は家族や恋人と、一生会えないのが『正しい』んですよねえ。それが彼女の『世界』であり、『正しい』姿なんでしょうねえ」
「……何が言いたいのであるか?」
「何も。私は単なる老人ですしねえ。歳だけ取ったから、こんな場所にいるだけでねえ」
「……」
九雀は無言で、二枚目のクッキーを割った。
「中指の爪。折れてしまったんですってね」
「折れたであるよ。ついでに、全部の爪を切り揃えた」
「まあ、『傷つけたがらない』のも程々に。日常生活に支障が出ますよ。髪の毛とかも。人間はある程度傷ついて生きていくものなんですからね」
「……何かしら、わかっているような口振りであるな」
「別に。私は一介の元医療班ですよお。ただ私は、あなたの守っているその肉体が、ひどい実験の末の産物であることを知っているだけです」
「ひどい――実験、だったのであるかな」
半分に割れたクッキーを、九雀はまた、肉体に食べさせる。
「オレは、そう思わんよ」
「記憶もないのに?」
「記憶がなくとも」
残りの半分を、自分の方に放り込もうとして――九雀は、肉体の口に入れた。菓子の類を食わせると、何となくだが喜んでいるように感じるので、仮面は、この肉体に菓子を食わせることを好んでいる。
――自己満足の、罪滅ぼしなのかもしれない、とは、少し、考えないわけではなかった。きっと、自分は、この肉体に、そんなささやかなことさえしてやれなかったから。
「葛籠雄君、クッキーだけ食べさせるのは、可哀想ですよお。口の中が、こう……もさっとしてしまいますからねえ」
「……もさっと?」
「もさっと」
この老人のオノマトペはよくわからん。「牛乳でも飲みます?」と老人が言って、ソファから立ち上がると、ひょこひょこ――おそらくあれは、足の長さが違うのだ――戸棚の方へ赴いて、小洒落た瓶の、白い液体を取り出した。
「……それは、牛乳ではないであろう……」
牛乳だったとしたら常温保存をするな。
「白くて甘ければ大体牛の乳では?」
「暴論が過ぎるであるな」
「まあまあ、まあまあまあ。あなた方、成人してるんでしょう」
「しておるとは思うが、オレは飲まん。この肉体にも飲ません」
「そう言わずに。美味しいんですよ、ピニャコラーダ」
「間違いなく酒であるなあ!」
牛乳でないことを自ら白状した老人の押し売りに負け、細いグラスに氷とピニャコラーダを注がれてストローをそっと添えられた。飲めと? いや飲まぬが。この老人の、こういうところが九雀は大層苦手であった。嫌いなわけではないが、あまり近寄りたくない。というかここは確か応接室であるはずなのだが、ほぼ老人の私室と化していないか? 老人はいつの間にか、ウイスキーを取り出して一人で飲んでいる。
「まあ、今回に関してはねえ。ギーズ君も、葛籠雄君も、悪かったですねえ。反省文です」
老人が笑った。そう言えば、役職などのせいもあるのだろうが、この老人だけは、九雀の今住む屋敷に、一度も訪れたことがない。
「仕方があるまいな」
「そうですねえ、戦闘訓練を積んだ職員を一人駄目にしたのは大きいですからねえ」
「オレのせいなのであるか? あれは」
確かに、もっと上手くやれたと言えばやれたのかもしれないが。それは結果論に過ぎないのではないか。白い頭の小男が、ウイスキーを水のようなペースで飲みながら、これまたいつの間にやら用意したチョコレートを食べている。最早何でもありである。
「勿論、葛籠雄君だけのせいじゃあありませんよお。さっきも言ったようにね。ギーズ君もねえ、葛籠雄君への嫌悪を隠さなさ過ぎた」
だから相手からも嫌われてしまうんですよねえ、と老人が、ソファの背に身を沈める。
「オレは別に嫌っておらなんだが……」
正確には興味がなかった。顔も知らない相手に何の感情を抱けというのか。
「だから、葛籠雄君が知らないだけなんですよお。ううん、ですが、そうですねえ。確かに、葛籠雄君『は』、今回あんまり悪くなかったかもしれませんねえ。まったく悪くないわけではないんですが」
「さっぱりわからん」
からん、と、手をつけていないグラスの中で、融けた氷が崩れて鳴った。
「ねえ、葛籠雄君」
「何であるか」
「愛とはどんなものだと思います?」
「『恋とはどんなものかしら』か?」
「いえいえ、モーツァルトではなく」
「それをなあ、オレに聞くのは間違っておると思うのであるよなあ……」
「いいじゃあありませんか。答えて欲しいものですねえ」
「はあ……まあ構わんが……」
どうも、押しの強い相手には弱い。自分の性分なのだと思う。こうやって会話の主導権を握られると、そのまま流されてしまいがちであった。
「何度でも、やり直せるものではないのか」
「やり直せますか」
「やり直せる……うぅむ。言葉にするのが難しいであるな」
「はっはっは。愛を語るのが容易であるならば、世の中もっと単純でしょうしねえ」
愛。そう言えば、あの乙女ゲームなるものの事件も、そんな話であったか。繰り返し続ける、終わりのない愛の円環。あれは恋と呼ばれる愛だったが、結局、誰かを『想う』という感情は、どれも同じようなところに行き着くのではないだろうかと九雀は考える。自分にそんなものがあるかどうかは別として。
「なくなることなど、ないもの」
「永遠?」
「永遠とはちと違うであるな……なくなったとしても、何度でも生まれてくるもの?」
「疑問形にされましても、私にはあなたの考えは判りませんからねえ」
「オレにだってわからぬよ。オレはただの仮面であるぞ」
「では、質問を変えて。『記憶を失っても、愛は残ると思いますか?』」
「……」
そんなもの。
「当然残るに決まっているであろうが」
「葛籠雄君はそう答えるでしょうねえ」
あなたがそう答えなかったら困りますよ、と老人がカラカラと笑った。一体何が言いたいのか。
「オレにそれが残っていると?」
「残っているからその体を守っているんでしょう」
「……そうかもしれんであるな」
そう言われると、否定するのも違うだろうと思ったので、九雀は曖昧に肯定しておいた。愛などというものはわからないが、この肉体を守りたいのは、事実であったから。
「ところで、反省文なんですけれども」
「うむ」
「小型のラップトップを貸すので。それで書いて来てください」
はい、と、どこからともなく現れたデバイスを差し出され、反射で受け取る。それから九雀は、「は」と間抜けな声を上げた。
「葛籠雄君、デジタルで書けないわけじゃないでしょう。丁度爪も切ったところですし」
「待って欲しいのであるが? 言っておくがオレはキーボードの配置などまるで覚えておらんぞ」
「それは良かった。これを機に覚えてください」
「オレにそんな記憶力があると!?」
「他人の顔以外なら、葛籠雄君はちゃんと覚えられる仮面だと私は知っていますよ」
「て、提出期限は」
「明後日の夕方五時」
壁の時計を見る。現在時刻は、昼の三時だった。
「待て! 待て待て!」
「はてさて。アナログで下書きをしてる時間がありますかねえ、あなたのタイピング速度で」
「わかっていて言っておるのか! おるのであるな!?」
「ほぉら立って立って。間に合わなくなりますよ。言っておきますが、間に合わなかったら屋敷からあなたのコレクションまで、全部没収して廃棄しますからねえ」
「ぬぅ……!!」
言われた通り動くのは癪だが、本当に早く始めないと間に合わない。根こそぎ没収されるのは辛く苦しいものがあるので、九雀はソファから立ち上がると、ラップトップを脇に抱えて部屋の扉へ向かう。収集家の収集物を質に取るなど、鬼畜の所業ではなかろうか。
「ああ、葛籠雄君ねえ」
「何であるか」
ドアノブに手をかけたところで、老人が言った。
「気が向いたらでいいよ。いつかねえ、ギーズ君の『世界』も、『救って』あげてよ」
葛籠雄君は、猟兵なんでしょう。
「……気が向いたらな」
まあ、オレに出来るとも思えんが。
背を向けて部屋を出ていきながら――九雀はひらりと一つ手を振った。じゃあねえ、と間延びした老人の声が、閉まる扉に遮られたのは、それからすぐのことだった。
●
「お前に娘がいることを、知っているか?」
夜闇に紛れた仮面の男は、そう言った。
●
あれからどれくらい経ったんだろうか。
鏡の中の自分は、最後に残った記憶の中の自分より、いくらか老いて見えた。だが、狂気の中で自分を取り戻すという戦いで疲弊したのだと言われたら、それもそれで納得ができるような変貌だった。肉体はそれほど衰えていないから、後者なのかもしれない。日付が知りたいと思ったが、エイミーの病室にカレンダーはなかった。
ひどい目に遭ったな、と思った。こうやって病室のベッドで寝ているとわかる、自分は、あの屋敷に入った時から、正気を失っていた。『客人』として扱われていなかったからだ。あの屋敷は、住人か、その客人以外の侵入を決して許さない。そして、どんな理由であれ、客人以外の侵入を許してしまった、住人のことも許さないのだ。要するに、あの屋敷に住んだ人間が不審者に入られた場合、住人は不審者に殺され、不審者は屋敷に殺される。そう言う理屈である。
であれば、あの仮面が、エイミーを『客』だと思っていなかったのか。そうではないのだろう、と彼女は思った。あれはクズだが――エイミーは葛籠雄九雀が嫌いだ。それは狂気によるものではない。本当に心底素面で反吐が出ると思っている――、そのあたりはきちんと割り切ることが出来る仮面である。何故なら『他人に興味がない』からだ。別に何も求めていないので、役割で人を見ることが出来る。感情と理屈を切り離せる。大体、前提として、あの仮面はエイミーが質問するまで、彼女を認識していなかった。認識していないものに対して、好悪も何もない。
だからつまり。
(……あの肉体……案外ちゃんと『自分がある』んじゃないの……)
仮面の方ではなく、肉体に嫌われていたのである。肉体が、エイミーを拒絶した。客として認めなかった。自分と仮面の領域に、入って来ることを許さなかったのだ。かくして、招かれざる客であるところのエイミーは、正気を失って仮面を、否、あの肉体を襲った。自分というものを置き去りにしていたはずの、物言わぬ男を。何故自分だけがあの肉体にそんな感情を抱かれたのかと言えば、おそらく、彼女が九雀を嫌っていたのが原因だろう。猟兵は知らないが、職員とエイミーの違いと言えば、あの仮面への嫌悪を露わにしていたかどうかくらいだったと思う。尤も、あの肉体がどれくらい物を考えられているのか知らないので、もしかしたら、彼にしかわからない、他の要素もあるのかもしれなかったが。
それを――『魂』と呼ぶべきか。
あの肉体は、仮面が言う通り、『生きている』のか。
正直、エイミーにはわからない。わかるものではないのかもしれないとも思う。
人は一体どこで、『死』を判断しているのか。
その答えは、自分には今しばらく、出せそうになかった。
(大体、そんな簡単に出せるんだったら、『人』はこんなに悩んでいないでしょうしね)
まあ何にせよ、エイミーはそろそろ退院できるらしい。訓練もやり直しだろうな。鍛えるのは嫌いじゃないけど、ブランクを埋めるのは容易じゃないだろう。世の中はどうなっているのだろうか。UDCがちょっとでも減っていたら、エイミーは嬉しいのだけれど。
そう言えば、今日はお見舞いの人が来るんだっけ。どうせ支部長のお爺さんだろう。あの人は、相手によって対応を変える類の人種なので、エイミーは彼との会話を嫌っていない。贔屓とかそう言うことではなく、『相手が正気でいられるように』、あの老人は会話をするのである。あれは技術だ。彼の前では、あの腹立たしい仮面でさえ、お道化者の様子が鳴りを潜める。尤も、そう言うところを見ているからこそ嫌いというのもあるのだが。できれば、あの仮面とは、もうしばらくは会いたくないものであった。
と、そこで病室の扉が叩かれたので、「はい」と返事をする。看護師が、見舞いの来訪を告げる。あれ、と思った。あの老人だったら、いつも看護師はついて来ない。
そして。
「――あ」
扉は、開かれた。
●
エイミー・ギーズは葛籠雄九雀が嫌いである。
なぜなら彼女は、『世界』を愛しているから。
これからもきっと、彼女は『世界』を愛し続ける。
愛とは、そう言うものだと、エイミーは思っている。
(了)